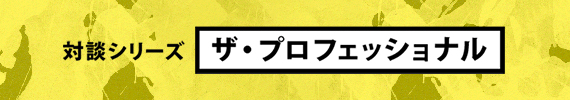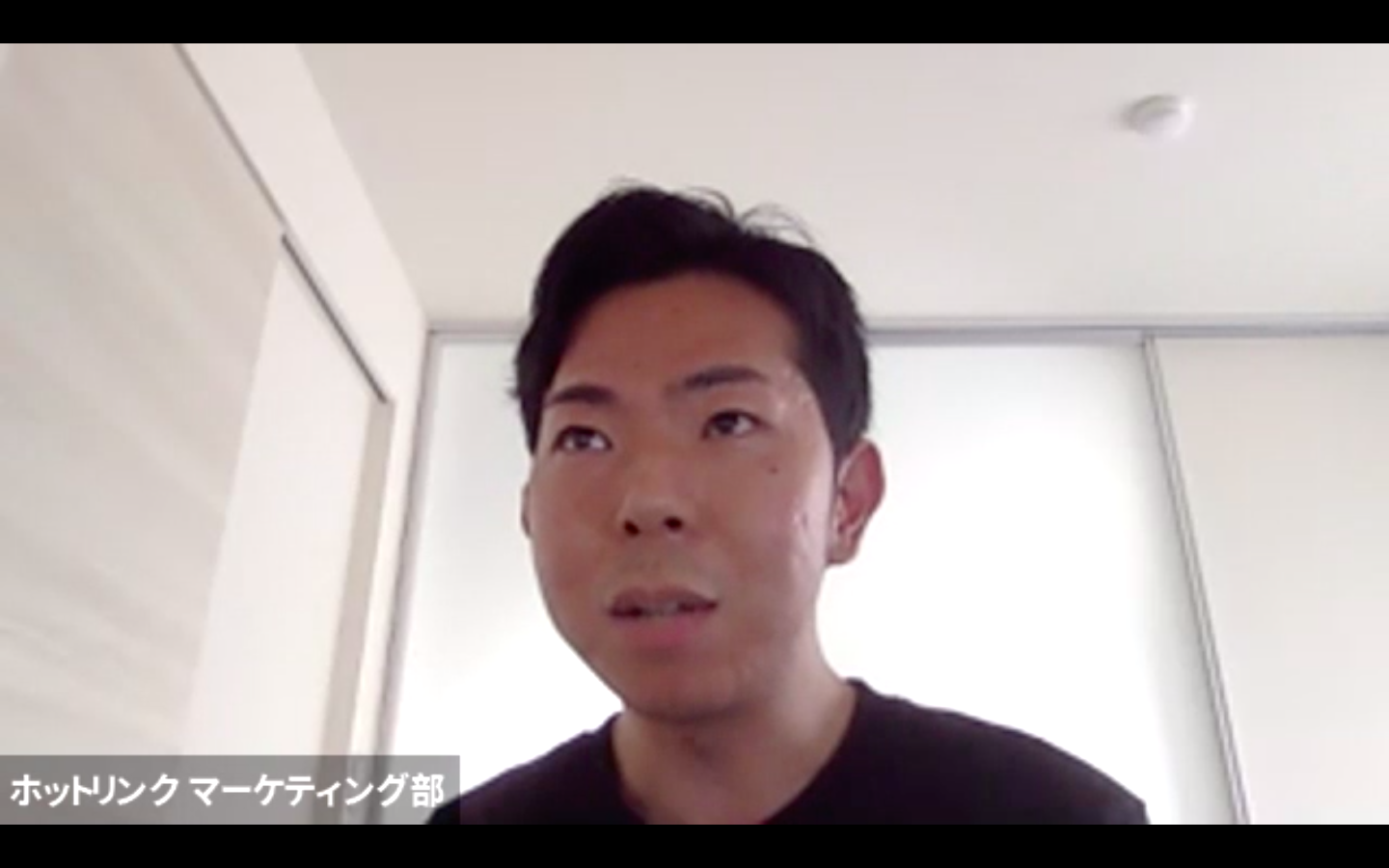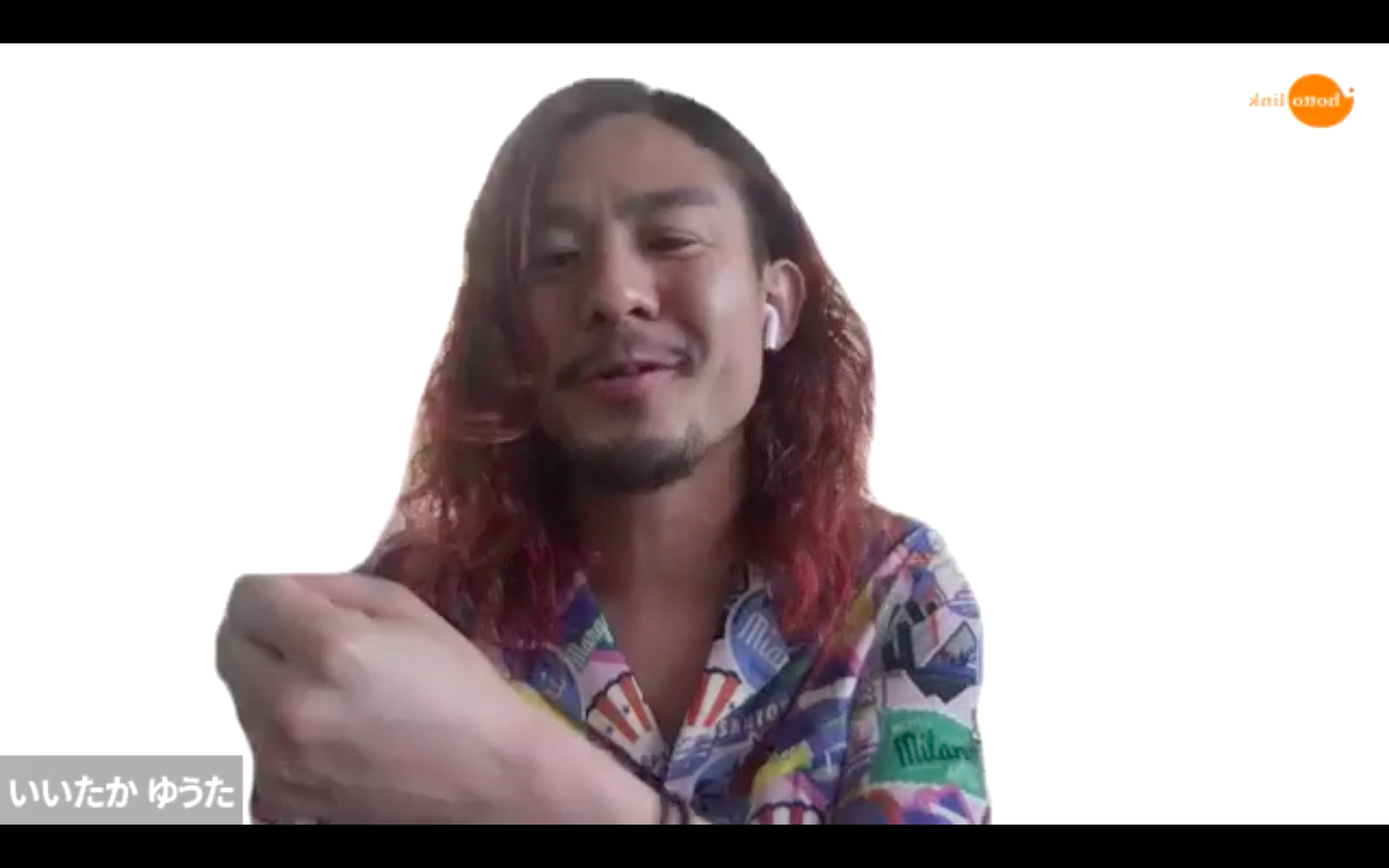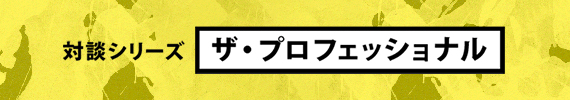前編では、鶴見教授が「SNSマーケティングを疫学の観点から解釈すると理解が深まる」と解説。飯髙・室谷もアカデミックな視点を持つことで、SNSマーケティングをより実践しやすくなると見解を述べました。
【前編】SNS活用の鍵は「クラスター」。消費者行動研究の専門家が語るSNSマーケティングの今後
後編では、SNSが消費行動にどのような影響を与え、その変化に対して企業が対応するべきことやマーケターとアカデミック領域との連携の必要性について語っていただきました。
オンライン消費が増えるほど、オフラインの価値は高まる
室谷:
SNSがどれだけ購買に影響するかを研究していく中で、消費者側の変化を受け、小売業界も変化しているのでしょうか?
鶴見:
正直、まだそれほど変化はしていないように感じます。本当はもっとSNSとリンクした売り場づくりをした方がいいと思うのですが、今は断絶してしまっている。
わかりやすい例を挙げると、「お店の写真を撮ってはいけない」というルールを敷いている店舗がほとんどですよね。競合に値付けや売り場を知られてしまうのを恐れているのかもしれません。ただ、今は売り場の情報を積極的に拡散していく方が良い影響を出せるはず。もちろん店舗によって状況は異なりますし、すべてが一気に変えられる訳ではないと思いますが、SNSを意識した戦略を取り入れる小売企業が増えるといいですね。
メーカーだと、SNS活用に積極的な企業が増えていますが、小売だとまだ保守的なところが多いように感じます。
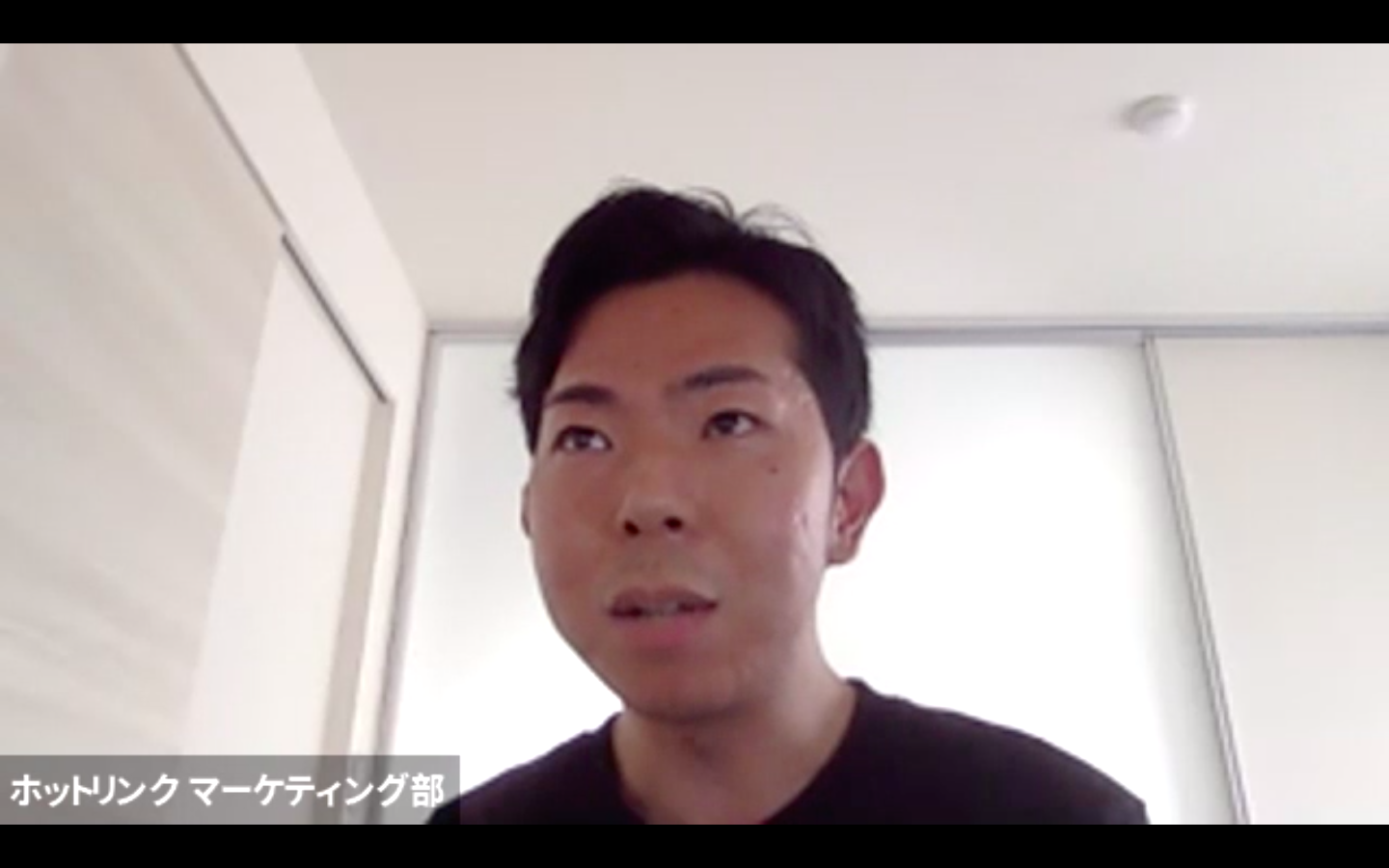
室谷:
メーカーだとD2Cに踏み込んで、ユーザーと直接つながるところも増えていますよね。
そういえば、僕自身もSNSと店頭の売り場を無意識に繋げて捉えているなと感じたタイミングがありました。朝コンビニへ行った時、ふとある商品が目に入ったんです。「これ、そういえばTwitterで話題になってたやつだな」と。「美味しそうだし買ってみよう」と思ってそのまま購入しました。
これって、SNSで先に接触していたからこそ起こった購買行動ですよね。このように、SNSは買う気持ちを自然に後押ししてくれるものだから、売り場としっかり連携していくべきだと感じています。
鶴見:
そうですね。あとは、オフラインでどのような価値を提供できるのか、明確に理解しなければいけないフェーズになっています。
今はコロナ渦の影響もあり、オンラインシフトが急速に進んでいますよね。だからこそ、オフラインでの価値がより高まってきている。
わざわざリスクを冒してまでオフラインの場に足を運ぶだけのメリットを消費者に感じてもらえるようにしなければいけないですね。
また、Zoomを使った接客や商談などのリアルとネットの重複領域も生まれています。今後はリアル・ネット・その重複領域という、3つの領域の価値を見極め、活用していけるかが企業に求められるでしょう。
先読み力を問われる現場のマーケターこそ論文を読むべき
鶴見:
私からも質問させてください。ノーマルからニューノーマルへ移行しつつある今、消費者や事業者はどのように変化しているのか、現場の方の肌感覚をお聞きしたいです。
飯髙:
消費者側のインターネット接触時間が増えた今、多くの事業側がデジタルシフトせざるを得ない状況になりましたよね。
先日当社で開催した「#NEWWORLD2020」というZoom上で実施したオンラインイベントでbaigieの枌谷さんがお話しされていたことが印象深かったです。中小企業から「Webサイトを構築したい」という問い合わせが今までにないレベルで増加しているらしいんです。その話を鑑みると、Webサイト制作をはじめDX関連事業はすごく伸びると思います。
参考:「リアルの強みをネットで体現する。コンテンツメーカーが今やろうとしていること #NEWWORLD2020 DAY3」ホットリンク
鶴見:
オフラインだけでなく、オンラインでの接点も必要だということに気づく企業が増えているわけですね。これからの時代、オフラインだけに軸足を置いた1本足打法ではかなり危うい。
室谷:
前提が全て変わってしまいましたよね。個人的には、このように状況が激変しても冷静に対処していくためには、アカデミックな領域の知識が不可欠だと思っています。
でも、論文を読んでいるマーケターはごくごく少数。論文で発表されている内容を現場に接続できれば、解決策を簡単に見出せるはずなんです。

鶴見:
まさしく今お話しされてることを、本学のビジネススクールである「横浜ビジネススクール」でやっています。
参考:横浜国立大学 国際社会科学府 経営学専攻 社会人専修コース(横浜ビジネススクール)
参加された方に感想を聞くと、室谷さんと同様「今まで悩んでいた課題の解決策が、驚くほどあっさり見つかった」といっていただけることが多くて。
私たちの研究内容をより多くのマーケターに届けなければいけないと感じています。
室谷:
そうなんですよね。今は学会やビジネススクールしかタッチポイントがないので、もっと気軽にアクセスできるようになればいいなと思います。
鶴見:
気軽にアクセスできないという問題に対して、私たち側から歩み寄るとしたらまず何をすればいいでしょうか?
室谷:
論文に触れている中で感じるのは、「専門用語や定義をもっとわかりやすく噛み砕いて説明してほしい」というところです。
論文は基本的に研究者向けに書かれるものなのでしょうがない部分はあると思うのですが、一般人でも読みやすい、柔らかいコンテンツに変換するようなものがあればいいなと。
飯髙:
言葉へのアクセスのしやすさは本当に重要だと思います。僕もよく論文を読みますが、正直結構な労力がかかっています。そこを、わかりやすいコンテンツに落とし込んで、メディアで流通させるなどするといいかもしれませんね。
鶴見:
そういえば以前、とあるメディアに寄稿したことがあって。私のかたい話を、ライターさんのアドバイスで分かりやすく書き直したのですが、そのおかげか記事はかなり読まれたんですよね。
参考:データが証明!SNSと売上はやはり連動していた ツイート数で売り上げは変化、ではツイート数を左右するのは?(1/5) | JBpress(Japan Business Press)
室谷:
噛み砕くだけでなく、具体的な解決策もセットで置いておくと読者にとって自分ごと化しやすいのかなと思います。アカデミックな知識をより流通させるためには、その2点が重要かなと思いますね。
マーケターを志望するなら、まずは自力で稼いでみること
鶴見:
もう一点、お聞きしたいことがあります。これから「SNSマーケターになりたい」と考えている人は、何から勉強すればいいのでしょうか?
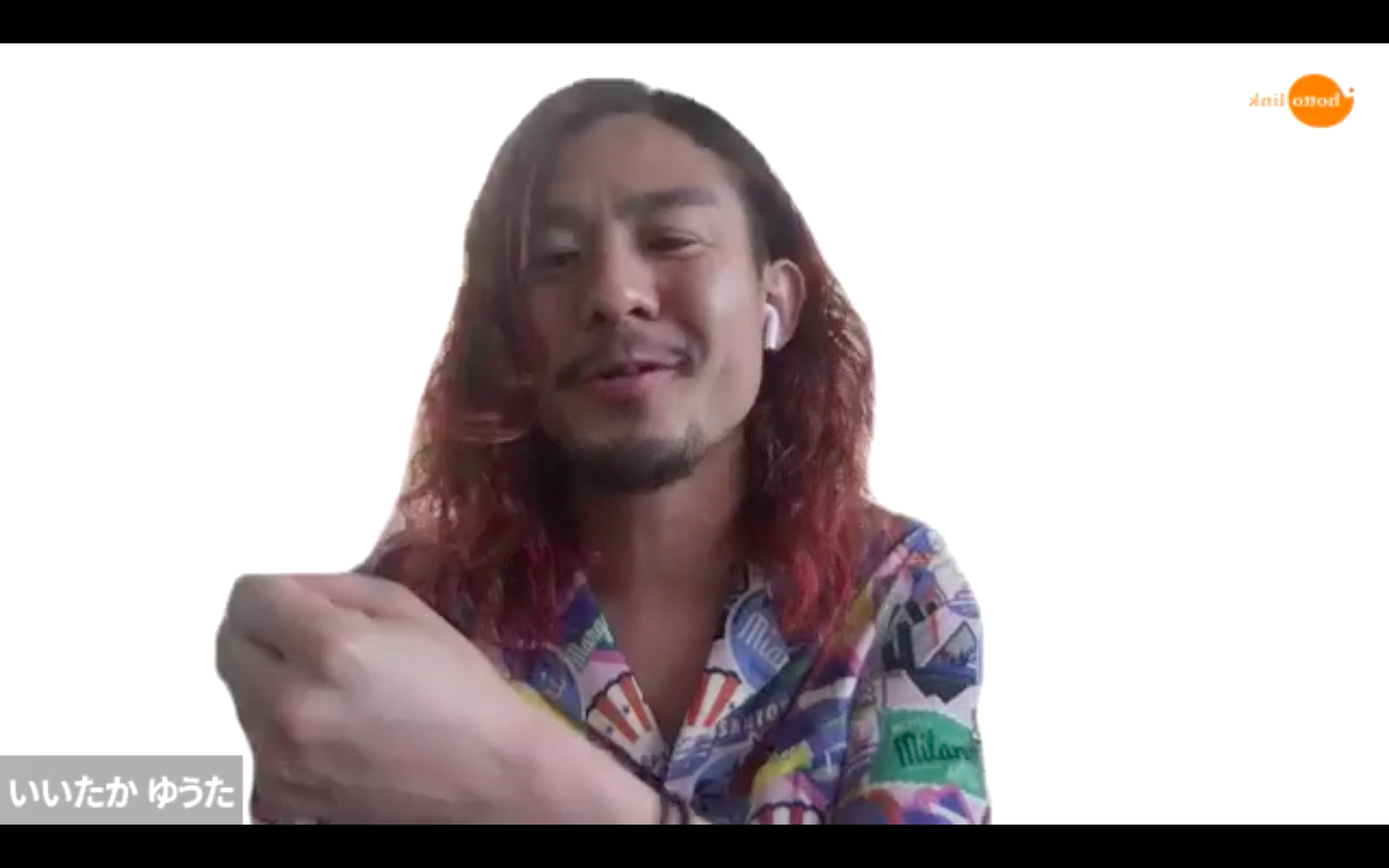
飯髙:
これはSNSに限らずなんですが、まずはWebサイトを立ち上げて、SEOやSNSで集客して、アフィリエイトプログラムに参加して報酬を獲得するなど、お金を稼ぐための一連の流れを経験してみることが一番大事だと思います。規模は小さくても、ビジネスの仕組みを体感できますからね。
後は自分でSNSアカウントを運用して、フォロワーがつく仕組みを理解することですね。
自分なりにデータを蓄積してそこから分析して改善する、その一連の流れを自然にできる人はSNSマーケターに向いていると思います。
僕たちはSNSマーケティング支援を行っていますが、SNSだけ理解していても部分最適な提案にしかならない。全体戦略を理解した上での提案でないと、お客様への価値提供はできないので、こうした経験は糧になるかと。
鶴見:
とても参考になります。私のゼミには毎年10人は入ってくるのですが、2グループに分けてTwitterアカウントを運用してもらい、エンゲージメントを競わせています。
これからはアカウント運用だけでなく、Webサイトを立ち上げてコンテンツ作成から売上まで一貫してやらせてみても良いかなと思いましたね。大学で実践的な内容を学べる環境を用意して、社会に出てすぐに活躍できるよう育成したいです。
「産学連携の機会はもっとあってしかるべき」
室谷:
さきほど、企業のマーケターとアカデミック領域との連携に関するお話をしました。今後の企業と大学側の産学連携に関して鶴見教授がどのようなご意見をお持ちか、最後にうかがいたいです。
鶴見:
企業のマーケターが抱えている問題と、我々のような研究者が持っているノウハウに橋がかかるような取り組みは、非常に有効なはずだと感じています。企業とアカデミック機関が繋がる機会はもっとあってしかるべきですし、今後増やしていく方がよいと思っています。
論文に感じるハードルのお話がありましたが、論文ってひとつのKWで検索しただけでも1万本ぐらい出てきてしまうんですね。どの論文が重要で、どの研究者の説が有効なのか、すぐにはわからないんです。私ですら、新しい分野にチャレンジするときはどの論文を読めばよいのかパッと見では不明なので、そういうときは研究者に聞きに行きます。
研究者の強みはある分野に長年携わっている点や、専門領域に関する情報の取捨選別ができる点です。なので、企業の方にはそういった専門家の強みにもっと頼っていただくとか、もしくはこちら側から企業に提供するという手段もアリだと思っています。
室谷:
僕自身、書籍や論文から解決策を得ることが多々あるので「もっと知の交流が促せるといいな」と感じています。
鶴見:
ホットリンクさんは、何か大学側と交流したり協働したりする機会はあるのですか?
室谷:
当社は産学連携は盛んですね。創業時からR&D部もありまして、自然言語処理やSNSデータの解析などデータサイエンスの領域で研究をしています。東京大学や筑波大学など、複数の大学と協働で研究事業を行ったり、定期的に学会で研究成果を発表したりもしています。
ちょうど今年、ソーシャルメディアマーケティング領域のアカデミック研究も始めようということで「ホットリンク総研」も立ち上げました。
※詳細はこちらから。
ホットリンク総研 | SNS時代の売れる話題づくりを科学する #ホットリンク
鶴見:
素晴らしい取り組みだと思います。
私も引き続き、マーケティングの現場とアカデミックな領域が融合するよう色々取り組んでいくので、双方で良いシナジーを生み出せるといいですね。
飯髙:
今後もし何かできることがあれば、ぜひ一緒に協働や連携などさせて頂けるとうれしいです。
――鶴見 裕之教授、本日はお忙しいところありがとうございました!
前編はこちらから。
【前編】SNS活用の鍵は「クラスター」。消費者行動研究の専門家が語るSNSマーケティングの今後
今回の「ザ・プロフェッショナル」もお楽しみいただけましたか? 本シリーズでは、今後も各業界で活躍するさまざまなプロフェッショナルをお招きして対談を行ないます。過去の記事はこちらからご覧ください。