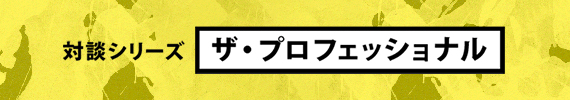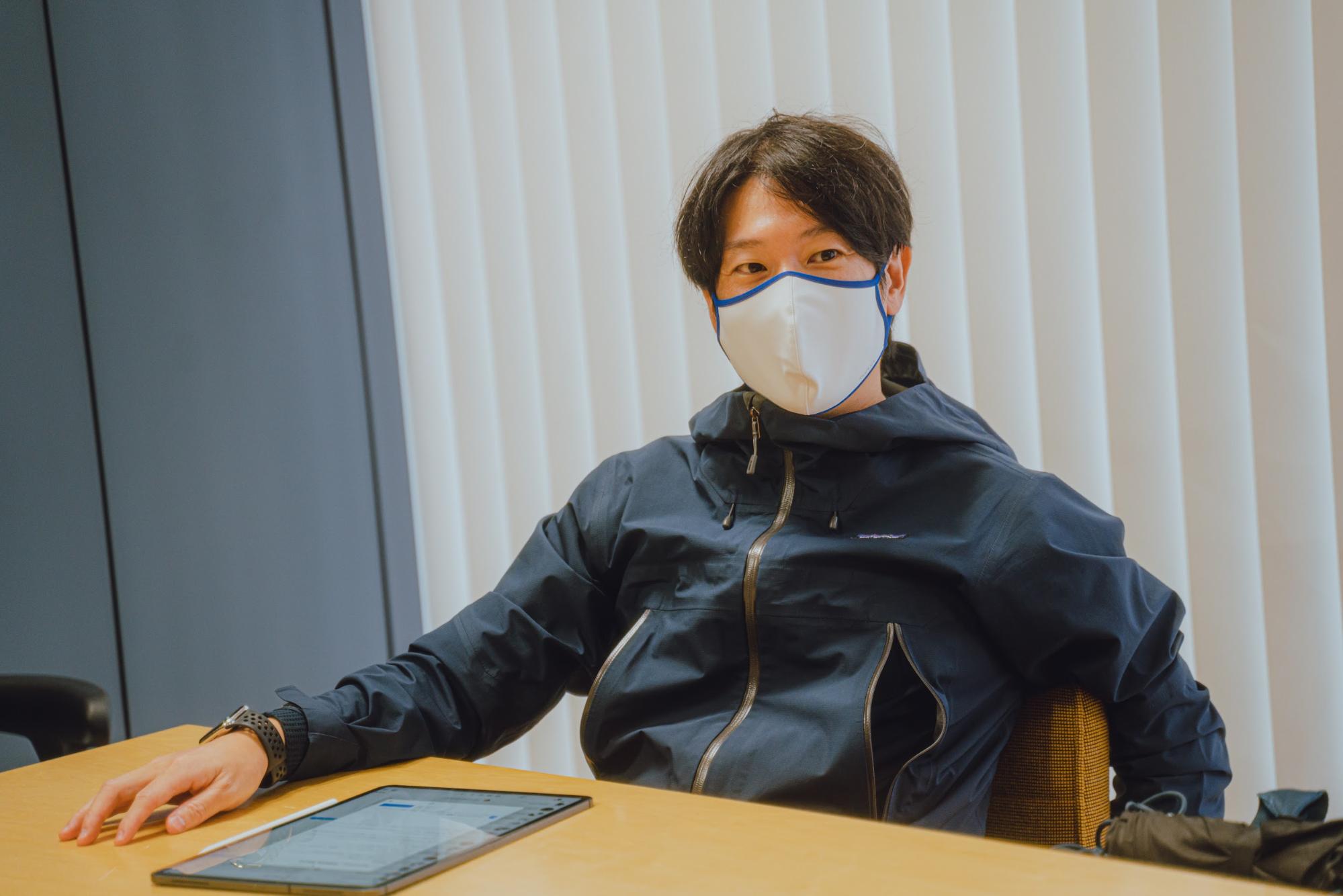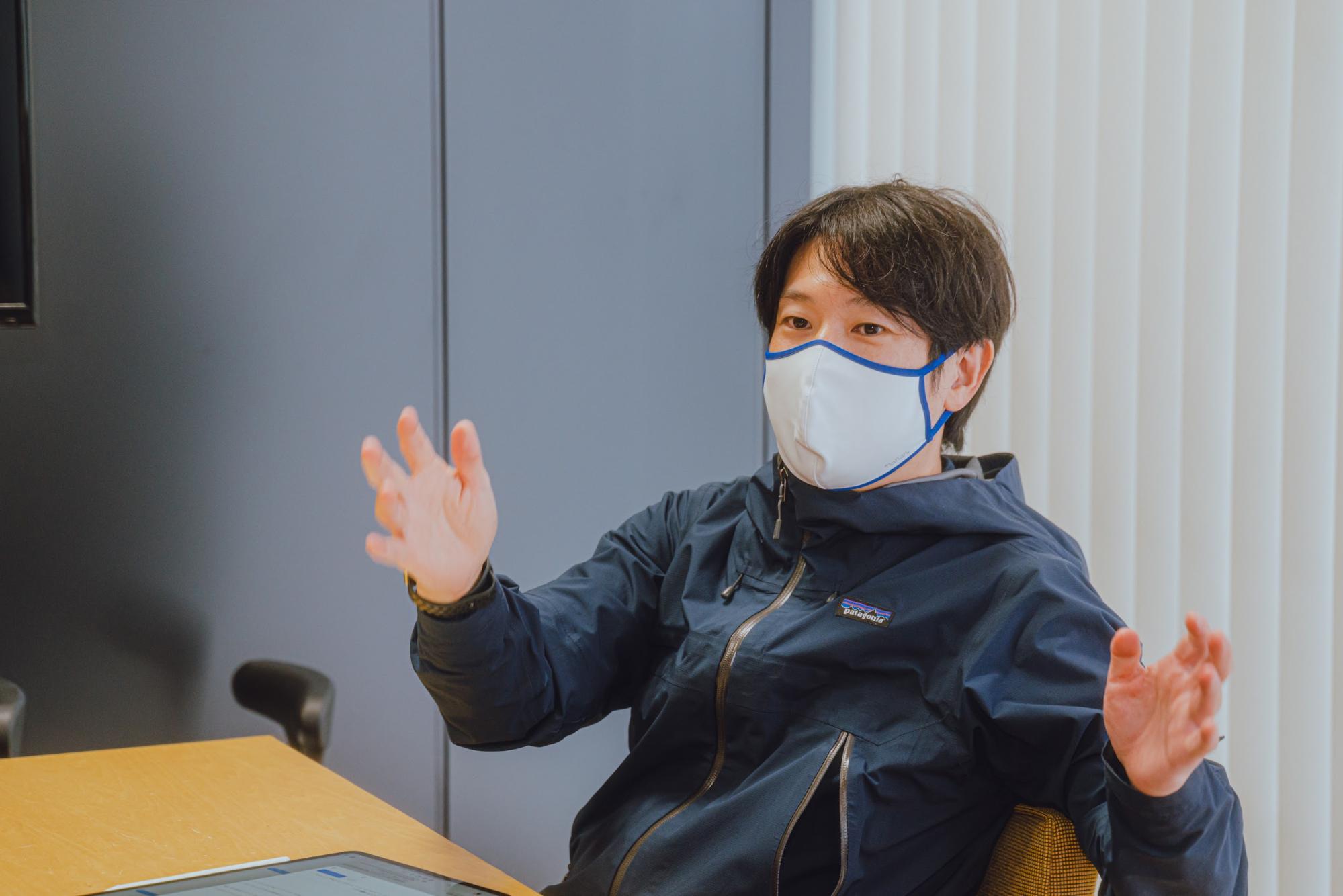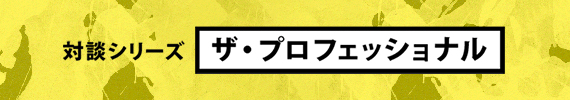各業界で活躍するさまざまなプロフェッショナルたちとホットリンクCMO・いいたかゆうたが、2020年以降のSNSマーケティングのあり方について考える対談シリーズ「ザ・プロフェッショナル」。
ゲストは、ティネクト株式会社の代表取締役の安達裕哉さんです。個人ブログとしてスタートした「Books&Apps」はSNSを中心に多くの人に読まれ、現在では企業のオウンドメディア支援を行っています。YoutubeやVoicy、noteなどといった多くのプラットフォームでコンテンツを配信している安達さんは、「コンテンツメーカー」として第一線を走っています。ちなみに安達さんといいたかは、「Books&Apps」立ち上げ以前から公私ともに交流のある間柄。
ホットリンクのライター/編集者「私がエレン」も参加しつつ、安達さんに「Books&Apps」の運営を通じて得たコンテンツ論、メディア論を聞きました。
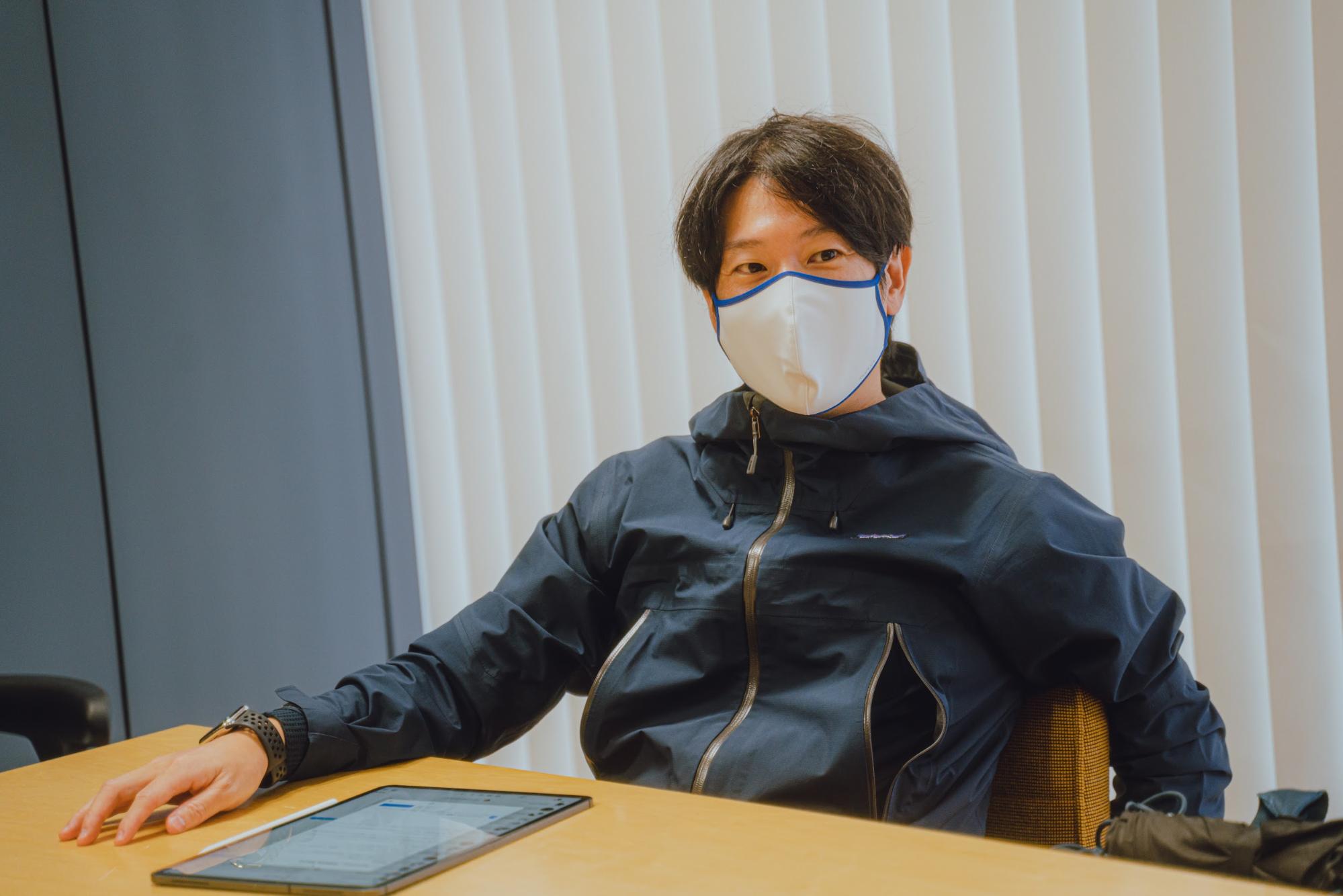
安達裕哉。Deloitteにて12年間、コンサルティング業務を経験。また個人ブログとして立ち上げたBooks&Appsは、月間約200万PVを誇るビジネスパーソン向けWebメディアとして成長する。2013年に、企業のオウンドメディア支援等を手がけるティネクト株式会社を創業
「Books&Apps」誕生秘話と、いいたかとの出会い
私がエレン:
安達さんといいたかは旧知の仲ですよね。安達さんはどんな経緯で、「Books&Apps」を始めたんですか?
安達:
「Books&Apps」は個人ブログとして、2013年2月から書き始めました。実は同じタイミングで、会社を退職して大学時代の友人とブログとは全く関係ない事業で会社を立ち上げました。
当時から有名だったコグレマサトさんというブロガーが、「ブログは毎日更新しろ」とおっしゃっていたんですね。やるからにはちゃんとやろうと思い、そこから真剣に毎日更新しました。
そこから1年半毎日更新していたんですけど、当時のPVは月間6,000〜8,000ほど。「頑張っているのにこんなもの?」と思いました(笑)。しかしある時を境に、突然サーバーが落ちるくらいバズるようになったんです。
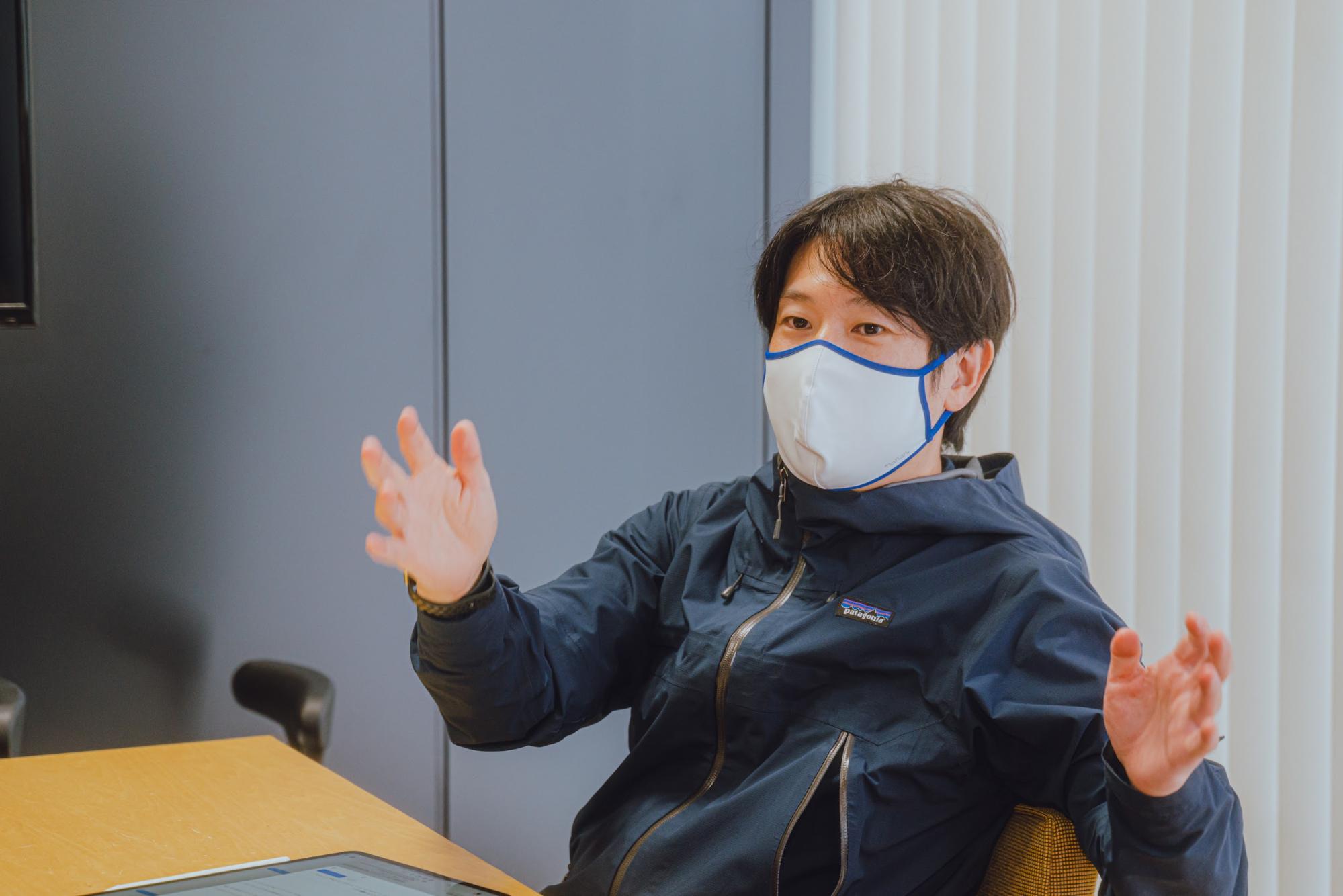
安達:
そして時を同じくして、本業が立ち行かなくなってしまいました。ブログがせっかく読まれているなら、会社運営の軸をこっちにピボットしよう、と。そこからメディア運営を事業の主軸にして、取材記事なども手がけるようになりましたね。
そうしたら、いいたかさんから「僕も取材して」って依頼があったんですよ。当時はまだいいたかさんを知らなかったので、「誰この人?」って驚きました(笑)。
いいたか:
僕も「Books&Apps」はよく知らなかったんだけど、真野さんの記事を読んで面白いなと思って。「この人に取材してほしいな」と思い、すぐに連絡しました。
安達:
最初の取材は、いいたかさんが「ferret」に関わっていた頃でした。僕たちはまだメディアを商用化するノウハウやデジタルマーケティングの概念がなかったので、教えてほしいという気持ちもあって取材したんですよね。
その頃から歯に衣着せぬ言い方で、面白い人だなと。この人に商用メディアとしての「Books&Apps」の立ち上げを手伝ってもらおうと思いました。
いいたか:
自宅も徒歩5分くらいの距離だったんで、すぐ「ご飯行きましょう」って誘いました(笑)。
安達:
メディアの稼ぎ方は、それほど多くありません。コンテンツそのもので稼ぐか、広告料で稼ぐかです。それで言うと、「Books&Apps」はSEOが強くありませんでした。流入もSEOは2割で、ほとんどがソーシャルやダイレクト流入です。そのためコンテンツを商売に転用できないな、と感じました。
広告でも月間PVが100万〜200万ほどでアフィリエイトに特化していないため、収益はあまり上がらない。それなら、メディア単体で収益を伸ばす道は捨てて、メディアに集まる人へ向けて商売をしよう。
そうやって選んだのが、第3の道であるオウンドメディア運営でした。記事数や注目を集めるニュースを扱ってPVを稼ぐという発想は捨てて、どんな人が集まるかを重視するようにしたんです。
ちなみに、当時いいたかさんに教えてもらった『デジタル・ジャーナリズムは稼げるか―メディアの未来戦略』という本は、僕がもっとも影響を受けた一冊です。
重要なのは「信用の積み重ね」 安達さんのSNSとの付き合い方
私がエレン:
さきほど少しお話が出ましたが、「Books&Apps」の流入のほとんどがSNSかダイレクトってすごいですね。
いいたか:
運営当初は安達さんのFacebookからの流入がすごく多かったんですが、Twitterでも多くの人が記事をシェアしていて。そこからのトラフィックが結構ありましたね。
だから、Twitterも公式アカウントを作ろうとアドバイスしたんですよね。
安達:
Twitterの流入が、Facebookの3倍くらいありますね。日中Twitterを開くと仕事が全然進まないから、全部予約投稿しています。しかも5ツイートつぶやくのに、2時間かかっちゃうんですよ。社内では「それはもはやTwitterじゃない」ってツッコまれるんですけどね(笑)。
Twitterはマイクロブログという側面もあるし、僕は「140文字=1記事」のブログと思ってつぶやいています。愚直にやると成果が増えるし、そう考えていたらうまくいくようになりました。
いいたか:
話は少し変わりますが、今って「マーケターならTwitterをやれ」っていう話題になりやすいじゃないですか。僕はこれ、ずっと本質的じゃないなと思っていて。
「2か月でフォロワー1万いきました!」とか言われても、そこに何の意味があるの? と考えちゃうんです。それよりも、与えられた業務をしっかりこなすほうが大事だよ、と。

安達:
なるほど、建設的ですね。
結局、Twitterにしたってひとつのコンテンツなんですよね。だからこそ愚直に、真面目にやった方が面白い。Twitterは愚直にやればやるほど、成果が増えると思ってます。努力した分だけ報われるのがSNSですよね(笑)。僕の場合は力を抜いた発信が苦手なので、今のやり方で投稿を始めてからの方が上手くいくようになりました。
あと、コンテンツ発信って花火のように刹那的なものではなくて、ストックし続けるものだと思うんです。このストックは、ユーザーからの信用とも言い換えられます。「このアカウントに行けば、そこそこ面白いものがある」という信用が、商売を支えてくれる。良い発信をしていないと、見る人にはわかっちゃうんですよね。
コンテンツメーカーが持つべきエンタメ思考
私がエレン:
ベイジの枌谷さんの取材記事でいいたかが言っていたんですが、安達さんはある時期から、ライターさんに自由に記事を書かせる方針に切り替えたそうですね。その方針転換が現在の「Books&Apps」に繋がっていると。
安達:
テーマを指定してライターさんに執筆を依頼すると、自分のなかの経験などが元にない、ありものの情報をかき集めたツギハギの記事が出来上がっちゃうんです。
調べ物が有益になるときは、自分の中になにかしら、経験や知識があるからじゃないですか。実際にやった、体験したところから書いてみる。これがないと記事は面白くなりません。それなら、ライターさんに自由に書いてもらうほうがいいなと。
10月6日に掲載した「老朽化していく築十数年のマンションというのは、まさに「日本」そのものだなと思った話。」という記事も、僕が管理組合に入ってひどい会議を経験したのをきっかけに書きました(笑)。
ある体験をして「これおかしくないか?」と考えて、そこに文章力が加わる。そうやって面白い記事が生まれると思うんですよね。僕は文章に関しては、自分の感覚を信じています。そのせいであまり再現性がないんですけどね(笑)。
いいたか:
「問題を指摘するだけで改善案を出せない専門家、『重箱の隅おじさん』の話」って記事も、僕が飲み屋で話したことを安達さんが「それ面白いですね」となって、翌週記事になったんですよね(笑)。

いいたか:
「Books&Apps」を手伝い始めたときは、なぜこんなに訪問ユーザーが増えるんだろう? って疑問だったんですよ。SNSとダイレクトからの流入が多いということは、やっぱりユーザーの記憶に残る面白いメディアということじゃないですか。
私がエレン:
今お話してくださったような、ライターさんに執筆を依頼するときの方針などの話を聞くとコンテンツの面白さを維持する秘訣が表れているような気がします。
安達:
ただひとつ、「Books&Apps」で書いてくれるライターさんを選ぶ基準で重視しているものがあります。ライターさんがどれくらいの期間、ブログを書いてきたかです。1年とか短い期間じゃダメ。現在執筆しているライターさんは、10年間くらいブログを書いている人ばかり在籍しています。
書いている期間が長いライターさんほど、ユーザーに何がウケるのかを見抜く感覚が研ぎ澄まされていきます。だから僕は、ライターさんの経験則を重要視しているんです。
この「面白い」という軸は、「役に立つ」とは別の軸になると思います。SEOでは役に立つ情報が重要だし、Googleもそうしたコンテンツを評価します。しかし有用性だけに特化しても、ほかのプラットフォームではまったく評価されません。
 安達:
安達:
有用性に特化しただけのコンテンツは、Googleのアルゴリズムの変更次第で、すぐに崩壊してしまうでしょう。しかしエンターテインメント要素があれば、普遍的にどのプラットフォームでも楽しめるコンテンツになります。
例えばジブリ作品って、映画館であれYouTubeであれブログであれ、どのメディアで観ても面白いじゃないですか。コンテンツメーカーは誰もが、このエンタメ思考を持つべきと思います。
いいたか:
Google検索は能動的かつ緊急性の高い行動で、知りたいことを調べるだけだから、訪問したメディアが記憶に残らないんですよね。SNSやYouTubeはスキマ時間の出会いで、面白ければ必ず記憶に残る。
面白いコンテンツを作ったものが覇者となる時代
安達:
今、多くの人々の思い描くメディアのイメージが、オウンドメディアになった気がします。実際にGoogleとFacebook以外はほぼすべてオウンドディアと呼べるんじゃないでしょうか。TwitterやYoutubeはもちろんですが、最近ではここにオンラインゲームも含まれるようになっている気がします。
特に僕が注目しているのが「フォートナイト」というゲームです。
いいたか:
やったことないです。
安達:
フォートナイトはEpic Gamesが提供するオンラインゲームです。100名のプレイヤーがひとつのエリアに集結して、最後のひとりになるまで戦うというサバイバルゲームで。他の類似するゲームと違い、素材を集めて建物やバリケードを建設することもできます。
完全に対人ゲームで、課金してもコスチューム等が手に入るだけなので、強くなるにはめちゃくちゃ練習が必要です。
最近ではYouTubeチャンネルもたくさんあるし、ライブ配信をするユーザーも増えています。YouTubeのメンバーシップ制度を活用するユーザーもいて、これは新たなメディアだと思い、僕も研究しています。
いいたか:
めちゃくちゃ面白そうですね。僕も今日からフォートナイトをやろう(笑)。
安達:
ほかにも、「吉田製作所」というYouTubeチャンネルをよく観ています。投稿者の方がぶつくさ言いながら、自作PCを組み立てたりゲーム機を組み立てている動画なんですが、チャンネル登録者数に対して再生数がすごく多いんですよ。
決して投稿者にスター性があるわけじゃないですが、撮影機材や企画にはかなりこだわっている。動画中のナレーションも、全て原稿を書いて読み上げているんです。その努力は尊敬します。
いいたか:
少し動画を観ましたが、たしかにクオリティ高いですね。
安達:
このチャンネルには、YouTubeならではの面白さが詰まっていると思います。お金をかけなくても、純粋にコンテンツで勝負できるんです。
いいたかさんに言われたことで、よく覚えているものがあります。コンテンツとメディア、プラットフォームの3つがあるうち、もっとも寿命が長いのがコンテンツで、次がメディア。そして最後にプラットフォームが続くと。
これはそのとおりだと思います。実際僕も、「フォートナイト」が出てからFacebookをほとんど見なくなってしまいました。一方で、僕はAmazonのスマートスピーカーで音楽をかけるのが好きなんですけど、新曲だけでなく古い曲もすごくいい。それこそ、数百年前に生まれたクラシックが今も現役で愛されています。こうした経験を通じて、コンテンツこそが本質だと確信しました。
加えて今は、あらゆるメディアに勝手にコンテンツに乗せていい時代です。「Books&Apps」のコンテンツをYouTubeでアニメ化していいし、過去記事をピックアップしてTwitterで流すと、普通にバズる可能性だってある。
いいたか:
同感です。最後にコンテンツやメディアの領域に関して、マーケターや企業が今後注目しておくべきポイントを教えてください。
安達:
いまだにプラットフォームがどうといった話をしているなら、今すぐやめた方がいい。それよりも「使えるものはすべて使う」という思考に切りかえて、あらゆる企業がコンテンツ作成力を鍛えるべきです。
デジタル周りで、今までとは異なる常識が生まれています。しかもそれが、あらゆる領域に無限に広がり続けています。個人に遅れを取っていますが、本来はそのすべてを企業も活用できるんです。質の高いコンテンツを配信できた企業が、覇権を握ります。個人的に、これはいい時代が来たなと思いますね。

――安達裕哉さん、本日はお忙しいところありがとうございました。
今回の「ザ・プロフェッショナル」もお楽しみいただけましたか? 本シリーズでは、今後も各業界で活躍するさまざまなプロフェッショナルをお招きして対談を行ないます。過去の記事はこちらからご覧ください。