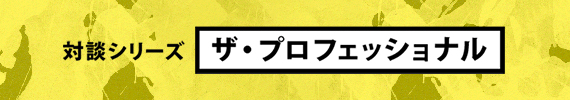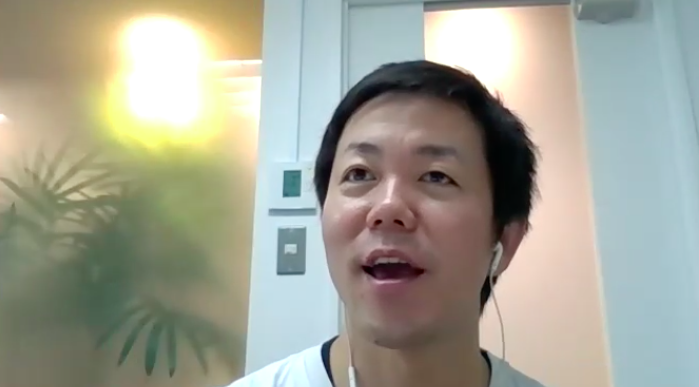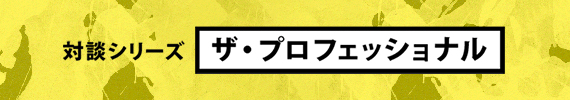前編では、マンガと商材の相性やマーケティングにおけるマンガの強みや活かし方に関する話がメインとなりました。
「良さが伝わりにくい無形商材にマンガプロモーションは活きる」フーモア芝辻さんが語るマンガとSNSマーケティングの相性
後編では、社会情勢の影響もあって大きく変化していく時代においてどのようなマーケティングが重視されてくるのか。芝辻さんはマンガ活用、飯髙はSNSと、それぞれの専門領域の観点から語ってもらいました。
マンガプロモーション×「ダークソーシャル」の新たな可能性
飯髙:
ホットリンクとマンガプロモーションとの関連でいえば、先日フーモアさんにUGCを解説する漫画を作っていただきました。
テキストだけではなかなか表現するのが難しかった「感情」が盛り込まれて、とても記憶に残りやすいコンテンツになったと思います。
芝辻:
ありがとうございます。
飯髙:
フーモアさんは、企業からどのような依頼や相談を受けることが多いんでしょうか。
芝辻:
「それほど予算を割けないけど、なんとか効果を高めたい」というご相談など多いですね。数百万円しか予算がない場合、大々的なプロモーションは打てない。そこで、「興味関心を引きやすい漫画を活用したい」と。
代理店さん経由のご依頼もあります。その場合は、トータルプロモーションの中のひとつの施策としてご相談いただく場合が多いですね。
飯髙:
デジタルシフトが推進され、時代が大きく変化している中で、企業のマンガ活用も変わっていくのでしょうか。
芝辻:
もちろん変わっていくはずです。今後くるかなと思うのは「ダークソーシャルの手前での認知獲得」です。
※ダークソーシャルとは……
「オープンではないソーシャル」のこと。FacebookやTwitterのタイムラインなど誰でもアクセスできるのがオープンソーシャル、DMやLINEなど当事者でのみやりとりされるのがダークソーシャル。
展示会やセミナーなど見込み客と直接コミュニケーションできる機会が減少した今、知り合いを辿って見込み客にアプローチする機会が増えていくと思います。
知り合いから見込み客へ自社を紹介してもらう際、事前に認知を獲得できていれば、商談を進めやすくなるでしょう。
自社の見込み客を明確にターゲティングし、マンガの視認性の良さやわかりやすさを活かしたプロモーションを実施し、認知を獲得していくという施策はアリなんじゃないかと思います。
飯髙:
素晴らしいですね。マンガは認知だけでなく、記憶に残りやすい点が魅力だと思うので、ダークソーシャルでも活きてくると思います。
芝辻:
あとは、海外の動きを見ていると画像検索も普及していくのではないかなと思います。
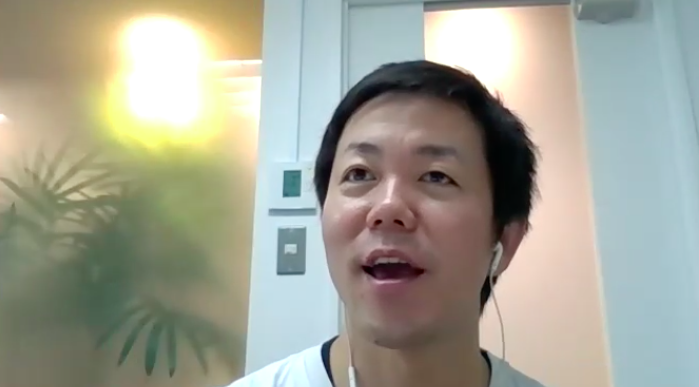
芝辻:
海外ではPinterest(ピンタレスト)が伸びていて、ユーザーは画像検索して気に入ったコンテンツをブックマークしてストックしています。料理やクラフト関連のコンテンツが人気みたいですね。
日本ではInstagramの画像検索がさかんに使われていますが、ほかのSNSでも広がっていくと思います。そうすると、マンガやイラストなど、絵を使ったマーケティングの幅が広がっていくのではないかなと。
ユーザーに価値提供できる「本質的な企業」のみが生き残る時代に
芝辻:
僕からも質問していいでしょうか。
今、オフラインのプロモーションが全体的に厳しくなっているなか、ホットリンクさんはどのようなマーケティング施策を実施しているんですか?
飯髙:
セミナーからウェビナーへ、対面営業からオンライン営業へとシフトはしていますが、基本的な戦略は変わりません。対面できない点をどう克服するかだけだと思います。
コロナ禍の影響もあってオンラインに移行して以降、リード獲得数は激増しました。オフライン時代の6倍は超えていますね。以前は週に1回やってたセミナーがウェビナーに切り替わった途端、毎日できるようになったので。
 ホットリンクで毎日開催中のウェビナーのひとつ。「UGCを生み出すSNSマンガ活用マーケティング講座」
ホットリンクで毎日開催中のウェビナーのひとつ。「UGCを生み出すSNSマンガ活用マーケティング講座」
ホットリンクのセミナー・イベント情報はこちらから
芝辻:
ホットリンクさんのクライアントとなるような企業って、コロナ禍の影響もあって、今後どのようにマーケティングを展開していけばいいのか、課題を感じているところもあると思います。
たとえば、屋外広告への出稿もかなり少なくなっていますよね。僕のオフィスの近くにコカ・コーラの屋外看板が出ていたんですが、いつのまにか無くなっていました。
飯髙:
コカ・コーラは切り替えが早かったですね。
屋外広告を辞めた代わりに、コカ・コーラは公式スマートフォンアプリ「Coke ON」から家でできるエクササイズのレッスン動画を配信しています。エクササイズで1,000歩達成したユーザーのなかから抽選で無料ドリンクチケットなどを提供する「おうちでリフレッシュ」プログラムも始めてますね。
参考:「#おうちでリフレッシュ」コカ・コーラ
もともと「Coke ON」は自販機でのドリンク購入を想定した設計で、いわば屋外向けのアプリだったんですが、Stay Homeの流れを受けてうまく屋内向けに転用した事例ですね。

飯髙:
昨今の社会情勢の影響で既存の広告手法がなかなか通用しにくくなっている今、こういうキャンペーンも有効です。
ただ、コロナの影響アリナシではなく、そもそもの普遍的なマーケティングの考え方として「時流に沿ったマーケティング」を行うことは引き続き大切です。その文脈からいうと、オーガニック投稿の重要性も高まってきていると思います。
具体的には、どのようなコンテンツを、どのように流通させるかが大事になってきます。
とくにSNSだと、これまでは一過性のバズを目的とした施策が主流でしたが、これからは、UGCをどれだけ生み出せるかがカギとなるはずです。
むしろ、SNSマーケティングの本質はそこにある。ユーザーが自社の商品について自ら発信したくなるようコミュニケーションを取ることが、本来SNSで行うべき施策ではないかなと。
もちろん、大前提としてユーザーに喜んでもらえる商品を提供している必要はあります。そこから正しいターゲット層に、正しいチャネルでリーチしていくべきだと思いますね。
芝辻:
ユーザーにしっかり価値を提供できる、本質的な企業が生き残り、それ以外は淘汰される流れがより加速していくと。
飯髙:
そうだと思います。この流れの中では、先ほど芝辻さんがお話ししていたダークソーシャルも重要なチャネルになりますね。
たとえば、僕がマンガ制作をどこかの会社にお願いしたいとなった場合、Webで調べる前に、友達に聞くんですよ。そこで友達が「フーモアさんがよかったよ」と言ったら、もうそのままフーモアさんにお願いしようとなるわけです。
人が何かを選ぶとき、身近な人間からのレコメンドが強く影響します。SNSでの投稿や、普段の何気ない会話で聞くオススメ情報が、購買行動を後押しする。だからこそUGCも、ダークソーシャルでの言及も重要なんですよね。
ただ、僕らも今の時流に対して、完璧な正解がわかっているわけではありません。基本的な思想は変えずに、さまざまな手段を試して試行錯誤しています。
芝辻:
それでいうと、漫画もひとつの手段なんですよね。
大事なのは何を成し遂げたいか。漫画はできることが幅広いですが、すべての課題を解決できるわけではない。お客さまと一緒に、「誰の何をどのように解決するべき」なのか、最適解を探っていかなければいけないと思います。

――芝辻幹也さん、本日はお忙しいところありがとうございました。
前編はこちらから。
「良さが伝わりにくい無形商材にマンガプロモーションは活きる」フーモア芝辻さんが語るマンガとSNSマーケティングの相性
今回の「ザ・プロフェッショナル」もお楽しみいただけましたか? 本シリーズでは、今後も各業界で活躍するさまざまなプロフェッショナルをお招きして対談を行ないます。過去の記事はこちらからご覧ください。