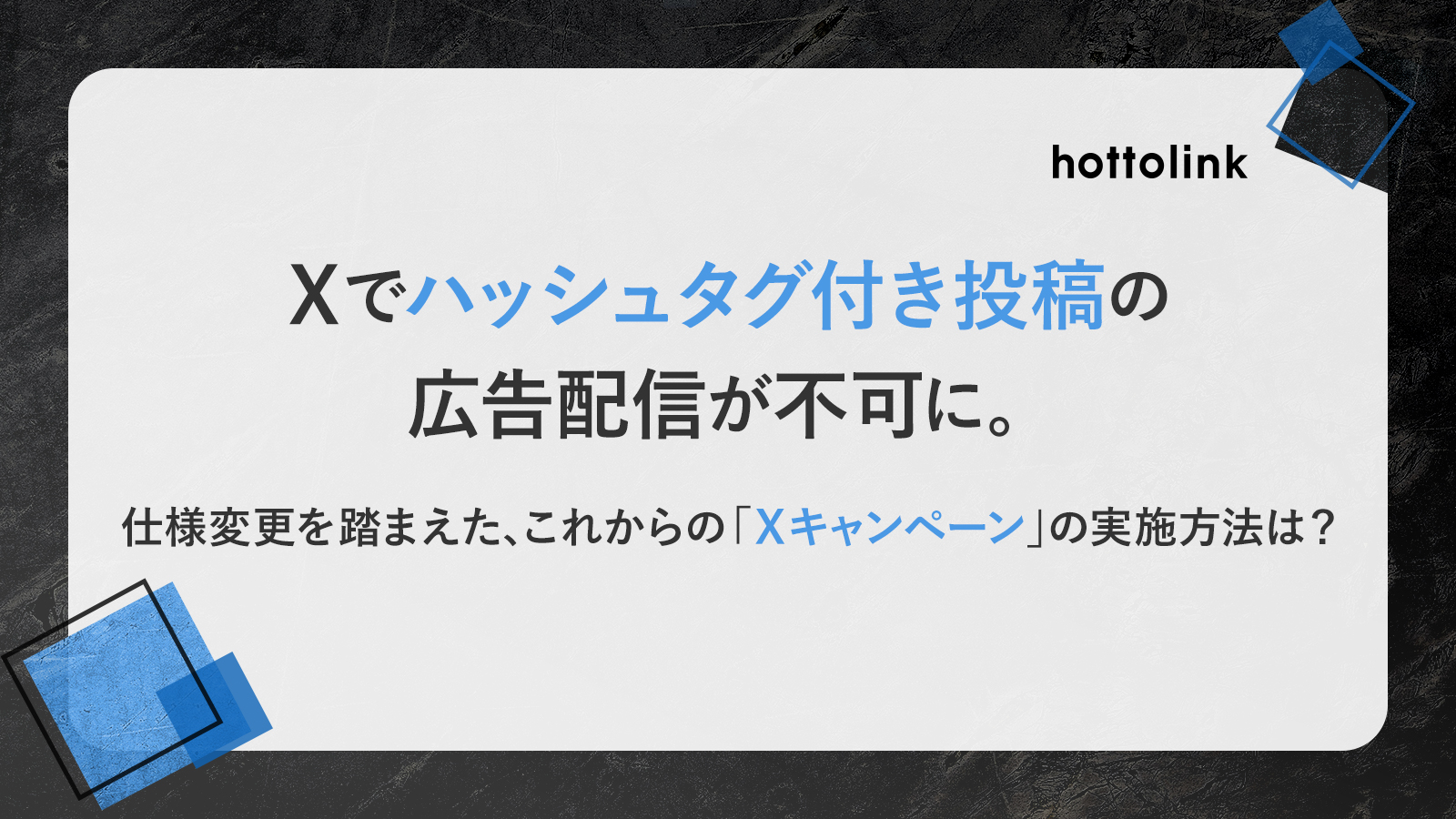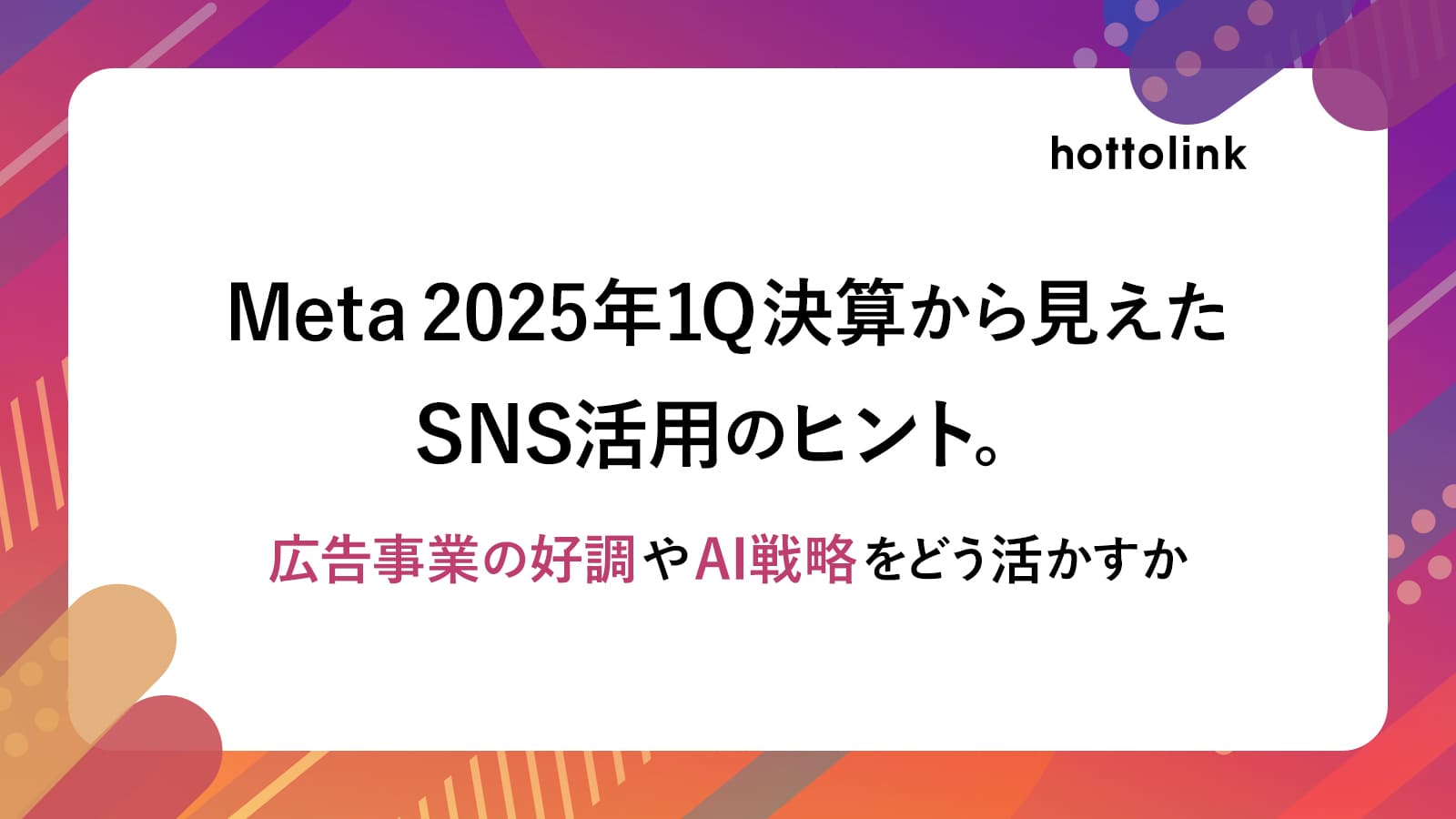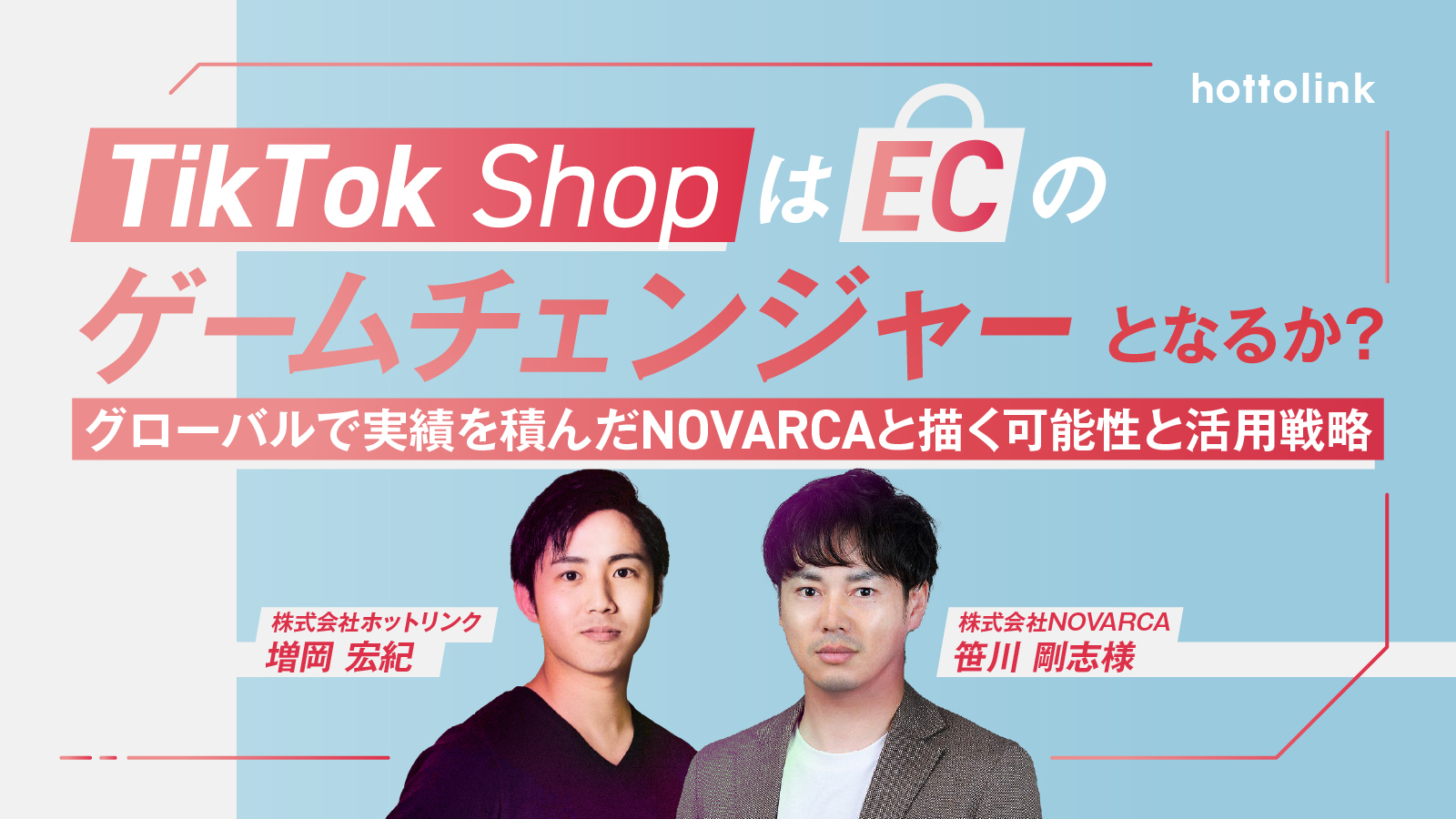新型コロナウイルスの影響は、人々の生活を一変する事態に発展しています。政府による緊急事態宣言発令と、各自治体からの外出自粛要請。激動のさなかにある今、私たちにできることはないだろうか。
そんな思いから、ホットリンクは各界のリーダーをゲストに招き、時代の変化に対応するヒントを探るカンファレンス「#NEWWORLD2020」を開催することとなりました。
#NEWWORLD2020 - 各業界をリードする15名をゲストに激動の時代のマーケティングを語る|イベント・セミナー|ホットリンク
2020年4月22日〜5月1日の平日の7日間にかけ、毎回異なるゲストを招いて行う当カンファレンスでは、オンライン会議ツールZoomを使用。リリースからわずか3日という期間にもかかわらず、現在では4,000名を超えるイベントとなりました。
DAY4のゲストは、ニューバランスジャパン マーケティング部 ディレクターの鈴木健さんと、inquire Inc CEOのモリジュンヤさんの2人です。
当社CMOの飯髙とともに、私たちが今できること、この時代をポジティブにとらえるための考え方を語っていただきました。
※DAY5は二部構成形式
DAY4の記事はこちらから。
リアルの強みをネットで体現する。コンテンツメーカーが今やろうとしていること#NEWWORLD2020 DAY3
社会、社員、そして顧客。マーケターが向き合うべきニューノーマルの変化
〜第一部 ニューバランスジャパン マーケティング部 ディレクター 鈴木健〜
飯髙悠太(以下、飯髙):
ニューバランスは海外にも展開していますが、新型コロナウイルスの会社への影響はどうですか?
鈴木健(以下、鈴木):
グローバルで見ると、感染拡大したアメリカ本社が先にアクションを起こし、日本は危機感が増してくるにつれ、素早くリモートワークに対応していった流れです。欧米では医療従事者を助けよう、称賛しようというアクションが起きたじゃないですか。ニューバランスもアメリカに自社工場を持っているんですが、かなり早いタイミングで医療従事者向けにマスクをつくり始めました。
参考:「ニューバランスがマスク生産開始 靴づくり応用、1週間でライン転換」|Forbes JAPAN
僕自身はこのアクションに直接関わっていませんが、マスク供給は対外的というよりも、社員からポジティブな反応があったと耳にしています。多くの人が困っている状況にあり、企業はなんのために存在するのか、自問自答する人もいたと思います。
そのなかで、自分たちの企業がアクションを起こしたことは誇りに思えたし、勇気もわいた。僕たちのブランドは社会のために存在しているんだって、自信にもなった気がします。

「ニューノーマル」が生む、新たな可能性と責任
飯髙:
鈴木さんはwithコロナ、afterコロナをどう考えていますか?
鈴木:
社内でキーワードになっているのは、「ニューノーマル」という言葉です。元に戻らない前提で、変化によって起こる新しい規範を考えています。
たとえばプロスポーツは、世界的に厳しい状況にあります。だからこそリアルで試合を観戦したくなるような情報コンテンツが、オンライン上で強化されるでしょう。試合以外で選手とファンがつながるみたいな。こうした活動は、今までおまけ程度の扱いでした。しかしこれからは、積極的に行うほど試合を観戦してくれる人は増えるはずです。
リアルというパワフルな部分はなくならず、その価値は上がっていくでしょう。そこに結びつける手間の手段として、オンラインを活用した取り組みはwithコロナで必ず増えるだろうとは思います。
飯髙:
確かに今、オンラインでスポーツを盛り上げようとしている選手が圧倒的に増えていますよね。
鈴木:
あと中国の事例で面白いと思ったのは、徐々に回復基調で本屋の売上が伸びているなか、ライブ読書をやっているらしいんです。これまで本は情報商材で、先出ししたら売れないと思われていた。ですが作者本人や本屋のスタッフが、ライブ読書でものの価値を伝えることで、「私も読んでみよう」となるわけです。
飯髙:
それ、日本でもできますね。書籍の販売方法が大きく変わるかもしれません。鈴木さんはコロナの影響で、働き方や生き方がどう変わると思いますか?

鈴木:
たとえば日本で進んでいるリモートワークは、自分の自由な時間が増えることでもあると思います。生活の自由度が上がれば、マルチタスクが社会に活かせる機会が増えます。
一方で、単に好き勝手できるわけじゃなく、責任も生まれますよね。いわば、スキルの自主管理が必要になるわけです。「この時間を自由に過ごすなら、ほかの時間で何をアウトプットするか?」決めないといけません。責任をもって管理ができないと、自由とのバランスが保てなくなります。
飯髙:
働き方の変化によって、仕事のパフォーマンスが可視化される可能性は充分ありますね。「今までは会社からの指示に従えばよかったのに、タスクがなくなってどうしよう」みたいなことも起こりそうです。
鈴木:
逆に言えば、それぞれがセルフコントロールをして働くことができれば、個性や自分のできることで、最大限企業や社会に貢献できる世界になると思います。
ブランドたちの「軸」を守り、新しいビジョンを生み出す
飯髙:
コロナの影響を受けた企業のマーケティングやプロモーション展開で、よかったと思う事例はありますか?
鈴木:
明日(4月30日)登壇予定のオールユアーズの木村さんはいいですよね。オールユアーズは店舗で採寸して試着体験できるのが売りだけど、自宅でも同じ体験をしてもらおうと、オンラインの施策にも力を入れている。オンライン化は大切ですが、ビジネスの本質がぶれないことの方が、DtoCでは重要だと思います。

参考:「インターネット上のオールユアーズ」|note
飯髙:
企業のマーケティング活動は、今後どう変わると思いますか?
鈴木:
マスクで痛感しましたが、ブランドの考えを伝えることは、社員の安心にもつながるし、結果的にロイヤルカスタマーにも響きます。1番のオーディエンスは、社員であることを自覚すべきです。その点を踏まえて、社内に広がるつぶやきを集めて、クリエイティブとして表現する。これがまず、マーケターがやるべきことだと思います。
その次にやるべきは自分たちの提供する価値を見直して、ビジネスを考え、継続させることです。
あるレストランが、お店を閉めて別のビジネスを展開するとします。それは食材を売ることだったり、レシピを売ることだったりするでしょう。これってリソースは変えずに、手段を変えただけです。元の価値を分解して、バラバラにしたりつなぎ合わせたりして売る。それをポジティブに考え、実践していく必要があります。
この2つの手法は、ある意味「生き残る」ためのもの。第3段階としてやるべきは、世界に新しいビジョンを出すことです。僕も今、これに取り組んでいます。
飯髙:
今後、いい事例が生まれるのを楽しみにしたいと思います。最後に視聴者の皆さまへ、メッセージをお願いできますか。
鈴木:
昨日、若い子とzoom飲み会をやったんですが、彼らはオンラインの新しい楽しみ方を、どんどん発見していました。ある日彼らは「遊園地に行きたいね」と話していました。すると、YouTubeでジェットコースターに乗った映像を見つけ、みんなで被りものを着けてそれを観ながら楽しんだそうです。
こういう状況だからこそ、普段やらないことをやる。その発想は若い世代の方が、圧倒的にフレキシブルだと感じました。ぜひ何か探して見つけたら、僕に教えてください。一緒に乗っかりたいと思います(笑)。
ひとりひとりの小さな力の総和が、世界を変えるチャンスを作る
〜第二部 inquire Inc CEO モリジュンヤ〜
飯髙:
ジュンヤと知り合ったのはもう10年前で、プライベートでも仲がいいんです。今回のカンファレンスでは唯一の同い年ということで、僕もちょっとリラックスした感じで話せそうです。早速ですが、新型コロナウイルスで会社はどういう状況になっていますか?
モリジュンヤ(以下、モリ):
働き方の変化は少ないですね。僕はもともとリモートワークで、ミーティングの時だけオフィスに集まっていました。今ではミーティングも、オンラインで対応しています。取材に関しては、現状対面でのインタビューができないのでオンラインで調整しているところです。
飯髙:
視聴者さまにはライターや編集職の人も多いですが、オンライン取材で気をつけている点はありますか?

モリ:
一番大事なのは、取材への入り方ですね。生活空間から取材に切り替えるまでのアイスブレイクが、対面より難しいです。あと、オンライン取材って対面よりも話し続けることに体力を使うんですよね。話をまとめたり休憩時間作ったり、色々と試しています。
たとえばアイスブレイクの時はお互いに顔を写すけど、その後はドキュメントを共有して話すとか。ずっと顔を合わせるよりリラックスできるし、取材内容のログを一緒に見て確認できます。それ以外にも、オンラインでは通信環境のエラーも起きやすいので、音声が切れたら補助チャットを使うなど、メンバーで対応策を考えています。
飯髙:
リアルで会う取材より、オンラインのほうがコンテンツの深みが出そうですね。
モリ:
確かに、ビジネス的にロジックを深める取材は、テキストとの親和性が高いかもしれないです。ただし相手の心情に寄り添うような、エモーショナルな部分をどう掴むかは、まだまだ試行錯誤が必要ですね。
アイデンティティを見つめ直し、常識を再構築する
飯髙:
ジュンヤはwithコロナ、afterコロナをどうとらえてますか?
モリ:
常識の再構築が起きていると思います。今まで「こうしなきゃいけない」という前提があったけれど、不可能になって別の方法に代替したら「意外となんとかなった」みたいな。
医療従事者など、大変な状況にある人もいるけれど、どうすれば幸福度が上がるのか、理想の生き方・働き方に近づけるのかを考えるいい機会だと思います。
PCの父と呼ばれるアラン・ケイの言葉に、「未来を予測する最善の方法は、それを発明することだ」というのがあります。今できる新しい行動を積み重ねて、習慣化していければいいですよね。
飯髙:
新しい習慣をつくることは、今だからこそできることかもしれませんね。
モリ:
週末に『エフォートレスな行動で、能力を最大化する 「無為」の技法 Not Doing』っていう新刊を読みまして。本書には「しないことを考える大切さ」が語られているですが、この考え方は今後加速していく気がします。
素早く行動することが大事な局面でもあるけれど、今立ち止まって考えることは、中長期で価値があると思います。
大切なのは、なりたい自分や目指すアイデンティティはなにか。それが体現できている自分は、これを習慣にしているはずだ。そういう観点で日々の行動を変えていくべきだと思います。
企業も同じです。「自分たちはなんのために存在するのか?」を問いかけて、withコロナに新しい習慣を作れたらと思います。
飯髙:
これからの生き方や働き方を、ジュンヤはどう考えていますか?

モリ:
これからの働き方で大切なのは、自分の変化に自覚的にすることでしょうか。気持ちを不安にさせる情報が流通する今、気づかないうちにストレスを溜めていることって多いじゃないですか。自分が何にストレスを感じて、どうするとリラックスできるか。それを知ることが大事だと思います。
あとは多面性という言葉も、これから重要なキーワードになると思います。今持っているスキルが、今後使えなくなるかもしれない。常に新しいことをラーニングしてスキルに幅を持たせることで、社会が変化しても適応できるようになることが大事ですね。
ユーザーとメディアが寄り添える、コンテンツのあり方
飯髙:
メディアやコンテンツのあり方は、今後どうなると思いますか?
モリ:
これまではメディア側が伝えたい情報を、一方的に発信するだけでした。これからは受け取った側で情報が完結するような、双方向に関わることで成立するメディア・コンテンツの役目が、より重要になると思います。情報を受け取ったユーザーがそれぞれに解釈して、自分で語りたくなるような。能動的に応援したくなる余白を残した伝え方が、大事だと思うんだよね。
飯髙:
僕としては、これからのメディアは「誰が言っているのか」に、より焦点が当たると思います。
モリ:
海外とか北米のメディアでは、「誰が発信しているのか」をより強く打ち出してますよね。完璧な人間も発信者もいない、バイアスが入った前提で情報を発信して、ユーザーもそれを踏まえて情報を受け取る。これが成り立つことで、ユーザーのリテラシーも上がると思う。
飯髙:
具体的に、「このメディアがいい」と思った事例はありますか?

モリ:
オランダの『De Correspondent』という新興メディアは、スロージャーナリズムを掲げて話題を集めています。
参考:「速報も広告もやらない「新メディア」のジャーナリズム哲学を読み解く」|現代ビジネス
速報ニュースは扱わず、ひとつひとつのニュースにしっかりフォーカスを当てて、発信するやり方は今の時代だからこそとても大切だと思います。触れることで安心できる、安心できる発信の仕方というんでしょうか。手前味噌ですが、僕が副代表を務めるsoarもそれを意識して情報発信しています。
参考:「soar(ソア)|人の持つ可能性が広がる瞬間を伝えていくメディア」
飯髙:
最後に視聴者の皆さまへ、メッセージをお願いします。
モリ:
世界をよくするために、何ができるかを考えることがすごく大事だと思います。
文化人類学者のマーガレット・ミードは「少数の市民が行動したことで、社会が変わってきた。市民の力を信じよう」と話しているんです。
ひとりの力はちっぽけかもしれないけど、それぞれが望む未来や社会に向けて、行動に移せればいいですよね。
あとは社会や企業といった外的なサステナビリティを追求する一方で、「自分がいかに幸せでいられるか」という内的なサステナビリティも考えていきたいですね。自分が落ち着ける状態を作ったうえで、未来に向けたアクションを起こす。それは誰にでもできることなんじゃないかと思います。
――鈴木さん、モリさん、ありがとうございました。
DAY6の記事はこちらから。
コロナによって変わること/変わらないことを見つめ直す #NEWWORLD2020 DAY6
ホットリンクは「ソーシャルメディアマーケティングにスタンダードを創る」をミッションに、一緒に働く仲間を募集しています。
お気軽にご連絡ください。
募集中の職種を見る