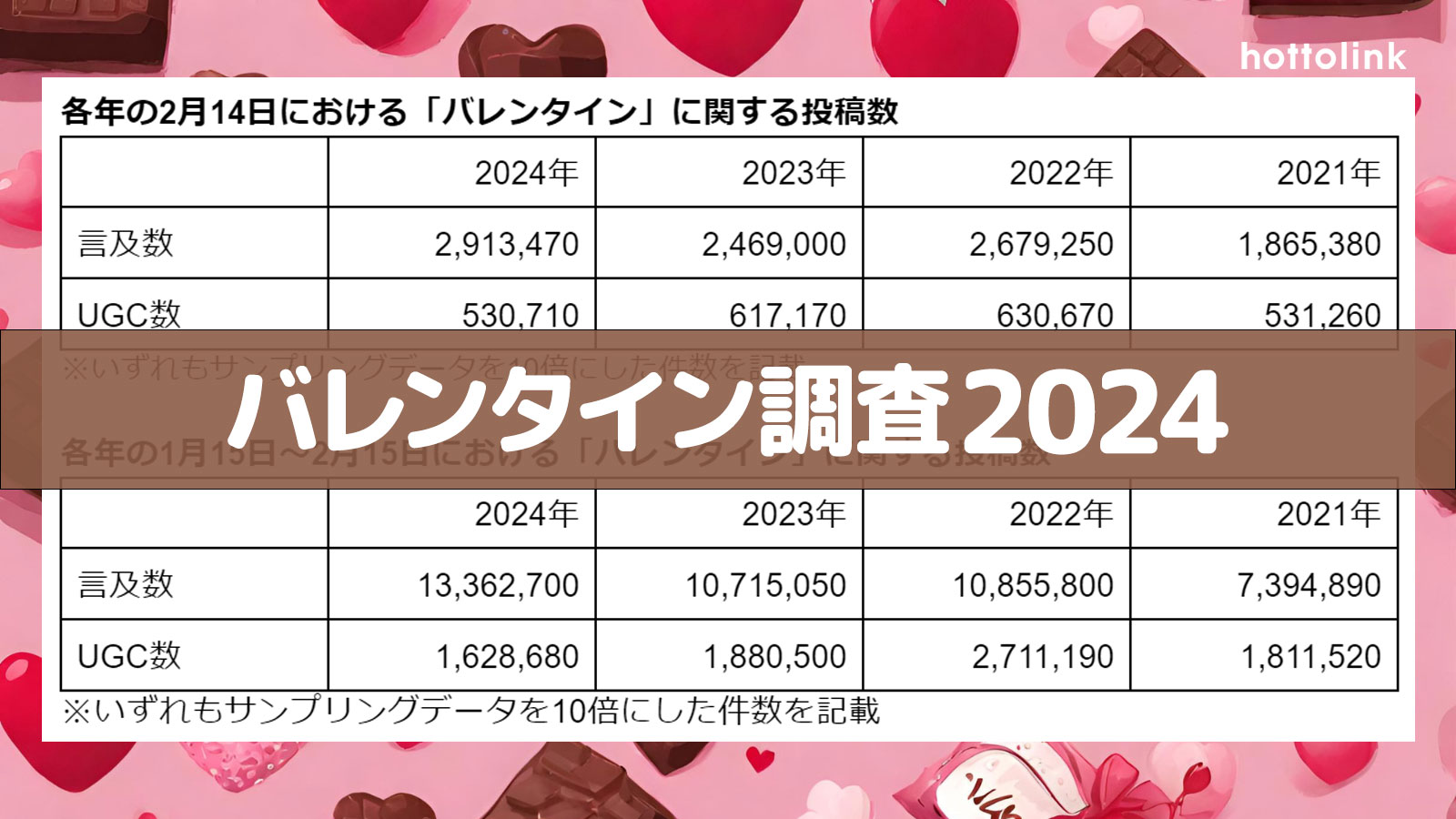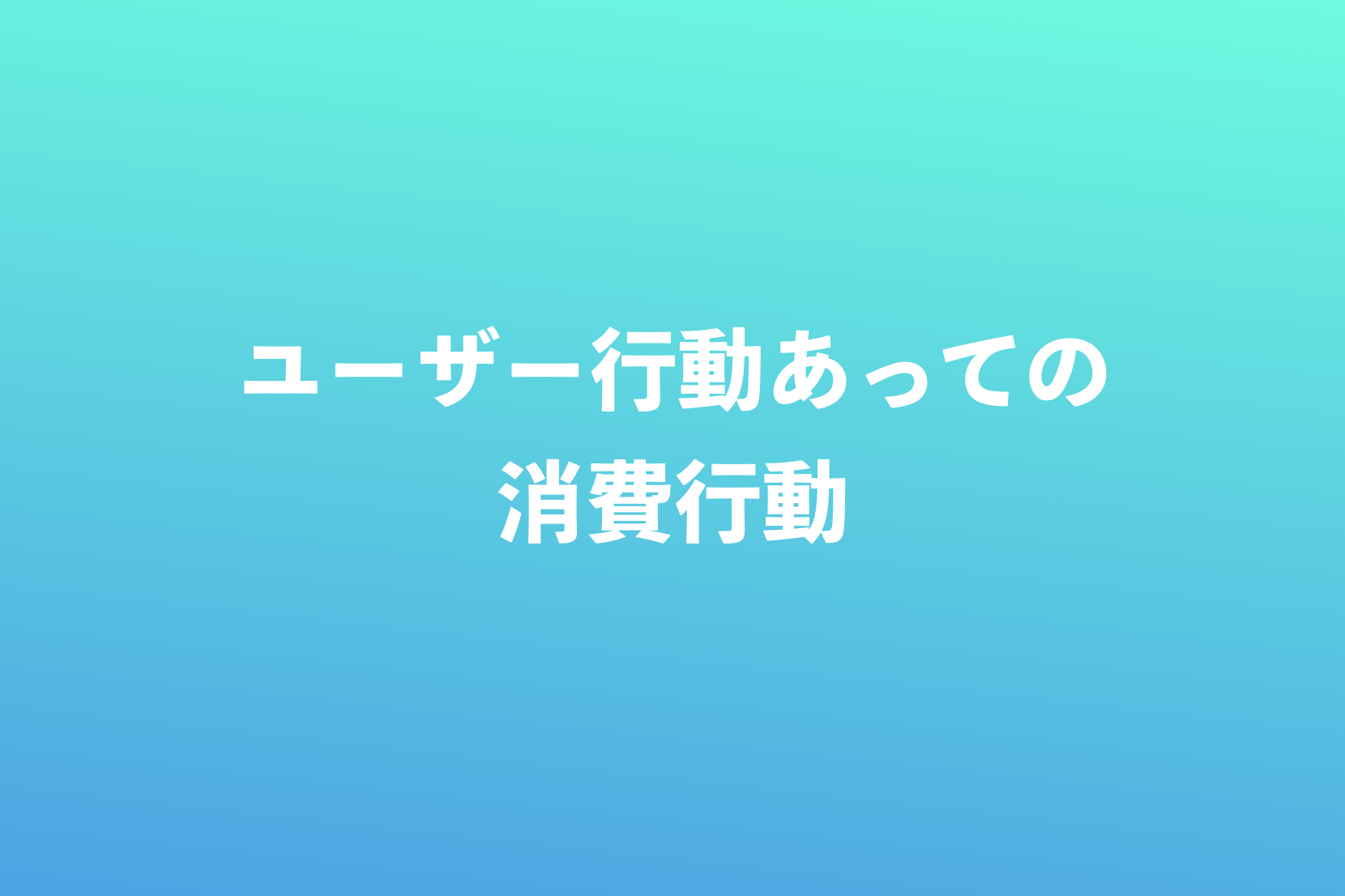 ソーシャルメディア上に商品・サービスのUGCが出るようになれば、ユーザー自身らの発信が増えることになるので、広告費をかけずにブランディングができるようになります。
ソーシャルメディア上に商品・サービスのUGCが出るようになれば、ユーザー自身らの発信が増えることになるので、広告費をかけずにブランディングができるようになります。
また、UGC数と指名検索数は相関することがわかっており、UGC数はソーシャルメディアマーケティングの主要なKPIとなります。
では、ソーシャルメディア上に商品・サービスのUGCが出るようにするには、どうすればよいのか。
そのためには、ユーザー行動の分析が重要です。
ユーザー行動はデータとなって現れる
ユーザーが何を思い、考えているのかについて知るにも頭の中は覗けませんが、「ユーザー行動」はデータとなって現れるので覗くことができるのです。 WEBサイトでは
・流入元 ・ランディングページ
・離脱ページ ・ページのスクロール量
・CTAボタンのクリック量
がトラッキングできるように、 ソーシャルメディアでは
・投稿内容
・アカウントの属性 ※取得できるSNSであれば。できない場合は過去の投稿内容などから類推
・投稿タイミング
・エンゲージメント(いいね数、RT数)
・メンション
などのデータを見ることができます。 UGCを増やすために、ユーザー行動を分析することで、施策の仮説構築に活かすことができます。
まずは基礎診断から
分析というと、慣れていない方にとってはどこから手をつけていったらよいか迷うと思いますので、 以下の手順に沿って、分析していくことをおすすめします。 まずは各状態を切り分けて、自社の診断をしましょう。
診断方法
ブランドに対してUGCが出ているかどうか、指名検索がされているかどうかをリサーチしましょう。 「自身の商品・サービスはUGCが出ているかどうか」 「自身の商品・サービスは指名検索されているか」 の確認です。 UGC数はソーシャルリスニングツールで(UGCが少ない場合にはTwitterのエゴサーチで代替可能です)、指名検索数はGoogleのサーチコンソールや、Googleトレンドなどで確認できます。 ①UGCが既に出ている(且つ、指名検索もある)ならば →UGCが既に出ているならば良い状態で、もっと増やせる余地がないかの分析に進むと良いでしょう。 なお、競合がこの状態であれば、成功の秘訣を探ってみるとよいです。 ②UGCは出ていないが、指名検索はある →UGCが出る可能性があるならば、シェアされるSNS運用に取り組んでいきましょう。 UGCとして真似されやすいような投稿をするなど、いくつかの方法論はあります。 具体的な施策の立案のための分析については、後述します。 ③UGCも指名検索も出ていない →この場合は、コモディティ商品かもしれません。 シェアされるためには強力なコンテンツが必要です。 こちらも、具体的な施策の立案のための分析については、後述します。
次はUGCが出ている具体的な分析を
パターンがわかれば、あとはパターン別の取り組みをすることです。
「自社商品が、最大限、ユーザーからUGCが生成されるようにしたい」から、分析しているのであって、そのための示唆を得ることが目的になりますよね。その取り組みに対して、有益な示唆を得られる分析を行っていきましょう。
一例ですが、各パターンがわかった後は、「誰が、何を、どうやって」の3つの理解を深めていくことをおすすめします。
それぞれ解説します。
誰が:どんな人がUGCを出してくれているか
ここで行うのは、UGCを作ってくれているユーザー属性の把握です。
どんなユーザー属性が中心となってクチコミをしているのかの分析を行うことで、UGCを出してくれやすいユーザー像を出し、次に狙えそうなクラスタはあるかどうかが分かってきます。
UGCを出してもらうために、集中的に狙っていくターゲットを特定していきます。
何を:ブランドのどんな提供価値がUGCとなって現れているか
ここでは、クチコミとしてどのように商品・サービスが言及されているかの把握です。
・どんな商品価値がクチコミされているのか
・どんなキャンペーンやコンテンツがクチコミされているか
・どんなRTで多くの共感を呼んでいるのか
といった観点で分析を行います。
こちらは、とあるアレルギー対応ケーキの事例です。
飯髙「その企業では、クリスマスにアレルギー対応のケーキを販売していました。100人ほどしかフォロワーがいなかったのですが、そのケーキを見つけた母親が、『アレルギー対応のケーキがあったことで、子どもに初めてケーキを食べさせてあげられた』という投稿をし、同じようにアレルギー持ちのお子さんがいる母親や子供のころアレルギーでケーキが食べれなかった人へ広がって、連鎖的に情報が拡散していったんです」
出典:ユーザーとしての自分を忘れない。ホットリンク飯髙氏が語る、SNS時代の企業が顧客と向き合うために必要な視点
このように、「アレルギーでもケーキが食べたい」ではなく「アレルギーでも他の子と同じようにケーキを食べさせてあげたい」というニーズがあったのです。
有名なAmazonのこちらのCMも、同じような欲求・感情を表現していますよね。
こういうった分析を通じ、ブランドに顧客が関わる理由は何か、シェアする動機は何かを探ることができます。
どうやって:どのような文脈・コミュニケーションでUGCが出ているのか
ここでは誰に、何を、どのように伝達されているかの把握です。
また、SNSに投稿されるにはどの文脈・瞬間・シーンが良さそうかの把握もできます。
例えば、UGCの投稿を分析して、
・店頭で認知したのか
・TVCMなのか
・WEBニュースなのか
・SNS上の会話なのか を見てみたり、
・その会話は友人同士なのか、知らない人なのか
・どういうハッシュタグが添えられているのか
・会話にどうやって出ているのかを分析する
・その中でもとくにTwitter映えする文脈は?
・ユーザー同士でどのように推奨に関する会話が発生しているのか
など、どういうコミュニケーションを促すとよいかの示唆を得られます。
分析のポイント
自社ブランドの分析だけでは、次のアクションにつながる示唆は得にくいため、比較をするのがおすすめです。
ベンチマークしたい代表的なブランドのクチコミを見てみると良いでしょう。
自社と競合の話題量にはどれだけ差があるかの基本的な調査はもちろん、UGCを多く出せている成功企業を徹底分析し、どういう工夫(UX、商品パフォーマンス、PR施策、キャンペーン)をしているか探ることで、自社にも取り入れられるヒントが眠っているかもしれません。
あとは、時系列で比較をしてみて、UGCが多く出ていた頃の施策と出ていない頃の施策を比べることで、ヒントが見つかるかもしれません。
UGC分析例
より具体的にイメージがわくように、さまざまな業種の分析例を紹介します。
レジャー施設の集客担当だったら
・同規模の競合と比較することで、シェアする理由の多さ少なさを探る
・撮影ポイントが狙い通りかどうか分析してみる
アプリの集客担当だったら
・先行するアプリのユーザー評価の声を聞いてみる
・どこに満足しているか、どこに不満を持っているか
・シェアする瞬間の引き出しを増やす
観光地のマーケ担当だったら
・カスタマージャーニーのどの瞬間がSNSに投稿されやすいのかを分析してみる。
・どのお店、どの観光スポットがUGCが出やすいか見てみる。
メディア担当だったら
・記事のURLで検索してみて、どのようなコメントがされているかを分析してみる
・コンテンツをシェアしてくれているユーザーの属性を分析してみる
・クチコミ数が急伸しているWEBニュースを分析し、記事広告のインプットにする
コンビニフードのマーケ担当なら
・パッケージや商品がどう写されているのか
・どういう食品ジャンルだとUGCが出やすいのか
・どこがウケているのか
・どういう感想をもたれているか
アクセス解析するようにクチコミ分析していくこと
分析方法は数多くありますが、今回は一部を紹介させていただきました。
ユーザー行動を分析することで、色々なことが分かってきます。
Google Analyticsでアクセス解析をするように、UGCも分析していきましょう。
(もちろん、場合によっては他のリサーチ手法を組み合わせましょう。
思い込みではなく、実際のデータを確認することで、ビジネスにインパクトを出せる示唆が得られるはずです。
<サービス紹介>
ホットリンクでは、UGCを活用したマーケティング活動を支援するツール・サービスを提供しています。

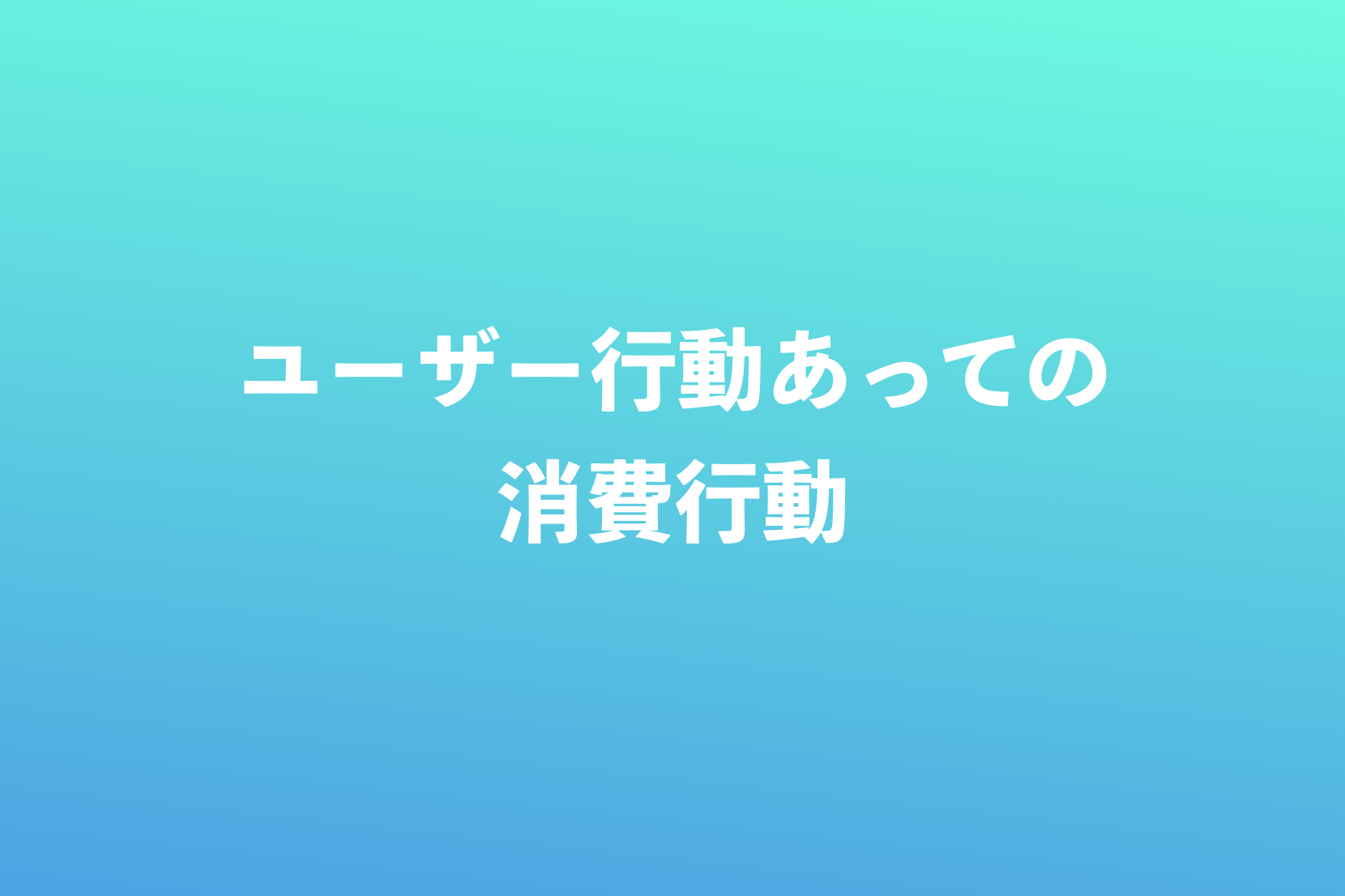 ソーシャルメディア上に商品・サービスのUGCが出るようになれば、ユーザー自身らの発信が増えることになるので、広告費をかけずにブランディングができるようになります。
ソーシャルメディア上に商品・サービスのUGCが出るようになれば、ユーザー自身らの発信が増えることになるので、広告費をかけずにブランディングができるようになります。