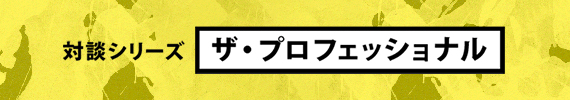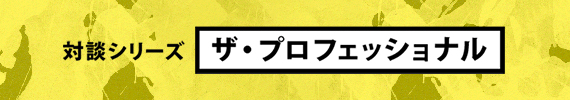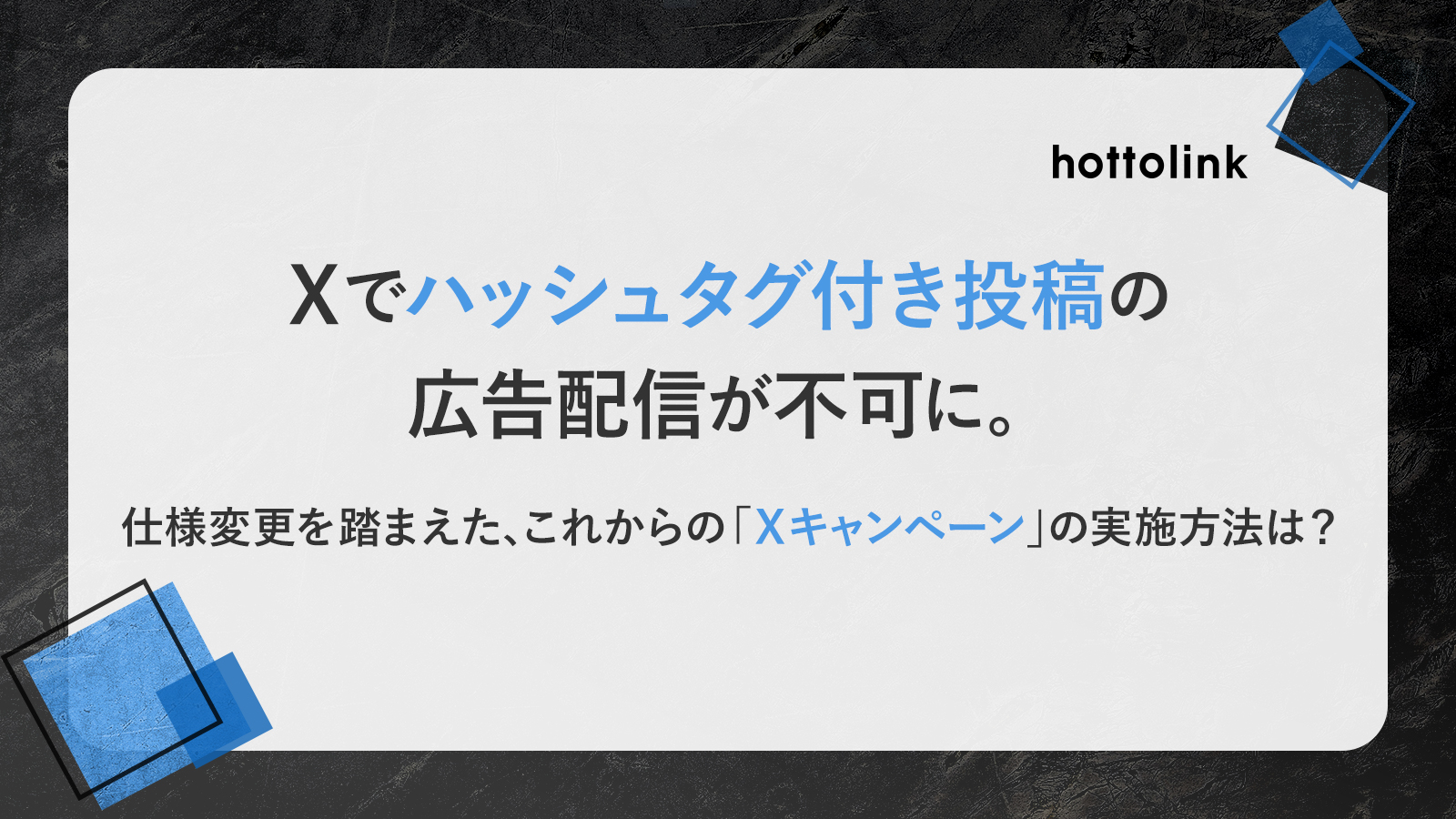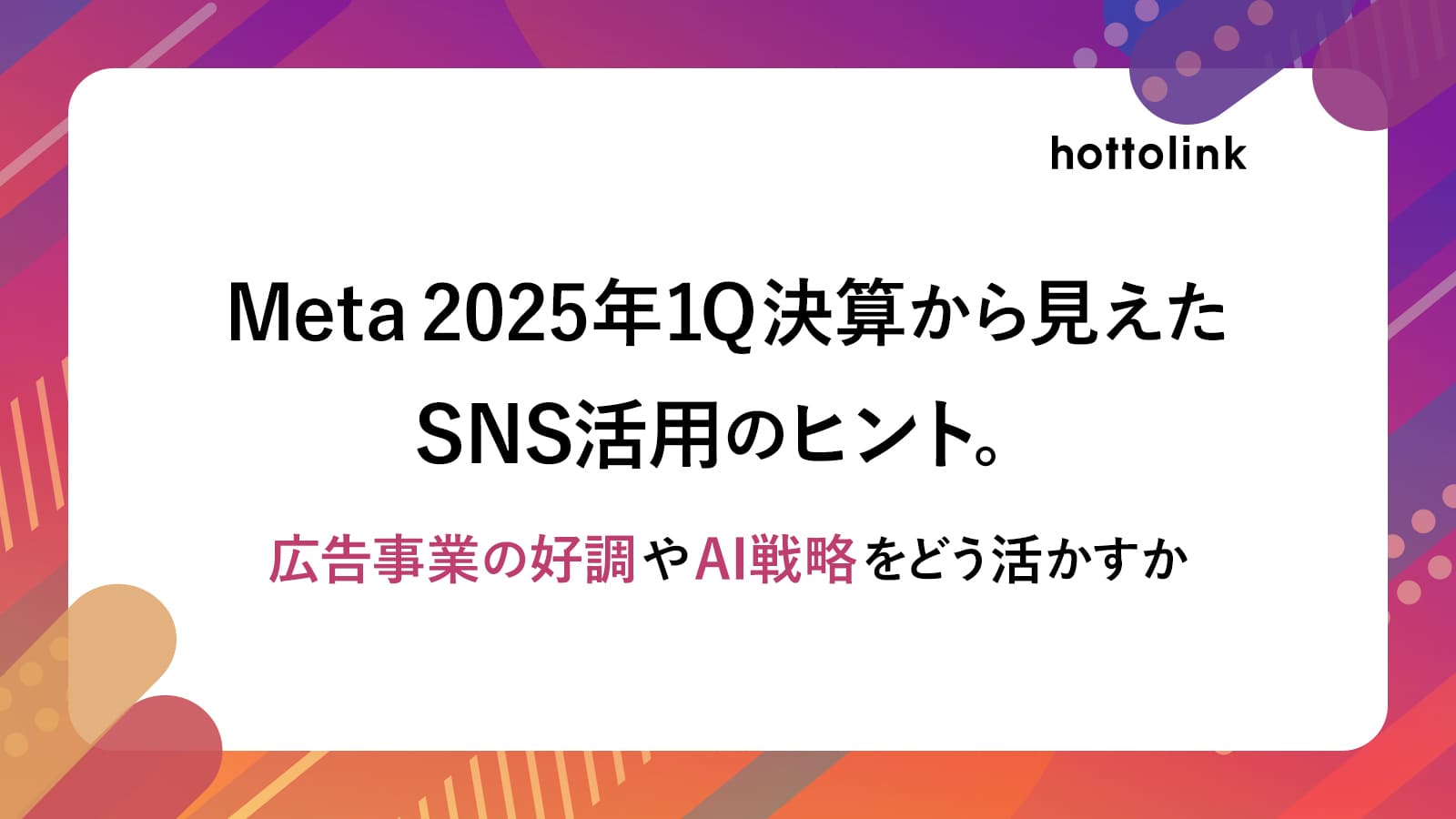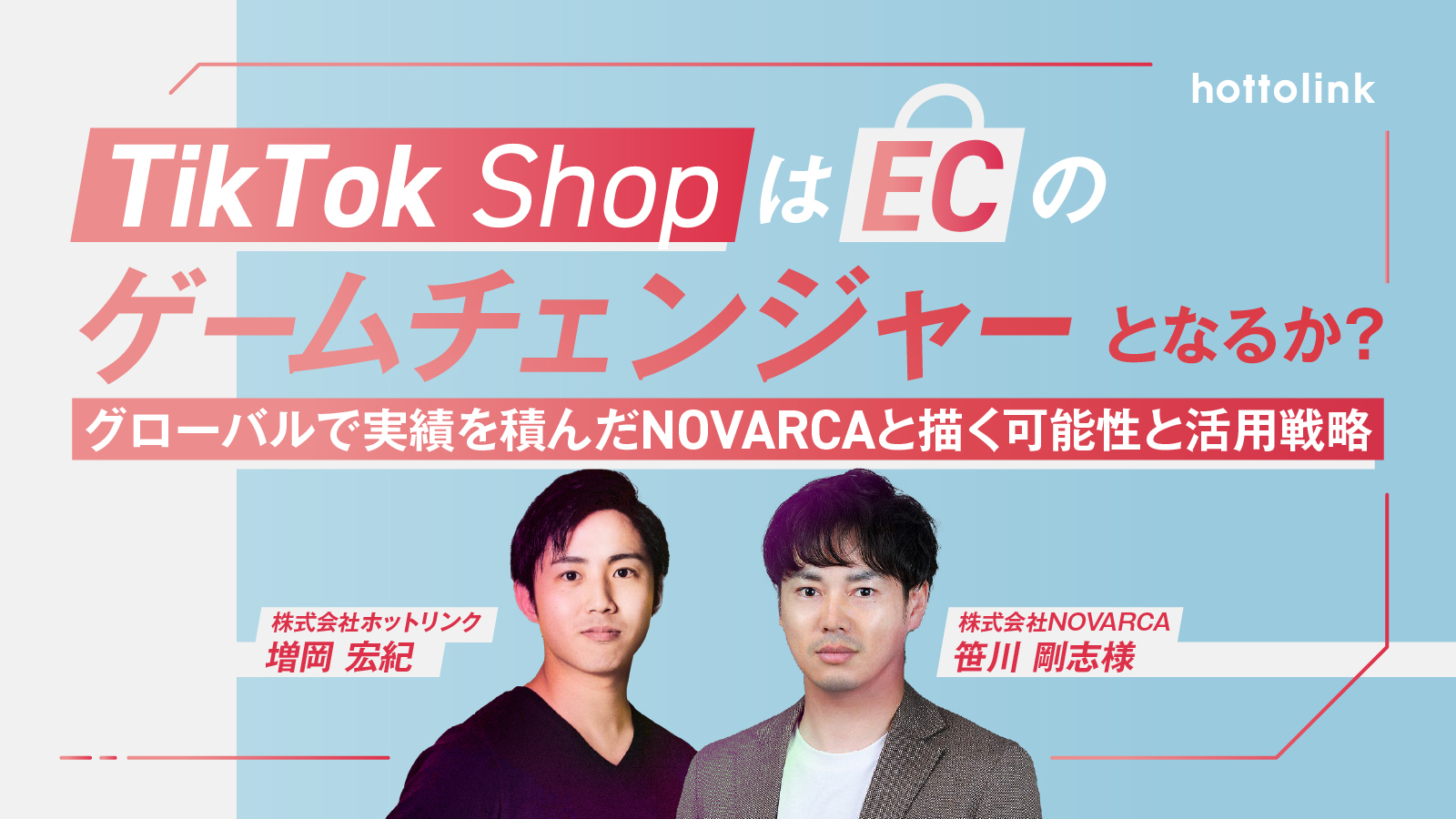ホットリンクCMO・いいたかゆうたが、各業界のトッププレーヤーを迎えてお送りする対談シリーズ「ザ・プロフェッショナル」。今回のゲストは、株式会社トライバルメディアハウス代表取締役社長・池田紀行(いけだ・のりゆき)さんです。
同社は、「ソーシャルエコノミーでワクワクした未来を創る。」をミッションに掲げるマーケティング会社です。弊社ホットリンクとは、競合関係ということになります。
ただ、2025年に1兆円市場と目されるソーシャルメディア広告市場において、同社も弊社もまだまだ発展途上の存在です。池田さんといいたかは飲み仲間でもあり、業界を健全に発展させる「同志」として今回の座組ができました。
編集長・澤山も憧れるマーケターの1人、池田さんのお話に耳を傾けてください。
(撮影:小林一真 進行・編集:澤山モッツァレラ)

紀行さん、なんで受けてくれたんですか?
いいたか:
紀行さん、今日はありがとうございます。改めて、なんでこの対談受ける気になったんですか?
池田:
そりゃ、受けなかったら「ケツの穴が小さい」って思われるからだよ(笑)。
一同:
(爆笑)
池田:
「あいつ、逃げたぜ」みたいなさ。
いいたか:
とはいえ今回って、真面目な意図もあって。僕、珍しく丁寧な文章で紀行さんにメッセージしたじゃないですか。
業界の横並びで、こういう座組あまりないですよね。同じイベントで登壇する時も、すごく距離を置きながらみたいな。「ダークソーシャル倶楽部」みたいな企画ならありかもと思ったけど、今回は「ザ・プロフェッショナル」で出演をお願いしたかったんです。
コロナ禍になって、いろいろなプレイヤーが出てきて。もちろん弊社も含めて各社すごく頑張ってる前提だけど、向かっている方向性がこれで正しいのかと思うこともあって。
運用にフォーカスしすぎたり、戦術面ばかり強調されるきらいもあって。本来、もっと本質的なところを話すべきだと思ってたんです。このテーマなら、紀行さんと話すのがわかりやすいなと思ってご連絡しました。
池田:
なるほどね。まあ、まだまだ業界がちっちゃい中、競合かどうかでいがみ合う理由なんてないしね。そもそもいがみ合ってないけど(笑)。お客さまの層も若干違うし。
僕としても、「手法論ばかりコスられるけど、本質的な議論が少ないな」という思いがあったんだよね。いいたかくんとなら、良い議論になると思いました。
いいたか:
ま、私もいがみ合ってないですが(笑)。そして、この業界これからなんですよね。弊社も3年くらい前に本腰入れてやっと10億程度の売上規模になりましたが、5年後に1兆円市場になるってことを考えればビアサーバーをおちょこですくうようなもので。
そんな中、横を見てどうこうって意味がない。手を組もうじゃないですけど、仲良くやって、業界全体でお客さんを成功させたい気持ちがありますね。

「これからはECだ」とか、煽りすぎないのが大事。
いいたか:
コロナ以降、SNSマーケティングをやる上で変化を感じている部分はありますか? 消費者のあり方や、広告のあり方など。例えばアパレルのクライアントさんが店舗重視からEC化にかじを切ったとか、SNSの重要性を改めて認識した、という部分はあると思います。
池田:
「リアルじゃないと」が意外とそうでもなかった、と強制的に学習させられましたよね。
感染拡大期、アパレル業界はお客さんが来ないからバンバンお店を閉めて、そのぶんECにチカラを入れざるを得なくなった。コロナ前は、「そうは言ってもリアルじゃないと」という感覚がありました。それが全世界同時に(リアルは)できません、ってなって、デジタルとSNSをやらないとどうにもならなくなった。
ショック療法の結果、「意外とデジタルいけるね」「ここはハイブリッドだね」「ここはやっぱりリアルだね」という棲み分けが進んだ感はありますね。とはいえ、ECで売上のすべてを補填できるほどではない。店舗スタッフもたくさんいるから。
いいたか:
そうですね。
池田:
リモートワークにしてもそうだよね。僕も否定派だったし、コロナが無ければ絶対に導入しなかった。
「リアルとデジタルの融合」だなんだ言ってたのが、融合もへったくれもなくなった結果一気に動いたのは良かったと思います。
ただ、日本のEC化率もいびつだから。アメリカに比べると、EC化率が上がっていない業界もたくさんある。「これからはECだ」とか煽りすぎると、例えば「生鮮食品をぜんぶEC化できるのか?」って話にもなる。そういう話は冷静に進めたいね。

試行錯誤を重ねた組織は、絶対に強くなる。
いいたか:
お客さんも試行錯誤してますよね。お店を閉めるといっても、リアルは変わらず重要だからメインどころの店舗は残してます。原宿とか表参道、あとはショッピングモール内とか。
集客が難しい店舗は閉めて、スタッフさんをオンライン接客に持っていったり。商品を試着できるようにして、ZOOMでアドバイスしたり。ALL YOURSさんが早い段階で取り組んでいましたね。
池田:
やっぱり、試行錯誤を積み重ねた組織は絶対強くなるよね。
企業によっては、インスタントに事例をマネておいしいところだけ学習したい、って欲求があると思うんですよ。でも実際は「ZOOMやってみた」「イマイチなのでインスタライブやってみた」「それもダメだったので次は……」みたいにいち早く考えて、行動に移していく組織が強い。
事例がそろったところで良いものをピックアップしよう、という態度では大きな差がつくと思う。
いいたか:
そうですね。これって日本特有の傾向なんですかね?
池田:
どうだろう。海外もケーススタディってやってるから似たようなものだろうけど、横並び意識はより強く感じるよね。
いいたか:
「どこかが動くから、ウチも予算張っていこう」ってケースは多いと思うんですよね。
池田:
SDGs然り、パーパス然り。SNSもそうかもしれない。
いいたか:
言葉が独り歩きして、後付けで語られるケースが多いと思うんですよね。本当にそんなストーリーで進めてましたっけ? みたいな。流行りの言葉や手法が出てくると、それに飛びついてしまう弊害も考えなきゃいけないと思ってます。
池田:
そうね。ただ僕、パーパスだけは流行っていいと思っていて。流行ることでハッピーな方へ向かうから。
マーケティングの役割が、変わったんだよね。良いものを作るまでは一緒だけど、「多くの人に大量に届け、売り上げ・利益を最大化する」ことではなくなった。株主が求めるものはESG(参照)になったんだから、持続可能な成長をしている会社にしか投資は集まらないわけです。
ここは大いに悩み、試行錯誤してほしい。そういう意味で、パーパスというワードの流行はできる限り長く続いてほしいですね。バズワードではあるけど、本質に沿ったバズなのでウェルカムです。

ストックのクチコミのほうが、何十倍も影響力大きいでしょ。
いいたか:
これもちょっと抽象度の高い話ですけど、今後のUGC・クチコミの可能性ってどういう風に捉えていますか?
池田:
それでいうと、口コミにおける直接的な売上への影響は、フィードよりもストックのほうが何十倍も大きいと思ってるんだよね。Amazonや食べログ、カカクコムやアットコスメ然り。
ニーズが顕在化した瞬間に、人は検索するわけだよね。そして検索においてフィードの口コミは出ない。どこを見ているかというと、ストックになる。そちらの影響力がもっと認識され、可視化されるといいなと思っていますね。
澤山:
なるほど、確かに。自分でも関与度の高い商材ほど、口コミを探しに行きますね。
池田:
いろいろな商品がレビューを見て買ったり買われなかったりしているわけで、そこのZMOT(Zero Moment-Of-Truth)をどう考えるかという話なんですよね。
そのあたりの考え方は、まだまだ偏っていると思います。やっぱり「ソーシャルメディアマーケティング」「SNSマーケティング」なんて言葉は、無くなるほうが健全なんですよ。デジタル○○もそうかもしれない。でも、現状は全然無くならないわけだよね。
澤山:
手段の目的化が起こるうちは、健全ではないですよね。
いいたか:
同感ですね。現状、分業が行き過ぎているというか。全て並列で見て、どこを取っていけば一番利益が拡大できるかというシンプルな話をすべきなのに、CPAいくらとか流入いくらとか部分最適に目が行き過ぎている。
プラットフォームが増えて、一つのモノを買うのに皆いろんな情報を調べるわけです。そんな中、なぜ出口ありきで考えてしまうのか。これはずっと言ってることなんですが、全体の傾向としては未だに変わらないですね。
池田:
意識変容が課題なのか、それとも態度変容なのか、行動変容が必要なのかみたいな話を理解すれば、現時点で何が重要かわかるんですよね。でも、分業がすぎると「ここからは、私の仕事じゃありません」という話になってしまう。
「SNSってファネルの中でいうとドコになるんですか?」と聞かれれば、便宜上は「ココとココとココですね」と答えるんですけど、実際は「マーケティング活動の全て」なんですよ。
澤山:
SNS自体が、なんなら「本流のマーケティングとは関係ないもの」という捉えられ方を未だにされているきらいはありますね。西井敏恭さんも当連載のインタビューで「SNSの重要性は、1%にしか認識されていない」とおっしゃられていました。

トイレリフォームの広告が、バズるか? 少し考えればわかりますよね。
池田:
仮定の話ですが、自分が年間売上100億円あるパン屋さんのマーケターだとして、数千万円ぐらいのマーケ予算があるとして。何をやらなきゃいけないか? 認知、興味喚起、理解促進、WEBサイト、SNS、来店促進……いろいろありますけど答えは「全て」ですよね。
部分最適じゃダメなんです。「熱狂」や「ファンベース」といった概念にしても、「ファンがいればライフタイムバリューが最大化する、新規顧客を開拓してくれる、万々歳」なんて話ではない。
でも、そうした概念が流行るとどうしても「これ一発で解決」という思考になる人が増えるのかな。選択じゃなくて組み合わせの話なんだけどね、「これからはULSSASだ!」とかね(笑)。
いいたか:
(笑)フィードばかりじゃなく、ストックを重視しようという話はおっしゃるとおりだと思うんですよ。
フィードに投稿することで認知を取れるかもしれないけど、人って誰かが発信したものを見て「他の人は何を言ってるんだろう」と検索するわけですよね。
その検索結果の中、例えばインスタなら上位にいい投稿があればめちゃくちゃ興味を持たれるのに、自分のタイムラインばかりキレイにしても意味がないんですよね。
池田:
「トイレのリフォームをして最高だった!」という誰かの投稿が流れてきて、『よっしゃ、リフォームしたろ』って思うか?」ってことなんですよ。
「トイレのリフォーム、最高だったよ! 100万円かかったけど、みんなやるべきだよ!」ってUGCが出ても、ニーズが無かったりタイミングが合わなければやらないよね。普通に考えたらわかるのに、なぜか会議室でプランニングしたら似たような話が出てきてしまう。
トイレのリフォーム投稿がバズるなんてことある? 仮にあったとして、その投稿で契約が倍増することある? 実現不可能なことを要求してしまう思考って、あると思うんです。
澤山:
コロナ禍でリアルの買い物が減り、購買者としての実感が薄くなった部分はあるのかもしれないですね。
先日、かなり迷って68,000円のアウターを購入したのですが、これって一種の高関与商材だなと思って。安くない金額なので、デパートの中を歩き回って類似品を実際に手にとって比較して、試着して、スマホで商品の検索もやって、ウンウンうなった末にエイヤと買いました。
こういう高関与な買い物の機会が減ることで、消費者としての実感が薄れた部分はあるのかなと思います。
池田:
本当にそれなんですよ。家を買う、住み替える、高い掃除機や洋服を買う、何でもいいからテーマを決めて「どう買ったのか」を社内でワークショップやるのは有意義だと思う。理論とかフレームワークとか新しいマーケティングコンセプトとかを議論する前に。
最初に「何をしたか?」を聞いてみるのがいいですね。ファネル云々を度外視して、最終的に抽象化してまとめる。そうしたら「これが最初の認知経路だね」「興味を持つきっかけってこんな感じだね」と、リアリティある感覚が手に入ると思うんですよ。

事例を聞きたいのは、わかるんですが。
池田:
リアリティある消費者実感。例えば「これからはAISASだ」みたいな話をしてもいいけど、一方で一般的な牛乳や豆腐を買うのにAISASで来るか? という実感も持っておかないといけない。
アテンションして興味を持ってサーチして購入して、SNSにやってきて「うまい!」って口コミ書くかって言ったら書かないんですよね。消費者としてのリアルな実感を持たないまま、流行りの概念をそのまま自社ブランドに当てはめるのはダメだと思うんです。
いいたか:
そこは、自分のお金か他人のお金かで全然違うのかもしれないですね。記憶がちょっと曖昧ですがスタンフォード大学で、1,000円渡されて「24時間後に一番大きな金額にしたチームの勝ち」といったワークがありましたよね。ああいうものは、すごくいいなと思っていて。
昔の話ですが、新卒教育で似たようなことをやってすごく盛り上がったんです。500円を渡して、24時間後に一番大きくしたチームの勝ち。
雨降りだったので「傘を売って大きくしよう」というチームもあれば、新橋に行ってお客さんが集まる場所で「一曲歌うから500円ください」ってチームもあって。いろんな個性が見えましたね。
池田:
ブラック企業の新卒研修みたいだ(笑)。
いいたか:
昔の話ですから(笑)。自由なテーマでやってもらったんですけど、すごく自分ごと化されるんですよね。
池田:
そうね。息子には、中学生か高校生になったら、お小遣いを毎月あげるんじゃなく、一定のまとまった額を与えて「これがお前の資本金だ」ってやりたいと思ってるんです。どう使おうが自由、お小遣いはここから稼いで捻出しろと。
縛りもいくつか設けます。例えば「人から感謝されること」「転売ヤーはNG」あるいは「1人でやるな、誰かを巻き込め」とか。そういう思考のプロセスってすごく大事だと思うし、足りてない現場は多いのかなと思ってますね。
いいたか:
お小遣いを毎月もらうのが当たり前だと、「1,000円をどう使い切るか」を考えても「どう大きくしよう」とはなりにくいんですかね。
池田:
どうだろうね、海外はお小遣い制なのかもわからないけど。
澤山:
アメリカだと、レモネードを売るみたいなケースはあるみたいですけどね。「小さくとも、自分の元手で稼ぐ」経験はいいんでしょうね。
池田:
自分で考えるのが大事です。講義をやっても、事例の話はやっぱり評判がいいんですよね。事例をたくさん出すと、講義後のアンケートでも満足度が高いです。でもね、そればかりじゃ本質的なものにならないんだよ。事例の焼き直しにしかならないので。
いいたか:
プレゼン資料にも事例は必ず入れますし、入れなきゃ「今の話、何だったの?」って言われがちですね。
池田:
入れないで話すと「教科書的な話ばかりでした」って書かれたりね。必要だと思って喋ってるんだけどなあ(苦笑)。

マーケティングとは、環境変化にフィットさせ続けること。
澤山:
最後のパートになります、お二人はマーケターとして今後どういうキャリアを描いていらっしゃいますか?
池田:
そうだなあ、食うに困らなくなったらここ(池田さんのご自宅)でカレー屋を開こうと思ってるんだけど(笑)。今は求められる限りは、例えば研修施設を作ってマーケティング道場とかやっていたいね。
やっぱり、行き着くところはそこかなと思っています。道場長として「あなたの言ってること、そろそろ古いっす」って言われるまではやっていたいですね。
いいたか:
私もそうですね、自分の持っているものは早く誰かに渡したいですね。
池田:
でも、主役が好きじゃないの?(笑)
いいたか:
(笑)20代の頃は「オレが、オレが」でしたけどね。今はSNSの仕事をしてますけど、やっぱりSNS自体は若い人のほうがわかってるじゃないですか。でも、表面的な知識だけでは軽いものになるので、歴史的な経緯をちゃんと教えたいなと思ってます。
うまくいった事例であっても、実はそこまで考え抜かれたものではないかもしれない。もう少し再現性を持ってやれる人を増やしていきたいですね、道場長になるかはわからないですけど(笑)。
池田:
うるさいおじさんには、なりたくないね。
いいたか:
なりたくないですねえ。今をどうこう言うより、「これまでの経緯はこうだったんだよ」という話を優しく伝えたいですね。
池田:
若い子たちのほうがデジタルに詳しいし、SNSを誰よりも使っている。プラットフォームをハックすることもうまい。でも、マーケティング全体の中で最適化することに関して、当然ながらわれわれのほうに一日の長があるわけじゃないですか。
俯瞰的なポジションに立って、「いまココの話をしてるんだよ」という話はしたいですね。
澤山:
なるほど。とはいえ、SNSというジャンルで若い人たちに啓蒙を続ける以上「現役感」は必要ですよね。実務を手放してはいけないというか。そういう意味で、お二方とも一生現役ではおられるんでしょうね。
池田:
そうそう。「TikTokって何?」はまずいけど、自分でアカウント作って動画撮って編集して投稿して、みたいのはもう限界(笑)。
プラットフォームをハックするとかは若い子に任せて、自分はマーケティング全体で考えたときにどういうものか、全体をデザインすることを意識するにはいい頃合いなのかなと思ってますね。
土地勘とか勢力図とか、すべて動的だから。地図がどのくらいの動きで、どのぐらいのスペースで、どういう時間軸で動いてるかを俯瞰して捉えることには大きな価値があります。
なぜなら消費者が変わったところ、環境変化にフィットさせ続けることがマーケティングだからですね。そこが見えなくなったらマーケター引退だろうな、と思ってます。
澤山:
ありがとうございます。最高の締めです。
池田:
すごいね、こんな感じで喋ったのがまとまるんだ(笑)。記事の仕上がり、楽しみにしています。

編集後記:澤山モッツァレラ
池田さんの話には、小手先でない「幹の太さ」を強く感じました。マーケティングという目的があり、SNSという手段がある。今はその手段が有効だから、それを使う。
いいたかも常日頃から言っていますが、われわれはあくまで「マーケティング」を行なうわけで、全体最適でモノを考える必要があります。
この取材前に池田さんのnoteをすべて読み返しましたが、池田さんの主張の根幹は首尾一貫していました。編集者としても、こうした「幹の太さ」を感じてもらえる人間になりたいと強く思う取材になりました。
次回は、株式会社YOUTRUSTの岩崎由夏さん・大前宏輔さんに登場いただきます。公開は12/6週を予定しています。どうぞお楽しみに!
今回の「ザ・プロフェッショナル」もお楽しみいただけましたか? 本シリーズでは、今後も各業界で活躍するさまざまなプロフェッショナルをお招きして対談を行ないます。過去の記事はこちらからご覧ください。