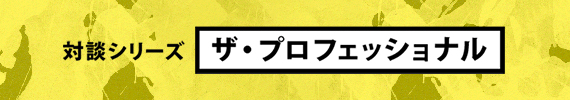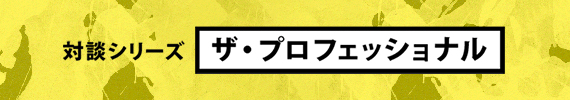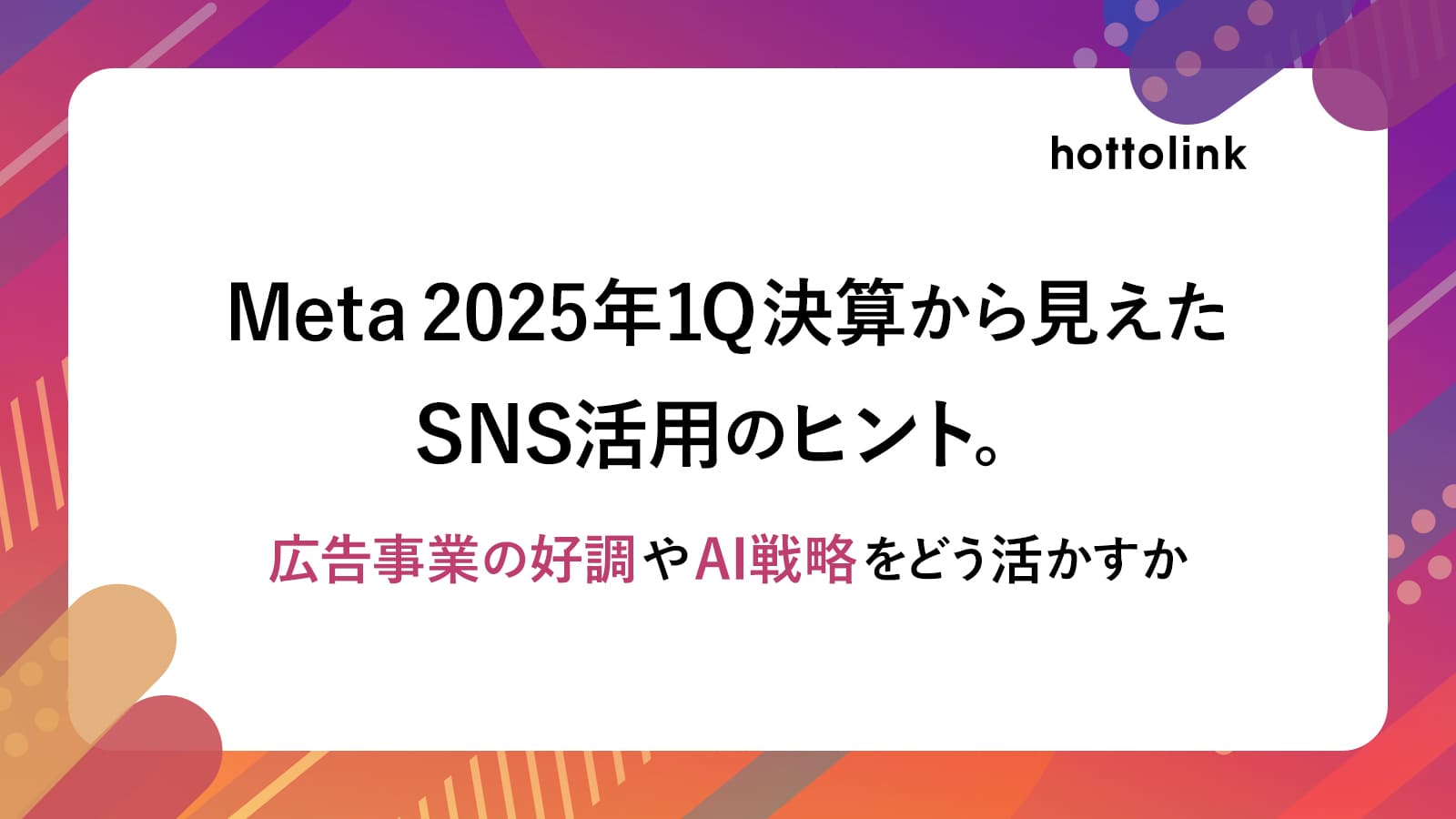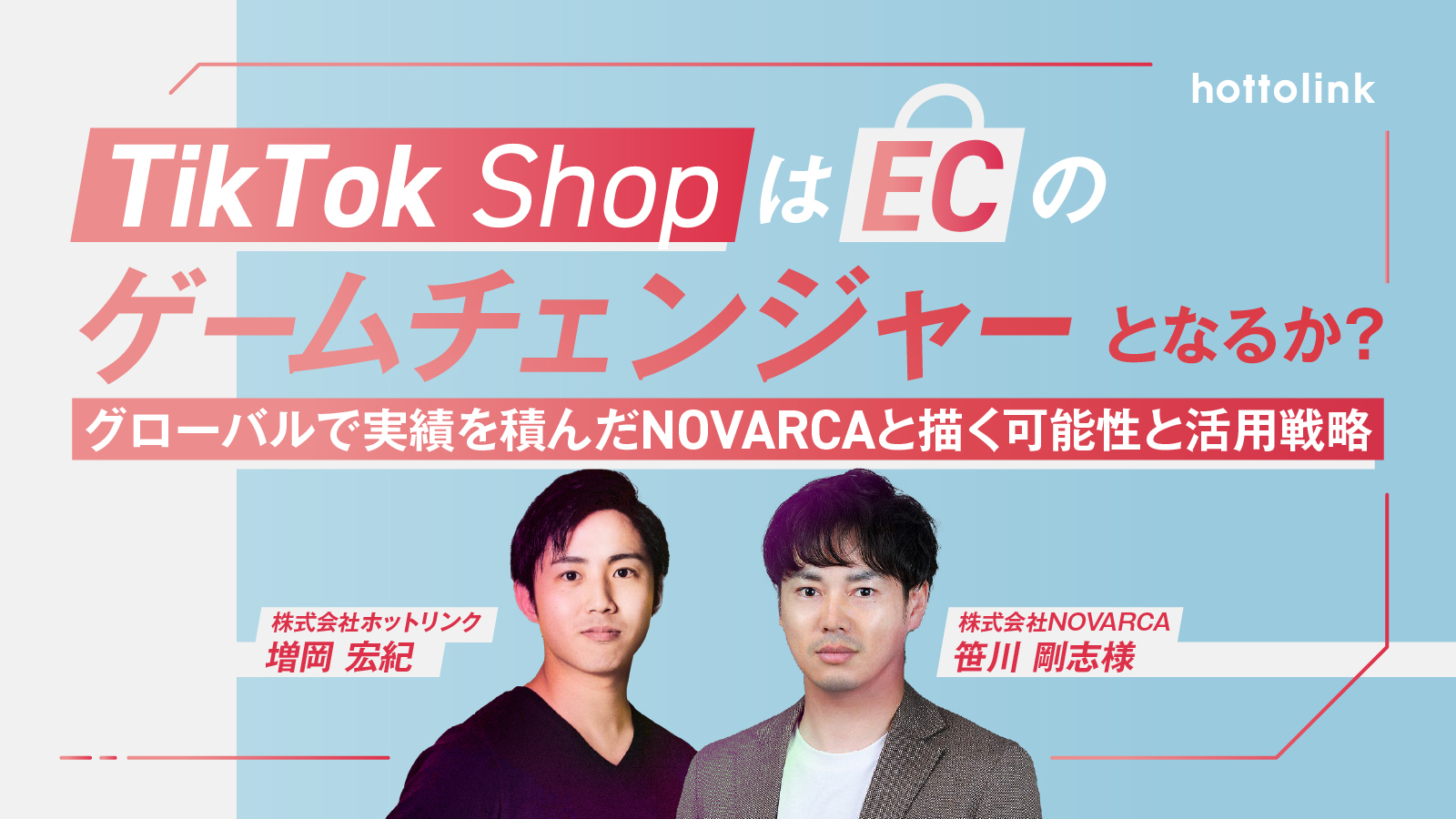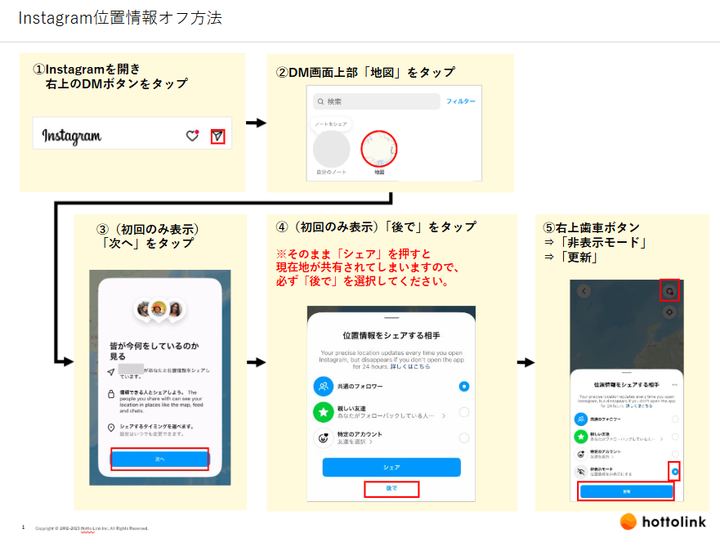「第5波」が過ぎ、情勢が一段落したころに収録された本対談。鬱屈した日々からの解放を祝うように、稲村ヶ崎(神奈川県鎌倉市)はさんさんと輝いていました。
ホットリンクCMO・いいたかゆうたが、各業界のトッププレーヤーを迎えてお送りする対談シリーズ「ザ・プロフェッショナル」。今回のゲストは、株式会社ベイジ代表取締役・枌谷力(そぎたに・つとむ)さんです。
テーマは「ハイブリッドワーク時代のマネジメント」です。コロナ禍が落ち着き、オフィス回帰をにらむ動きも起こる中、枌谷さん自身は福岡への移住を決定。すでに同社は、フルリモートでの採用も活発に行なっているそうです。
ホットリンクでも、基本リモートワーク勤務に舵を切りました。一方、マネジメント面においてはリモート・リアルそれぞれに課題が存在します。こうした課題に、ベイジさんはどのように取り組んでいるのでしょうか。由比ヶ浜~稲村ヶ崎の開放感あるロケーションで、闊達な議論がかわされました。
(写真・小林一真 進行・執筆・編集:澤山モッツァレラ)

機微がわからない人に、リモートは向いていない
澤山:
緊急事態宣言が明け、感染者数が落ち着いたこともあってオフィス回帰の流れができています(2021年10月時点)。その中でベイジさんはリモートワークを継続、枌谷さん自身は福岡へ移住されるそうですね。
枌谷:
そうですね。ネットを見ていると「オフィスのほうが素晴らしい」という論調も見られるんですが、正直まだ答えは出せないと思うんですよ。
いいたか:
確かに。僕自身も鎌倉に越して、「オフィスへ毎日通う」という選択肢はなくなりました。かといって、全くオフィスへ行かないこともないですから。どう考えても、ハイブリッド型になると思いますね。
枌谷:
やっぱり「選択肢がある」という状態が理想だと思いますね。毎日会社に出たいなら、そうすればいい。月イチ出社で、あとはリモートにしたいならもそれもOK。評価自体は、結果によって示される。
いいたか:
一方で、会社の文化を作るという部分ではリモートに限界を感じています。リモートになると自分の領域にこだわりが持てる一方、チームを気にしなくなっちゃう部分があります。あるべき組織像が、ねじれてしまうというか。

枌谷:
そこは確かにありますね。結局、元々の文化と仕事のスタイルによる気がします。隣のことをそこまで気遣わなくても、ゆるく繋がれる文化なら成り立つ。リモートワークしか選べない働き方だと、難しい。
あとリモートワークがうまく機能するかどうかは、社員のキャラクターにも依存すると思います。例えば、コミュニケーションの細かな機微がない人にリモートは向いていないな、とは思いますね。
いいたか:
なるほど、なるほど。
枌谷:
例えば「これやっとけよ」と言われたとして、オフィスにいて顔を見られるなら「別に怒ってないし、いつもこんな感じだしな」となるじゃないですか。でも、リモートワークでテキスト中心のコミュニケーションになると、わからなくなる。
そこで「ビックリマークを入れよう」「絵文字をつけよう」と配慮できる人は円滑な人間関係が作れると思います。ですが、無機質なコミュニケーションを好む人だと、積もり積もって人間関係がギクシャクしてきたりとか。うちの会社ではあまりないのですが、他社さんの話ではちらほら聞きますよね。
いいたか:
それは確かにあるなあ。テキストで送る時も、僕めっちゃ気にしますもん。「これ、ちょっと冷たく思われるかなあ?」みたいなのは。
枌谷:
最近のチャットツールって、発言を編集したら下に小さく「編集済み」って出ますよね。僕のコメント、「編集済み」ばかりなんですよ(笑)。
一回投げてから、だいたい編集してます。私は社長という立場なので、同じ言葉でも重みが違うと思うんですよね。なので不用意に無機質な言葉を投げかけると「こわい」となってしまうリスクがある。だから投稿した後も「あーこれはもっとこう書いた方がいいかな」とつい編集しちゃうんです。
いいたか:
そうですよねえ……。
枌谷:
そういうアンテナを立てないでリモートワークをすると、「上から目線」「一方的」と受け取られるコミュニケーションが増え、チームの雰囲気が徐々に悪くなっていく気がしますね。

テキストだけで愛着がわく人、いますよね
枌谷:
リモートのほうが成果主義に寄る一方、感情の機微に繊細になる必要もある。それが僕の思っていることですね。
いいたか:
わかります。リモートになって、今までなら返事をしなかったものにも返してます。最後に「ありがとう」と付け加えるとか。なるべく自分で終わらせることは、心がけてますね。
枌谷:
ああ~。
いいたか:
「上司である自分ができる、唯一のこと」ぐらいに思ってやってます。
枌谷:
ですね。リモートワークだと、顔や声でやっていた感情表現をテキストで表現しないといけなくなる、というのは大きいですね。
そういう意味で、TwitterなどSNS上でのテキストコミュニケーションが得意で、それでファンを作れるタイプの人は、実はリモートワークに向いていると思いますね。
いいたか:
確かに、わかりやすい。

枌谷:
テキストで心を繋げられる人。ソーシャルメディアを見ていると、テキスト情報しかないのにすごく愛着がわく人っているじゃないですか。
テキストでしか繋がっていないけど、その人のことをすごく好きになったり「一緒に働きたい」と思ったりすることは、十分起こりえる。ただし、これを実現する能力は属人的な能力でもありますよね。組織としての成功法則にはなかなかしにくいところがあります。
いいたか:
「これが組織コミュニケーションのあり方だ!」って言われると一気にうさん臭くなりますね。
枌谷:
そうじゃないんですよね、「みんなビックリマークつけよう」とかじゃない。
もはや誰も気にしなくなってるけど、メールの冒頭に「お世話になっております」ってつけるじゃないですか。あれになっちゃダメなんですよ。誰も何も思わない、形骸化したテキストじゃないですか。
澤山:
形式上、仕方なく入れているテキストなんですよね。
いいたか:
あれを見ても、何も思わないですね。
枌谷:
ある特定のフォーマットのテキストを使えば解決する、という簡単な話ではないのが、リモートワークにおけるテキストコミュニケーションの難しさですよね。

「リアルは重要だ」という認識は、残したい。
澤山:
僕は、ホットリンクに2021年1月から入社しました。正直、3月末くらいまでは「会えないのしんどいな」と思っていましたね。いいたかさんとはプライベートを共有させてもらってるものの、一緒に仕事をしたことはない。他メンバーも名前を知っている程度なので、細かい機微がわからなくて。
そういう意味で、グラデーションは必要な気がします。入社年次の若い人はなるべく週イチでもオフィスに来る、彼らに関わる年次の深い人も来る、それ以外のメンバーはフルリモートでもOK、みたいな。
枌谷:
なるほど。いいたかさんは1on1の使い分けはされていますか?
いいたか:
使い分けてないですね。1on1は完全にオンラインです。ジュニア層は毎日15分ぐらいFBの機会があり、中途は月イチぐらいですね。
枌谷:
ウチも基本、オンラインです。弊社はDiscordを使用しているので、そこの1on1ルームでやります。
ただ、キャリアの深い話やしっかり向き合う必要がある悩み相談については直接会って、ホワイトボードに書きながら2時間ぐらいみっちり話したりすることもあります。この手の話は、オンラインだけでは厳しいと思う。

いいたか:
単純に、リアルの価値が上がりますよね。シンプルに会って話すことが面白いし、関係ない話から本筋の学びに繋がったりする。僕も、ケースによってはもちろん直接会ったほうがいいと思います。
例えば今、全社員ほとんど経費を使わないじゃないですか。だから「マネージャー同士で月イチで飲みに行っていいよ」という制度を作るとか。澤山さん、他部署のマネージャーとご飯行ったことありますか?
澤山:
残念ながら、ないですね。
いいたか:
ですよね。これは絶対やったほうがいいと思ってて。最初は面倒に思うかもですが、3回も使えば「誰かとサシ飲みできて、しかも会社からお金が出る」ってめちゃくちゃありがたいと思ってもらえるはずなんですよ。
「リアルは重要な場である」という認識は残しておかないと、と思っていて。
枌谷:
そうですね。うちの会社の場合、仕事の8~9割はリモートでいいのですが、いざというとき「これはリアル」と使い分けられるか。
私、資本提携したクラスメソッドさんにCDOとして参加して、デザイン組織を作っているのですが、彼らってほぼ完全なリモートワーク文化なんですよね。だけど、現在のデザインチームのマネージャーとは、2時間ほどリアルでじっくりお話しする場を設けました。
その前に、オンラインでも1時間ほど話はしていたのですが、リアルで話した2時間の方が明らかに、心理的な繋がりが強くなった実感があります。
いいたか:
間違いないですよね。
枌谷:
ああいう実感は、オンラインではなかなか得にくいですよね。

SNSでの存在感は、レバレッジが利く
いいたか:
澤山さんは入社して、何カ月メンバーに会ってなかったんですか?
澤山:
4カ月ぐらいですかね。入社前に、少し会う機会はありましたけど。
いいたか:
そうか、たまたま緊急事態宣言が明けたタイミングで会ってましたね。
枌谷:
当時、薄々「ホットリンクさんに入るんじゃないか?」とは思ってました(笑)。
澤山:
一本釣りされました(笑)。でもいいたかさんに誘われる形じゃなかったら、入社直後の3カ月はもっとしんどかったと思います。誰が誰だかわからないし、一緒に飲んだこともないし。
枌谷:
でも、ソーシャルメディアで一定の認知があったことは大きいんじゃないですか? 社内のメンバーが、一定澤山さんを認知しているというか。
いいたか:
そうですねー、そこは大きいと思いましたね。
枌谷:
リモートワークが一般化した時代だと、キャリアチェンジしてジョインした後に、新しい会社の社員となじむ機会がすぐに訪れない可能性が高いですよね。
そういう時、ソーシャルなりで一定の評価を確立して知名度があったりすると、組織への入り方がよりスムーズになったりとか、そういう効果がありそうですよね。
澤山:
それは感じます。フォロワー数云々とか(仕事の)レベル感というより、カルチャーフィットするか否かはジャッジしやすいのかなと。

枌谷:
僕も同じことを、クラスメソッドさんに入ったときに感じたんです。クラスメソッドさんはエンジニア文化なので、私のようなデザイン系の人物への関心は基本的に高くないはずだと思うのですが、それでもSlackで何かを伝えた時の反応がとてもいいんですよね。
やっぱり「SNSで知ってるあの人だ」というのは、大きかった気がします。
いいたか:
確かにそれはあるだろうなあ。ウチもいろんな社員入ってきてますけど、例えば澤山さんなら「記事書いて」「コンテンツ出して」ってなりますよね。
枌谷:
深いところの自己紹介ができている状態で入れるのは、大きいですね。そのことが、リモートワークだと余計にレバレッジが利く気がします。

別に、お酒で案件が取れていたわけじゃなかった。
いいたか:
僕個人でいうと、お酒の席でお客様になるケースが多かったんですよ。もしかしたら、コロナのせいで自分の良さが消えるんじゃないかって不安はめっちゃあったんです。
でも、結果そんなことはなかった。単にお酒が好きで仕事の話もしただけというか(笑)。
枌谷:
はい、はい。
いいたか:
オンラインで話しても、ちゃんと案件化されたんです。「お酒で案件化している」は錯覚に過ぎなかった。だったら、空いた時間は走ったりドライブしたり海に行けばいいじゃん、となって鎌倉へ移住しました(笑)。
枌谷:
ありますよね、「ないと成り立たない」と思ってたものが、リモートによって意外とそうじゃなかったと気づく。
いいたか:
逆説的に、お酒の時間をもっと大事にするようになりました。だらだら話すのでなく、ちゃんと意味のある話もしたいなって。昨日も、どれだけぶりかわからないけど、みる兄さんや扇英資さんと飲みました。
枌谷:
オフィスの使い分けと同じですよね、飲み会もむやみにやるのでなく、本当に意味のあるときだけ開催するというか。
それでいうと、課題感もありますね。いま、社内打ち合わせがすごく増えたんですよ。移動がなくなったので。
いいたか:
気づいたら「え、この日やばいな。何件打ち合わせしてるんだ」って日ありますね。
枌谷:
マネージャーはいよいよ、「喋れる人」じゃないと務まらなくなりますね。ほとんどデスクワークがなくなって、喋ってるだけという日があったりするので。
いいたか:
背中で示す、みたいのは難しいですよね。
枌谷:
「言葉足らずだけど、いい人だから支えてあげよう」みたいのが成り立ちにくい。
いいたか:
めちゃくちゃ喋る人や、無駄話が好きな人のほうが有利ですね。用件だけ話す人だと、オンラインではキツいですね。

コロナ時代のコミュニケーション「だけ」では、苦労する。
澤山:
伺っていると、やっぱり「リモートだけ」「リアルだけ」という振り切り方は難しい気がしますね。
コミュニケーションにおいて、リモート/リアルでカバーできる範囲は決まっている気がします。すごく重い内容・すごく軽い内容、どちらもリモートには意外と向いていないというか。
枌谷:
リモートではカバーできない、感情の空白地帯みたいなものはありますね。
澤山:
会社組織で一番重い話でいうと「退職」だったりしますが、迷ってどちらを選択すればってなったときにリモートではやっぱり相談しにくくて。
枌谷:
ありますね。社員から転職や退職になりかねない相談を持ち掛けられたら、やっぱり僕はできるだけリアルで話しますね。リモートだけで済まそうとは思わない。
いいたか:
そうですよねー。
枌谷:
相手の考えや思いを受け止めた上で、こちらも重たい話をせねばならない。そういうケースでは、リモートでは無理とは言わないけど、少なくとも自分は自信がないですね。使い分けが必要で、オフィスがない会社はオフィスがないなりのハンディは生まれると思うんです。
いいたか:
前提として会社のステージによると思いますけど、オフィスを思い切って無くしちゃった会社で、大変になってるところってあるんじゃないかな? と思って見てますね。僕が古い人間なのかもしれませんけど。

澤山:
でも本当に、そういう部分はありますよね。単純にリモートとリアルという二項対立ではない。「オフィスは不要」というのは、コミュニケーションの浅いところしか見ていない危険を感じます。
枌谷:
そうは言っても世の中、30代以上の「コロナ以前」におけるオフィス中心のコミュニケーションで実績を積んできた人がマネジメントしているわけです。コロナ時代のコミュニケーション様式「しか」できないと、今後苦労する局面は出てくるかもしれませんね。
いいたか:
それでいうと、去年と今年入社した若い子たちは本当に優秀ですよ。あと、すごく素直。僕の若い頃なんて、上司に理不尽なこと言われたら「そんなもんおめえがやれよ」ぐらい返してたから(笑)。
澤山:
やんちゃすぎます(笑)。
いいたか:
でも、素直すぎる部分も感じるかな。もっと冒険してもいいなと思うところもあります。
枌谷:
自分も若い頃そうでしたが、実は若くて経験がない方が、保守的になってしまう側面はありますよね。先が読めなくて怖い。それが色々と経験を積むと、怖さを克服できるようになる、みたいな。

編集後記:澤山モッツァレラ
リモートワークか、出社か。どういったスタイルをどの割合で選ぶかは、冒頭で枌谷さんが述べられた通り「元々の文化と仕事のスタイルによる」と思います。
ただし、リモートだけでなくコミュニケーション全般において「細かな機微」は必要でしょう。どちらが優位といった話でなく、「適切な形式を選べるか否か」「繊細なコミュニケーションを取れるか否か」という点でお二方の意見は一致しています。
そうした部分を学びとして受け取ることが、今後の組織運営のキーになるのかなと思いました。
次号は、トライバルメディアハウス代表取締役・池田紀行さんに登場いただきます。公開は11月22日の週を予定しています、どうぞお楽しみに!
今回の「ザ・プロフェッショナル」もお楽しみいただけましたか? 本シリーズでは、今後も各業界で活躍するさまざまなプロフェッショナルをお招きして対談を行ないます。過去の記事はこちらからご覧ください。