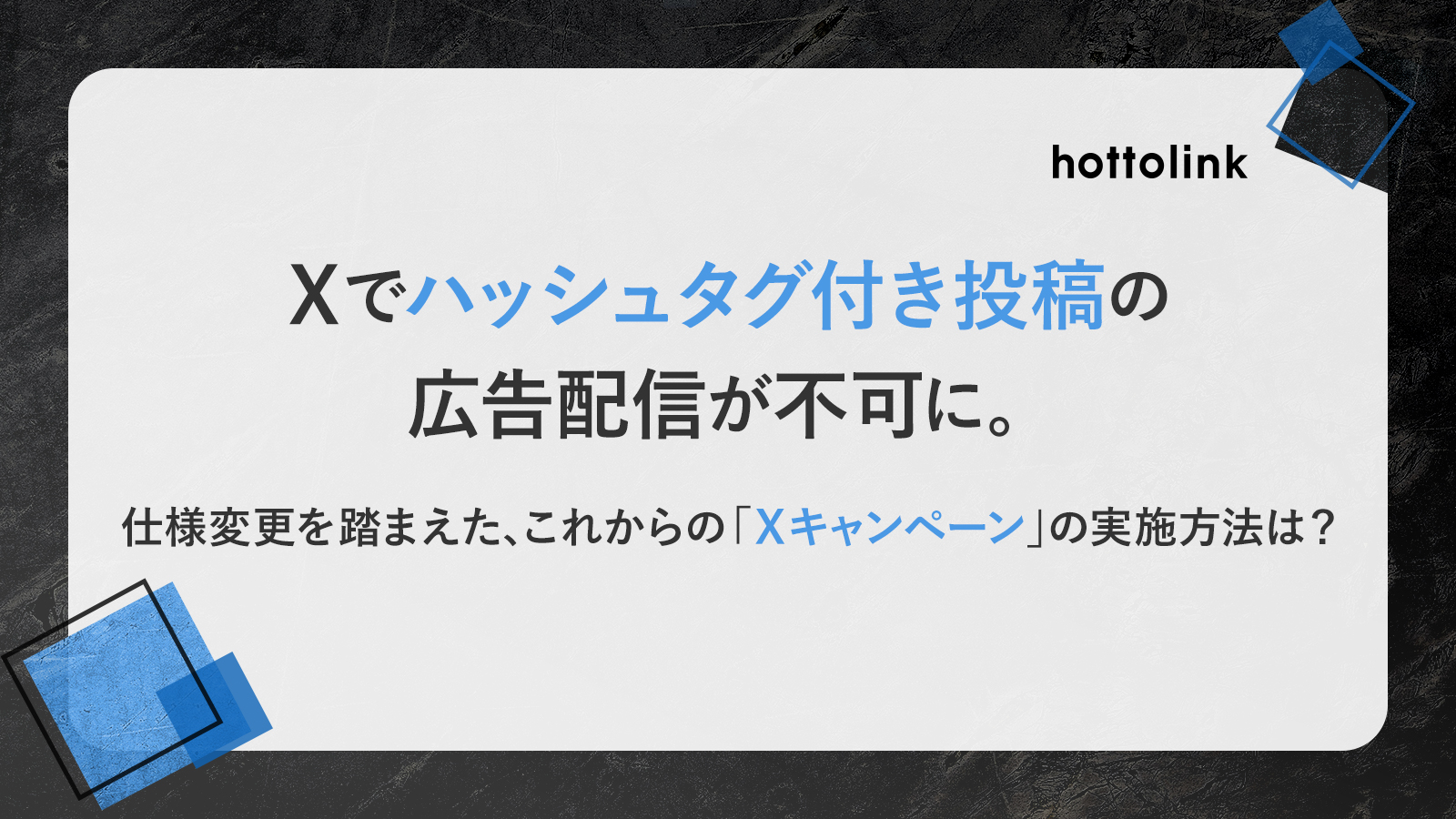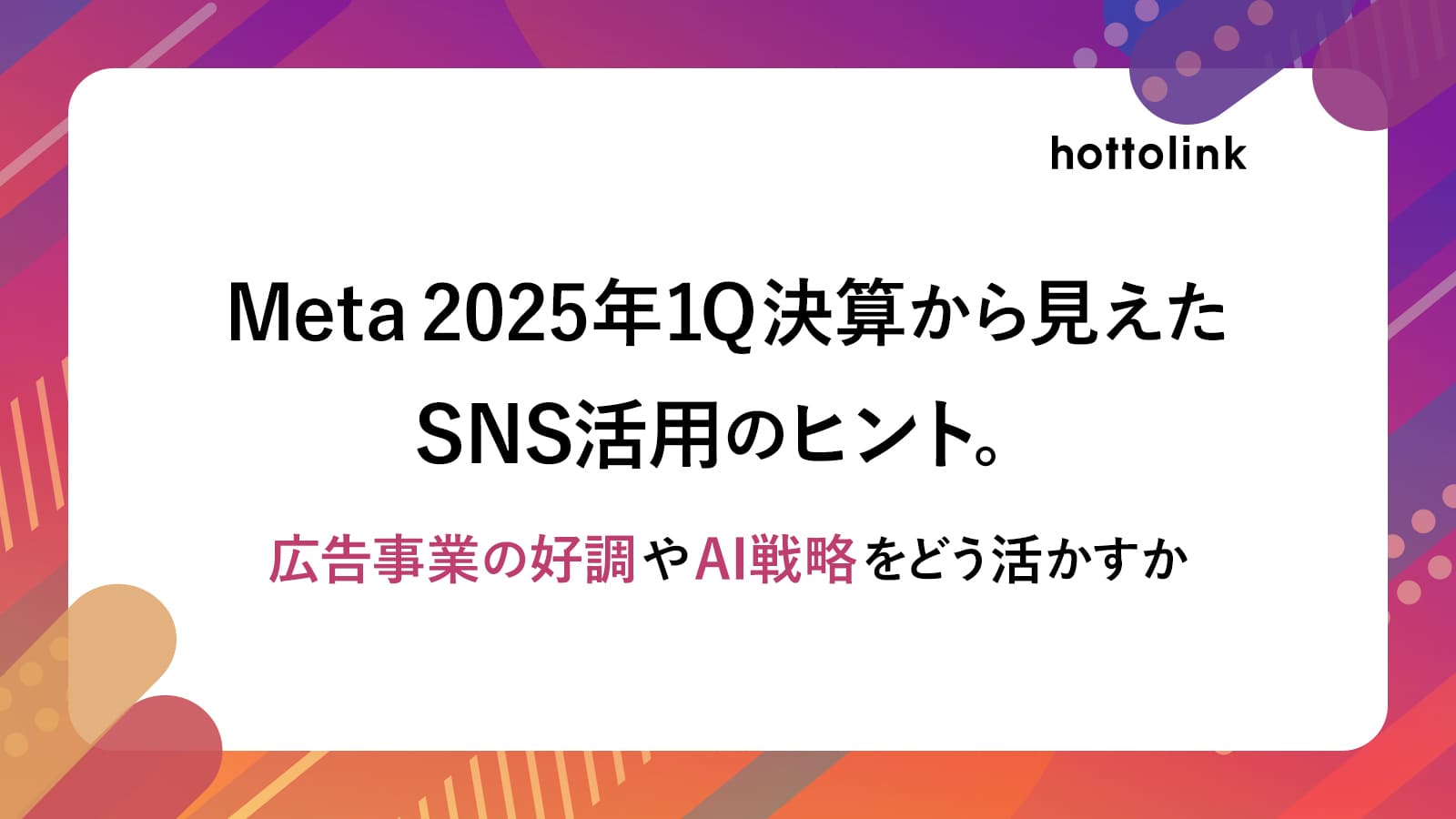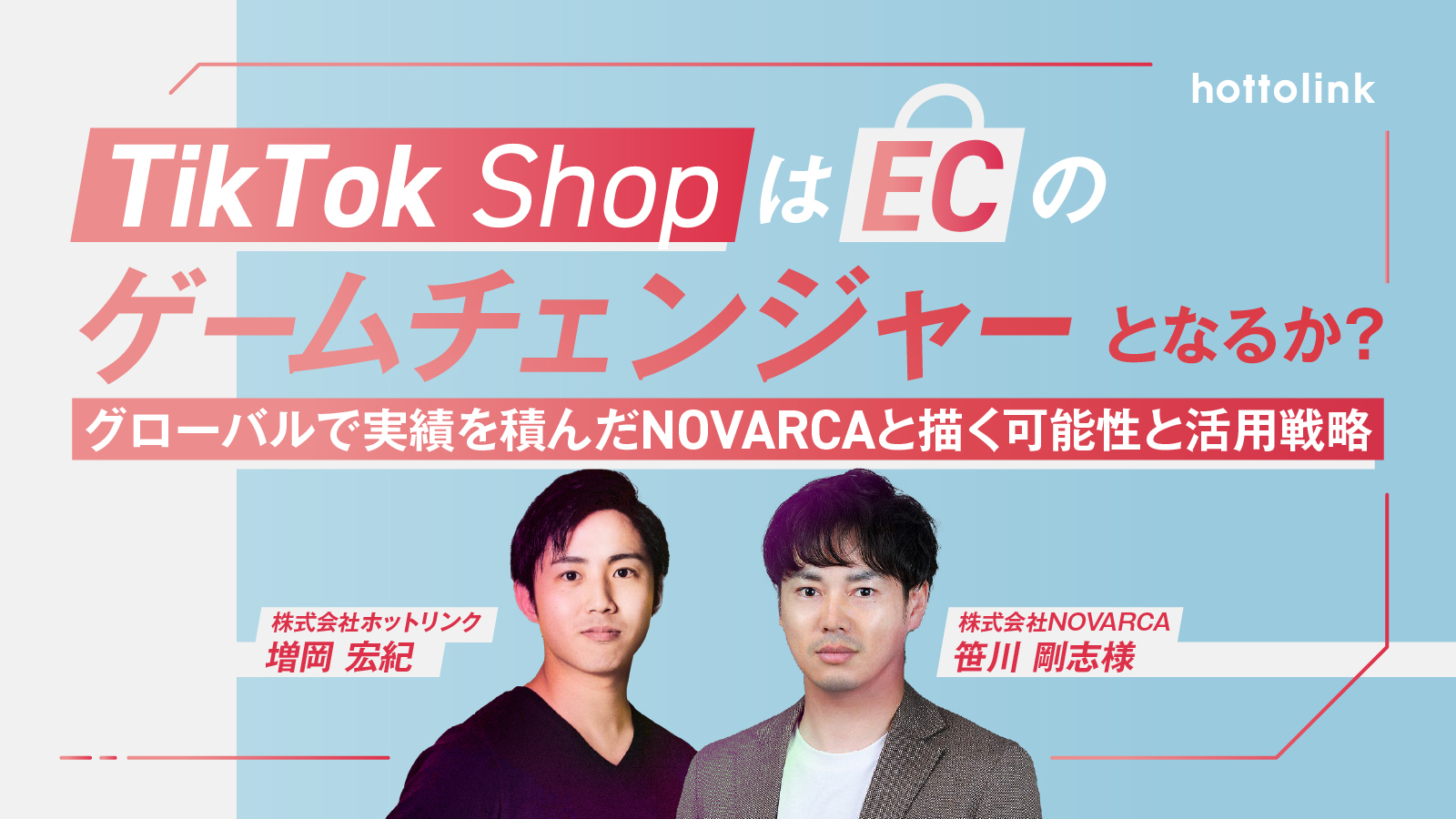ホットリンクCMO・いいたかゆうたが現場のスペシャリストとともに、激変する社会におけるメディアの未来を語り合う新連載『ザ・メディアエイジ』。第2回のゲストは朝日新聞デジタル編集長の伊藤大地さんです。
2021年5月18日に、創刊10周年を迎えた朝日新聞デジタル。そしてこの10年で、「情報」を取り巻く環境は激変しました。あらゆるユーザーが情報発信できる現代、長年報道を支え続けてきたオールドメディアは改めてその真価を問われています。
数々のデジタルメディアを経て、大手新聞社のデジタル領域を任された伊藤さんに、ネット時代における報道の価値について聞きました。(執筆:サトートモロー 撮影:保田太陽 編集:澤山モッツァレラ)
|
伊藤大地(いとう・だいち):
朝日新聞デジタル編集長。インターネットメディア協会理事。2013年にザ・ハフィントン・ポスト・ジャパンに参画。2015年にBuzzFeed Japanに入社し、2019年にオリジナル編集長に就任。2020年9月の退任後、同年11月に朝日新聞社へ入社。2021年春より朝日新聞デジタルの編集長に就任。
|
※編集部注:被写体には、写真撮影時のみマスクを外してもらっています。インタビューはマスク着用のほか、感染症対策を施してから行なっています。

大手新聞社のデジタル化を、さらに加速させる
いいたか:
伊藤さんは、現在どのような業務に関わっているんですか?
伊藤:
今年の春に朝日新聞デジタル編集長を拝命し、現在は会社全体のDXに取り組んでいます。
新聞社にとって、あらゆるコンテンツの前提は「紙媒体に掲載すること」でした。そこで生まれた記事を、どうデジタルに活かすか。つまり、デジタル側が紙媒体のコンテンツを二次利用する世界だったんですよね。それを、紙からデジタルまでワンストップで制作できる仕組みを作ろうと動いています。
ここでもっとも重要な問題が「時間」です。要は従業員の働く時間、コアタイムが激変するんですね。
従来は夕刊の締め切りが午前11時で、朝刊の締め切りは深夜0〜1時頃。記者も含め、新聞社全体がこれをベースに動いていました。しかし、デジタル側からすると夕方にその日のニュースが出ても困ってしまいます。
結果として、記事制作全体の動きを前倒しする必要がありました。僕たちにとっては当たり前の話ですが、新聞社にとってはすごく大きなトランスフォーメーションでしたね。
具体的には、午前11時頃から編集会議を行ない、その日にどんなネタがあり、それをどう組み立てていつ出すかを話し合っています。
僕のもうひとつの仕事は、中長期的な会社の方向性を考えることです。とはいえ、朝日新聞は4000人の社員がいるので、僕だけが「やる」と言っても話は進みません。社内官僚のように根回しをしつつ、調整をしています(笑)。
いいたか:
朝日新聞は、ここ数年デジタルに力を入れている感じがします。それでも、まだ変革すべきことは多いですか?
伊藤:
先駆的にやっていたデジタルの取り組みを、さらに加速させなくてはいけないと思いますね。
一方で、新聞社の強みというのは、現場から事実を報じることができるという、ごく当たり前のところにあります。この当たり前を、デジタルでもちゃんとできるかが非常に重要です。僕が新聞社で働くことにしたのも、そういう環境を維持したいという思いが強かったからです。
仮に新聞社がなくなったとして、Yahoo!やGoogle、Appleといったプラットフォーマーが、その代わりをすることはないでしょう。現場に記者がいる、地方に海外に記者がいる。この状況をいかに維持できるかが、マスメディアにとって非常に重要なことだと思います。

マスメディアとSNSの関わり方
いいたか:
この1年間は新型コロナウイルスの影響もあり、メディア業界にとっても大きな変革期だったのではないでしょうか。なにか印象に残っていることはありますか?
伊藤:
僕が新卒の頃に思い描いていたインターネットとは、やっぱり違うなと思います。誰もが発信できることのいい面・悪い面が、スマホとSNSの登場で極まっているのが現在だなと。
いいたか:
具体的にどんないい面・悪い面があると思いますか?
伊藤:
デジタルのいい面は、プロの意見も素人の意見もフラットに流れていくことでしょうか。フラットだからこそ、プロの目線では絶対に気づけない意見が出てくるというか。悪い面は、フラットゆえに本来慎重に扱わなきゃいけない情報が、間違った形で世に出ることです。
いいたか:
まさに表裏一体という感じですね。
伊藤:
かつてテレビ局や新聞社は、配信するチャネルを数社で寡占していました。その構造が崩れても、プロフェッショナルが手放してはいけないものとはなにか、僕たち報道は問い直されている気がします。
例えば、インターネットはいい意味でアマチュアリズムが強いじゃないですか。YouTubeでも、料理など趣味性のジャンルに特化した、専門チャンネルが人気です。その裏で、公共性の高い情報は一般の方は取り扱いません。だからこそ、僕たちがここをカバーしていかなくてはなりません。
いいたか:
今後、朝日新聞デジタルとしてソーシャルメディアとどう向き合っていきたいですか?
伊藤:
僕は、もっと記者が前に出てきてほしいですね。スーパーの有機野菜を見ると、「〇〇さんが作りました」と写真付きで出ているじゃないですか。作っている人とその過程が見えるのは、信頼につながると思うんです。
現在のメディア不信を乗り越えていくためにも、これは必要なことなのかなと考えています。「作り手は黒子であるべき」という、従来からのメディア特有の考え方も強固に存在するので、そこも変わっていくべきなんじゃないかな。
ただ、これは「ネット上で目立ってほしい」という意味ではありません。自分の記事に関する編集後記を投稿するとか、それだけでいいんです。
いいたか:
「目立たなくていい」って言葉は、すごくわかる気がします。
スマートフォン、SNSが普及して、ユーザーリテラシーが強く求められるようになりました。記者の皆さんが、編集後記のような良質なコンテンツを流してくれると、自然とリテラシーが上がると思います。
ちなみに、伊藤さん自身はSNSをどう使っていますか?
伊藤:
僕は、毎日「日々実験」のように使っています。自社の記事を紹介するにしても、見出しだけでいいのか、自分がコメントを加えたほうがいいのか考えたり。
公式アカウントは100万フォロワー以上いるので、ちょっと実験しづらいです(笑)。
ちなみに、僕は自分のタイムラインをほとんど見ていません。その代わり、ある程度ランダムにピックアップしたアカウントを、リストにしてチェックしています。
業界外でなにが話題になっているのかは、常に見ています。あとはトレンドになっているワードで、知らないことはめっちゃ調べますね。
いいたか:
業界外の人でリストを作るのは、私もやっています。自分の業界だけを見ていると「これが正しい」と思うんですけど、一歩外に出るとまったくその話題が語られていない。こういうことがよくあるんですよね。
伊藤:
新聞業界もまさにそうです。社内では当たり前すぎて議論にすらならない話題も、世間ではそう思わない人もいる。ここにすごく大きな落差があります。今まで、この業界はあまりにもこの違いを伝えてこなかったなという意識を、強く感じています。
いいたか:
ソーシャルメディアが生まれたことで、マスメディアがコンテンツを作ってきた時代から、ユーザーからウェブコンテンツが生まれる流れができています。この変化は、メディアにどんな影響を与えているんでしょうか?
伊藤:
そうですね。そうした変化の影響は受けつつも、僕たちがすべきなのは中長期のトレンドを読んでいくことだと思います。
「ネットではこれが流行っているから」と動いても、記事ができる頃にはとっくに乗り遅れているんですよね。だからといって、インターネットの流行に飛びついて、スピードで勝負しても絶対に勝てません。
インターネットが起点となって、人や社会が変化する先をどう捉えるか。「今これが流行っています」ではなく、「これが流行っているなら、次はこうなるだろう」を記事にすることが、もっとも重要だと思います。

伊藤「報道は、必須栄養素だと思うんです」
いいたか:
インターネットがこれだけ大きな産業になっているなか、改めてマスメディアの使命はどこにあると思いますか?
伊藤:
デジタルでも紙でも、価値判断がもっとも重いテーマです。限られた取材リソースをどこに置くべきか、必ず判断が求められます。ある意味で、アジェンダ設定力が大事と言いますか。
なぜこの記事が一面に掲載されているのか、朝日新聞デジタルのトップはなぜこの記事なのか。その理由こそ、「私たちはこれが大切なアジェンダだと思っているからです」という思いにほかなりません。
報道機関が、なぜ一般の立ち入りが制限された場所に入れるのか。これは、突き詰めれば公共性と結論付けられます。公共性を持っているからこそ、許されていることもたくさんあるわけです。だからこそ、そこには社会的責任がセットになっていると思います。
いいたか:
自分たちの意義がなにかということですね。10年後、メディアはどうなっていると思いますか?
伊藤:
閲覧デバイスはどんどん変わるでしょう。ただ僕は、変わるものより変わらないものを考えるほうがいいと思っています。変わるものは予想できないからです。子どもの頃に読んだ未来予想の本は、驚くほど間違えているじゃないですか。今の技術観、価値観で、未来を予測するからです。
世の中は、技術とそれを受容する人間によって変化していきます。僕が大事にしたいのは、10年後も変わらない、「変わらないもの」「変わってほしくないもの」です。
例えばZoomなどのオンライン会議ツールがもっともっと普及しても、官邸取材や特派員といった、現場で政治家に対して行なう取材には代替できないと思います。
10年後も、世界各地や日本全国に、記者がいてほしい。だからこそ、その環境を維持できるビジネスをしていくことが重要だと考えています。
いいたか:
「変わらないものを考える」っていいですね。一般ユーザーとしての目線で、変わらないことはなんだと思いますか?
伊藤:
生きていく上で必要なものであり続けること、ですかね。食べ物と一緒かなと。
必須栄養素ってあるじゃないですか。報道は、それに近いものだと思います。同時に、エンターテインメントも、人生を豊かにしてくれます。今後も、オーディエンスはエンターテインメントを必要するだろうし、ニュースが不要になる時代も来ないんじゃないかなと。
ただ、摂取の仕方は変わるでしょうね。それがYouTubeなのか、VRかはわかりませんが。
いいたか:
栄養素って話はわかりやすいですね。
今後、さらにデバイスもプラットフォームも増えて、それぞれの使い方をユーザーが勝手に選びはじめていくでしょう。そのなかで、朝日新聞デジタルはユーザーにとって非常に大切な栄養素を届き続けることに、価値を感じるということでしょうか?
伊藤:
そうです。「僕たちは社会にとって絶対に必要なことをしている」という認識だけは、ブレてはいけないと思います。ここがブレてPVを稼げるゴシップばかり報じだしたら、この会社が存在する意味はありませんから。

言論のグラデーションをどう線引きするか
いいたか:
私は、ソーシャルメディアにはフェイクニュースが出回り、ユーザーリテラシーもまだまだ低い一方で、リアルな情報が取得できるというポジティブな面もあると思っています。
この環境はより健全化していくべきですが、メディアの立場としてどのような要素が入ると、ソーシャルメディアで正しい情報を正しく届けられると思いますか?
伊藤:
いい情報か悪い情報かを見分けるのは誰か、という難しい問題がありますよね。倫理の枠組みをどう設定するのか。それを担うのは、おそらく法規制ではないはずです。もちろん、直接的に社会に害悪な行為を行なえば、法に触れるでしょうが。少なくとも自由主義国家において、言論規制は一番あってはなりません。
ウソも野放しにするのか、ガチガチに法規制するのか。このなかで、どういうグラデーションを選択するのかが重要だと思います。
たとえば、ドイツは言論に関して「嘘をついていい言論の自由はない」という立場です。憲法上でも、民主主義を否定する自由・権利は認められていません。一方で、アメリカは「情報が嘘かを判断するのは難しいから、基本なんでもあり」としています。この姿勢の違いは、今年1月に、アメリカの国会議事堂が群衆に襲撃された際の指導者のコメントにも、はっきり現れています。
対立する価値観の白から黒までグラデーションがあるなかで、自分たちはどんな社会で生きたいか。あいまいな枠組みのなかで、「こういう線であるべきだよね」という考えを発信していくことが、メディアが自らやるべきことだと思います。
いいたか:
ここまでの話を踏まえて、伊藤さんが朝日新聞デジタルの編集長に抜擢されたのは、どのあたりに理由があると思いますか?
伊藤:
変革のスピードを上げるためじゃないでしょうか。僕は明らかによそ者なので(笑)。
それでも、社内のメンバーと基本的な価値観は共有していると思います。10、20年後に紙が、デジタルがどうなっていようと「その時に僕たちがしなきゃいけないことは変わらないよね」ということは、ずっと言い続けています。
問題は、それをどう実行するか、ですね。今までやってきた方法を変える必要がある一方で、報道で社会に貢献する、という点は変わるべきではないですから。
非常に難しいことですが、本当に大事なことを残すために「それ、いらなくないですか?」って言うのが、僕の仕事の究極だと思います。
いいたか:
今回はお忙しい中、ありがとうございました!