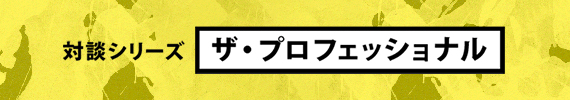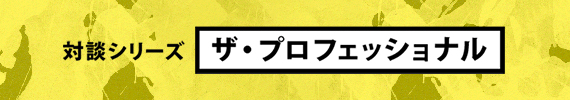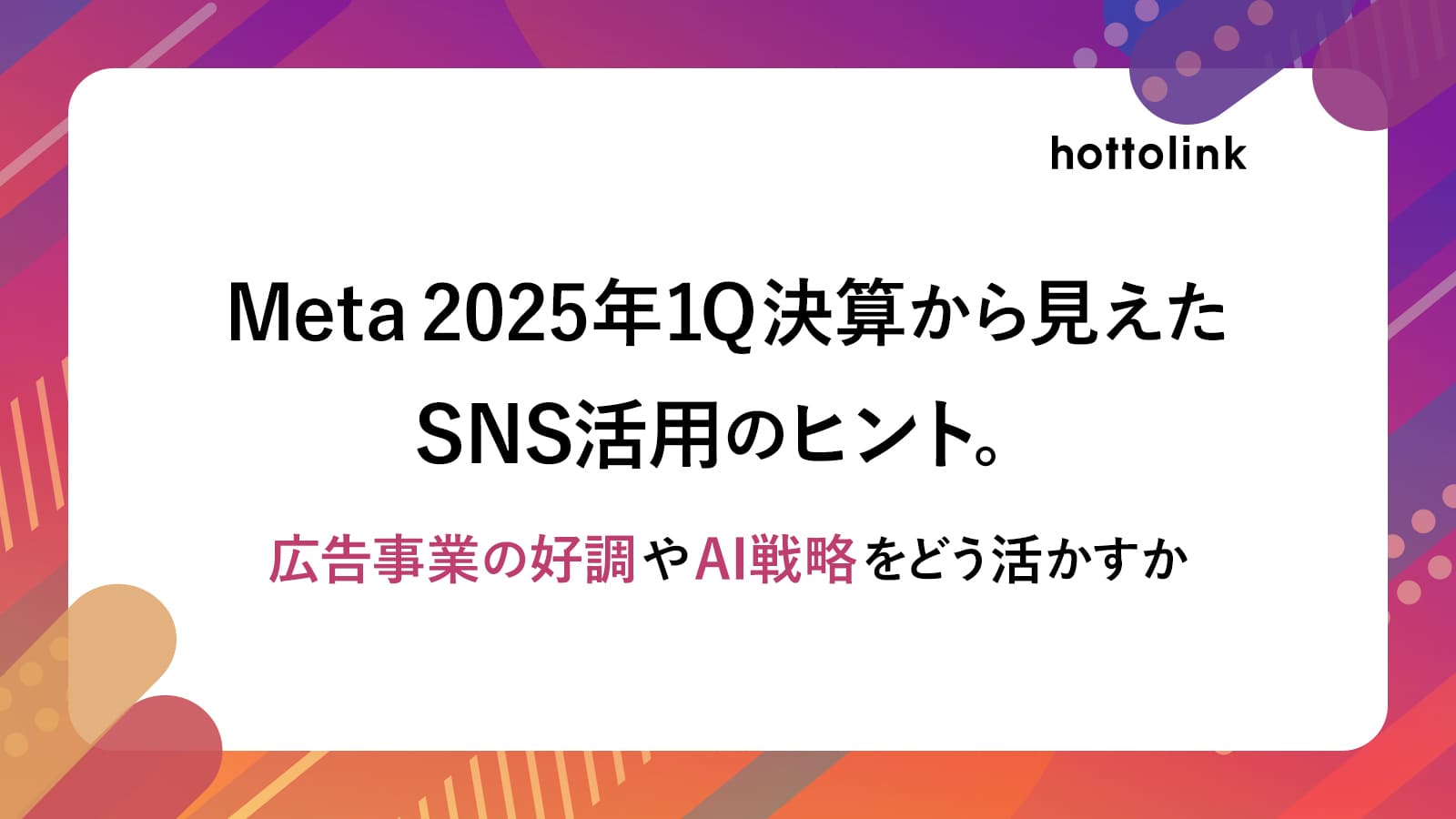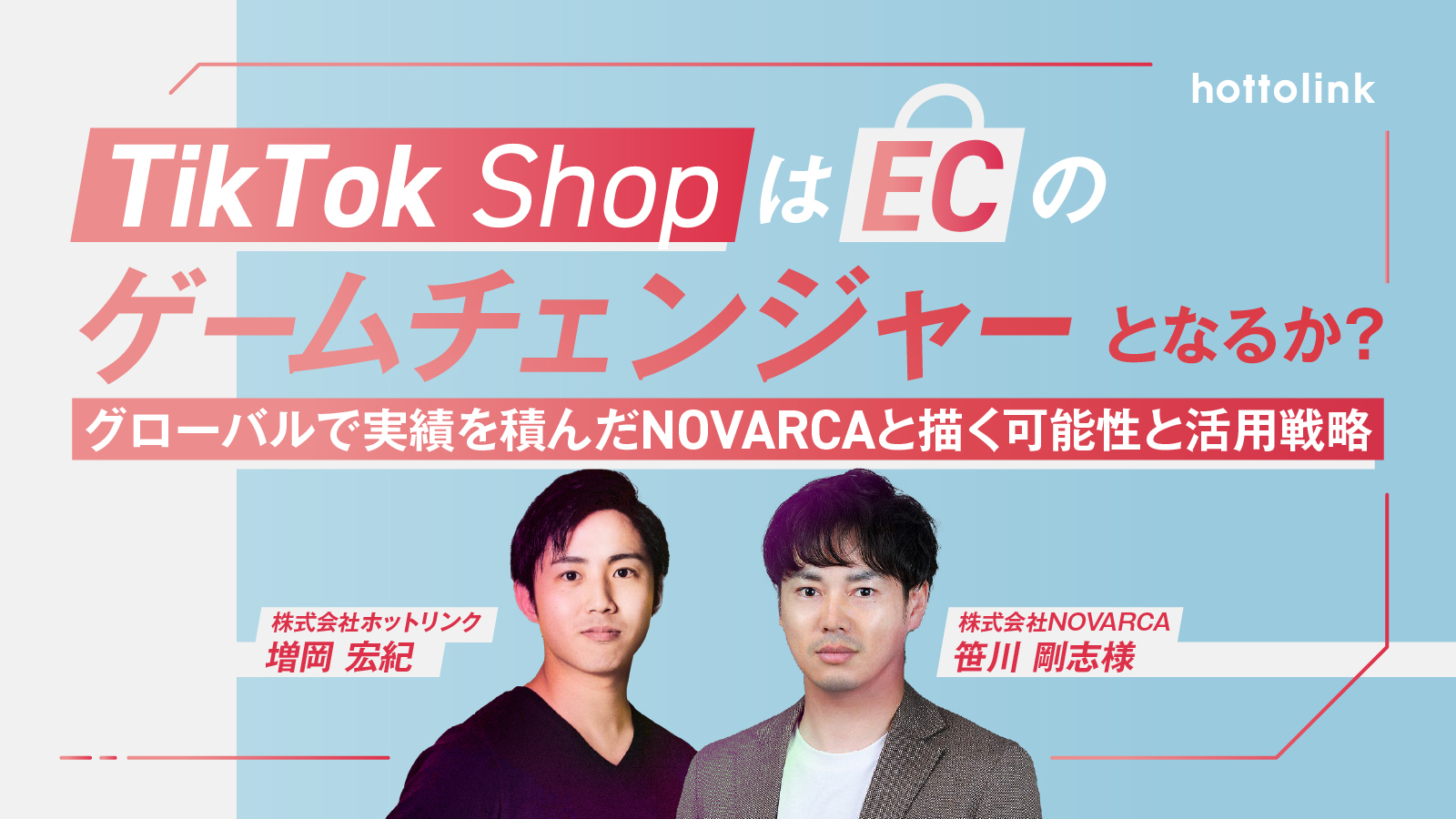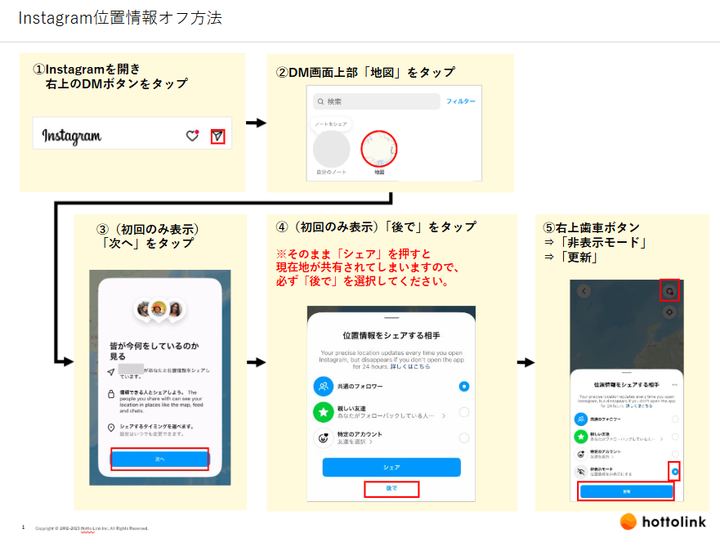各業界で活躍するさまざまなプロフェッショナルとホットリンクCMO・いいたかゆうたが、SNSやマーケティング、ビジネスのあり方について考える対談シリーズ「ザ・プロフェッショナル」。
今回のゲストは、小説家・ライターのカツセマサヒコさんです。数々のバズるコンテンツを世に送り出し、Twitterでは「妄想ツイート」で話題になったカツセさん。昨年は小説家としてデビューし、活躍の場を広げています。
いいたかと同じく、1986年生まれの「86世代(ハチロク世代)」の1人として、SNS黎明期を経験してきたカツセさん。現在20代で、黎明期を知らないライター・「私がエレン」も参加し、SNSの思い出やカツセさんが今後やりたいことを聞きました。
※編集部注:被写体はすべてマスクを外していますが、周囲に人がいないことを確認して撮影時のみ外しています。インタビューはすべてマスク着用で行なっています。

カツセマサヒコ。1986年東京生まれ。大学を卒業後、2009年より一般企業に勤務。ブログをきっかけに編集プロダクションへ転職し、2017年4月に独立。2020年6月に『明け方の若者たち』(幻冬舎)で小説家デビュー。同作は実写映画化も決定している。2021年7月2日には、バンドindigo la Endとのコラボ小説『夜行秘密』が発売予定。
SNS黎明期を生きた86世代の「あの頃のぼくら」
カツセ:
いいたかさんと2人できちんと話すのって、実ははじめて?
いいたか:
いわゆる「86世代」の業界人が集まる飲み会では、結構しゃべってたよね(笑)。この世代ってライター、編集者がすごく多くてさ。朽木誠一郎さんやg.O.R.iさん、長谷川賢人さんとか。
私がエレン:
その飲み会が、2人にとっての最初の出会いですか?
いいたか:
ううん。確か僕がマーケメディアの「ferret」を立ち上げたとき、一緒に案件をやることがあってそのときに、ちらっと挨拶したと思う。
カツセ:
そうそう。それくらいだよね。
いいたか:
ただTwitterでは、それ以前から知っていたかな。
カツセ:
うん。最近も会ってなかったけれど、お互いの進捗はTwitterで見ているから、あまり久しぶりな感じはしないなあ。
いいたか:
86世代の飲み会も、いまではあまり集まらなくなったしね。最後の飲み会は5年くらい前じゃないかな?
カツセ:
もうそんなに前なんだ……。当時は「上の世代に負けないように頑張ろう」って集まっていたよね。そう言ってた僕たちが、どんどん上の世代になってきちゃったけれど。
いいたか:
当時は20代後半だったね。僕が2014年に「ferret」を立ち上げて、朽木さんが2015年くらいに編集長になってさ。そのときに、「86世代編集長対談」って企画をやったの。
カツセ:
「まだ立ち上げたばっかなのに、早すぎない!?」っていまなら思うよね(笑)。

いいたか:
ただの小僧だった2人がメディアを語るなんてさ。思い返すと超怖いよ(笑)。
カツセ:
でも、当時はそういうのが当たり前だった。僕もまだライターになって1年経ったばかりなのに、イベントに登壇しまくっていたもの。あと、当時はプロフィールに「86世代」って書くのが流行っていた。
いいたか:
同世代だけだよね、そんなことしてたの。
カツセ:
思い返すと、恥ずかしいなあ(笑)。86年に生まれたことを、勝手に誇っていたんだよね。
ライター・カツセマサヒコが生まれた背景
私がエレン:
カツセさんがTwitterでつぶやきはじめたのは、26歳の頃ですよね。当時は通勤電車の悪口を言い続けていて、フォロワーもまだ300人程度だったとか。
カツセ:
確か最初は匿名アカウントだったんですよ。ライターに転職した2014年頃から「カツセマサヒコ」にして、本格的にTwitterを使い始めました。
いいたか:
最初につながった時点では、僕はフォロワーが2,000くらいで、カツセさんはまだ1,000くらいだったと思う。
カツセ:
転職直後は全然フォロワーはいなかったよ。2015年の半ばから「カツセマサヒコ」のバイネームで仕事が来るようになって、そこでフォロワーが1万を超えたと思う。
いまでも覚えているんだけど、28歳か29歳のとき、当時所属していた編集プロダクションのプレスラボのメンバーが、誕生日会をやってくれたんですよ。そうしたら、ケーキプレートに当時のフォロワー数が書いてあった(笑)。すごい文化だよね(笑)。
いいたか:
あの頃は、「ライターになるならフォロワーいなきゃダメ」みたいな風潮があったんだよね。ちょうど塩谷舞さんが露出しはじめたくらいかな?
カツセ:
塩谷さんがフリーになるあたりだね。彼女に続いて、僕もフリーになって。
いいたか:
カツセさんはなんでライターになろうと思ったの?

カツセ:
もともと、僕は大企業のサラリーマンをやっててさ。それこそ満員電車への不満とかをつぶやいていたんだけど、Twitterをのぞくと、面白いと感じる人にライターが多かったんだよね。サカイエヒタさんやヨッピーさんがすごく目立っていて。彼らのマネをしようと思って、週末にブログを更新していた。
そうしたら、2014年にプレスラボから「採用試験を受けない?」って声をかけられて。ライター試験を受けたら、受かっちゃったんだよね。
私がエレン:
サラリーマン時代に書いたブログって、どういうテーマだったんですか?
カツセ:
毎回違いましたよ。おもしろ系をやった翌日に、政治の話をして、その翌日は『ドラえもん』の予告編について書いて、別の日は『笑っていいとも』の感想を書いて……。
Twitterで見ていたライターさんの記事を見ると、あまり自分のことは書かないって気づきました。それまで、ブログは日記を書くイメージだった。しかし彼らは、読者がどこかにいて、その人たちが面白いと感じそうなものを書いている。自分も同じことをしようと思ったんですね。
すると、たまたま職業論のテーマがバズって。当時のフォロワーは700人前後だったけど、2万PVとかいきました。自分のなかではお祭り騒ぎですよね。「やったー!」って。そのタイミングでプレスラボに声をかけられたんだけど、実は妻に黙って入社試験を受けました。
一同:(笑)。
カツセ:
だって、絶対落ちると思うじゃないですか! そもそも未経験だし。
そうしたら、受かっちゃって……。 上場企業の社員から、従業員たった6人の会社にいく。しかも社長は、当時37歳だよ。内定後に妻と話したけど、ずっとけんかで平行線だった。最終的に、許しを得ずに転職したんだよね。「結果出すから!」って言って。
いいたか:
それがなかったら、いまのカツセさんはいなかったものね。いい決断だと思う。
カツセ:
いろいろひどい判断もしてきたけれど、あのときの自分だけはホメたいなと思う(笑)。

前線で戦う人。組織を作る人。「86世代」の分かれ道
いいたか:
地に足がついたと感じたタイミングってある? ずっとふわふわしていたけれど、「ここでなら生きていけるな」という実感というか。
カツセ:
そんなの一度もない(笑)。
いいたかさんはちゃんとナレッジを蓄積して、年齢重ねても問題なくやっていけそうな道を作っていったじゃない? 僕なんて、ずっとふわふわしているから……(笑)。バズることだけ考えてたと思ったら、今度は小説なんて書いてさ。だからいまでも不安。
もともと飽き性だからずっと同じことはできないし、40歳になってからもバズ記事でホームランを連発するのは、体力的にも無理だと分かっていた。
違う道を探さなきゃいけないっていうあせりは、30歳までずっと抱えていた気がする。だから書籍を出せたことで、ひとつ「延命措置」ができたと思えたなあ。
いいたか:
書籍を出したきっかけってなに?
カツセ:
2017年頃から、フォロワー数の多い人が本を出すブームがあったじゃない? 僕にもエッセイを出さないかってオファーがあったんだけど、書籍を出したのに自分の人生が変わらないのは、いやだなと思ったんだよね。
ちゃんと箔がつくもの、名刺になる1冊を作りたいと思って、グッと待った。もともと本を出すならエッセイじゃなく、小説を書きたいとも思っていたしね。
そのなかで、幻冬舎が声をかけてくれて。以来2年半くらい、ずっと耐えて書きあげました。
Twitterの使い方も、出版の1年前から徐々に「いいね!」集めはやめるようにシフトし始めて。書籍が発売された2020年の6月11日以降は、いわゆる「妄想ツイート」はすべてやめて、小説家として不自然に見えないように切り替えていきました。
私がエレン:
作家然としたTwitterってどんなものですか?
カツセ:
小説で食っている人は、わざわざ140文字でバズろうとはしないでしょう? SNSでバズっても意味がないと分かっているので、そういう努力をするのはやめました。1年間かけて、いいね数で一喜一憂しないようにしました(笑)。
僕がTwitterのフォロワーを増やしていたのは、当初ライター・編集者にとってフォロワー数(=拡散力)が重要だと思っていたから。書籍を出すときも、広告として自分から発信できるようにしたかったですし。でもいま、本が出たことで使い道がなくなってしまった。これからどうしようかなと、考えているところです。
いいたか:
カツセさんが伸びているのを見て、「僕らはカツセさんみたいになれないね」って話してて。じゃあ、バリューを出すにはどうすればいいだろうって議論をめちゃくちゃしてた。そこで行き着いたのが、自分のナレッジを多くの人に伝えて、組織を作っていくことだったんだよね。
「ferret」も少しずつ伸びたから、ビジネス側へいこうって選択したのが、2017年頃だったかな。ちょうどこのタイミングで、「86世代」のみんながそれぞれの道に分かれ始めたと思う。
カツセ:
みんながポジションを取りはじめたのも、ちょうどその頃だよね。個人から脱却していった人と、より専門的なライターを目指した人と、より効率的な働き方を目指した人。多分、みんな体力的に限界を感じていたんだと思う。このままだと、若い世代に負けるなって。

いいたか:
僕たちはホームランを打てないみたいって葛藤が、どこかにあった。ちょうどWebメディアについても、質か量かって議論があちこちで聞かれる時代だったよね。一定量を出さないとユーザーの課題解決はできないっていう認識を持つ人もいたり。
カツセ:
Webメディア論の議論が盛んだったよね。
いいたか:
そうそう。そこで僕たちは、マーシャル・マクルーハンやメディア社会学とか、学問にどっぷり入っていったんだよね。今思えば遅いよね(笑)。
カツセ:
実はこの頃、ひとつ転機があって。2018年に、バズが得意なライターを集めてタイアップ記事を出しまくるっていう、かなり乱暴な企画があったんですよ。そこではじめて、リツイート数で他のライターさんたちに勝てたんです。
元からヨッピーさんやサカイエヒタさんに憧れていたわけだから、その結果は嬉しかったんですけど、1位になった途端、達成感と同時に、あせりを感じ始めた。この状態をずっと続けるのは無理なのも明らかだし、5年後どうやって食うんだろうと思って、まずは体張るのをやめました(笑)。
この辺りからじゃないかな、いわゆる「エモ文脈」が流行りだしたのは。
いいたか:
一時期、「エモい=カツセマサヒコ」みたいなイメージだったよね。このポジションを取れたのは大きいと思うよ。
カツセ:
その頃、失恋とかのテーマをみんながシェアしていると思ったから、ツイートを切り替えてさ。でも約3年経過して、いまではまた「エモ」が当時と違う捉え方をされてきているでしょう? 僕は毎回、そうした時代の波に呑まれながら、溺れないようにしているわけ。
そうこうしているうちに、いいたかさんはこの領域からいなくなっちゃったわけだよ(笑)! そりゃあせるよね。
いいたか:
カツセさんはすごいよね。ずっと時代のトレンドと戦っていて、小説にしろエモ文脈にしろ、いい決断がその都度ハマっている。狙ってできないよそんなこと。一方で、僕はある程度「ここまではいくよね」って狙えるけれど、それ以上はトレンドの波にしか動かせないわけだし。

カツセ:
怖いけどね。トレンドの波は読めないから。もしもエモ文脈の波にいまも乗っていたら、炎上していたかもしれない。そういう不安は今後も常に付きまとうから。
判断基準は「楽しそうか、何かありそうか」
私がエレン:
SNSを通して、人生が大きく変わったって感覚はありますか?
カツセ:
僕はだいたいSNSがきっかけで人生が動いています。ライターに憧れたこと自体、Twitterがないと無理だった。書籍も、SNSがなければ実現しなかっただろうし。時代の恩恵を受けたおかげで、自分にオファーがきている。つくづくSNSの人だなって実感します。悔しいですけどね(笑)。
私がエレン:
なぜそう思うんですか?
カツセ:
いつまで経っても、実力ではなく、時の運でやってきたと感じちゃうからですかね……。ただ、恩師として尊敬している人に、「お前はただ運がよかっただけかもしれないけど、運をつかむ才能はあったね」っと言われたんです。それを聞いて、「ならよしとするかな」って心境になりました(笑)。
いいたか:
僕も、尊敬する経営者に同じことを言われたことある。「お前はすごくいい場所にいて、いい選択をしている」って。なぜそんなことができるの? と聞かれるんだけど、うまく説明できないんだけよね。
ホットリンクで改めてSNS業界に入ったのだって、SNSがビジネスとしてより本質になっていくと思ったからなわけで。実際にSNS業界に戻ってみたら、同じ人に「また来たな」って言われた(笑)。「お前が行く場所には、なにかが起きるのかもしれない」って。
私がエレン:
ベクトルは違うけれど、そこは共通しているんですね。なにか直感が働いているとか?
いいたか:
僕が判断するときは「どっちに行ったら楽しいか」しか考えない。つらさも含めてね、「こっちの方がつらいけど、やってみたら何かありそう」って。

カツセ:
僕もそうかな。ただ、楽しそうだと思いつつ「このレールに乗っても、いつか途切れるかもしれない」っていう危機感もある。多分、いいたかさんも僕も、次はこう行った方がいいなってことに人よりやや早く気づけるタイプな気がします。
カツセマサヒコは、どこへ向かう?
いいたか:
カツセさんはいま、次の本を書いているわけじゃん。これってすごいプレッシャーにならない? 1冊目が当たっている人ほど、2冊目っていろいろ言われるじゃん。1冊目を超えられるのか、とか。
カツセ:
なるなるなる!
次の一手という意味合いだと、2冊目はかなり「見られている」って感じるね。でも、小説を書いたことでライターとは違うステージが見えたから、そこはすごく安心したかな。
ライターを約7年やって、この先も道は続いているけれど、自分はずっと走り続けられるか分からない。そう思っていたところで、もうひとつ新しい地図が手に入ったのは、よかったですよね。
いいたか:
今後、カツセさんはどうなっていきたいの? もう少しここで頑張っていきたいみたいなジャンルはある?
カツセ:
小説の世界がわあっと広がったところなので、そこでしばらく足掻いてみたいです。2作目の小説で、「お前はどちらへ行くのか」を問われている。いま書き終えてみて、また少し可能性を感じているので。
でもそうすると、もはやネットの人ではなくなるし、本当に身近なロールモデルがゼロになるんだよね。それがちょっと怖い。
いいたか:
ネットも新しい人が出てきているしね。元々すごい人だったけど、同世代のDEの牧野圭太さんがいて。あと、一緒に仕事をすることもあるarcaの辻愛沙子さんとか、本当にすごいと思う。
カツセ:
下の世代のSNSネイティブはさ、本当に優秀だよね。価値観が全然違うというか。
いいたか:
いまの子達は本当に賢い。自分の主張を持って発言するなんて、僕はやってなかったもの(笑)。
カツセ:
気にするものが何もなかったよね。自分たちのことだけを考えていればよかった時代というか。それこそ、この記事なんて未来ある若者が読んでも全然楽しくないですよね(笑)。ただの「86世代」対談でしかないもの。
いいたか:
昔話ばっかしやがってって感じ(笑)。当時のSNSは、フタを開ければ「仲間たちが騒いでコンテンツを盛り上げてくれました」って話に過ぎない。みんながやたら、自分のコンテンツをリツイートする時代というかさ。
カツセ:
まあ、それはそれで楽しかったけどね。
いいたか:
イヤな時代ではなかったよね。SNS上の人間関係や距離感が、いまよりもずっと近い感じ。
カツセ:
きっといまはいまで、別のなにかがあるはずだよね。いいたかさんの『僕らはSNSでモノを買う』を読んで、インフルエンサーの時代は終わると感じて。じゃあ自分はどうしようっていうのは考えました。
実際に、当時「86世代」で盛り上がっていたことを誇りにしていた人たちは、みんな影響力を失っている。いままさに、そういう時代を迎えているよね。
いいたか:
そうだね。あの時はあの時でとても楽しかったし、同世代がとてももがいていた。
今はそれぞれ違う道に行ってはいるものの、Twitterを見ればどんなことをしているかわかるし、応援もしている。これから、もっと色々移り変わると思うけど、100年時代と言われているからこそ、まだまだもがいて頑張っていきたいね。
そして、下の世代の方がよりデジタルネイティブで優秀だから、一緒に何か作っていきたいって想いもあるよね。

―カツセマサヒコさん、本日はお忙しいところありがとうございました。
今回の「ザ・プロフェッショナル」もお楽しみいただけましたか? 本シリーズでは、今後も各業界で活躍するさまざまなプロフェッショナルをお招きして対談を行ないます。過去の記事はこちらからご覧ください。