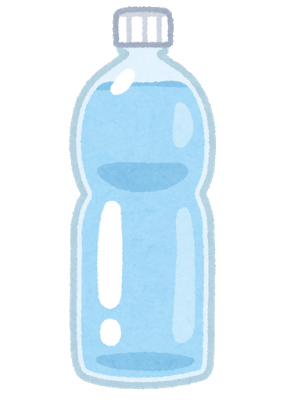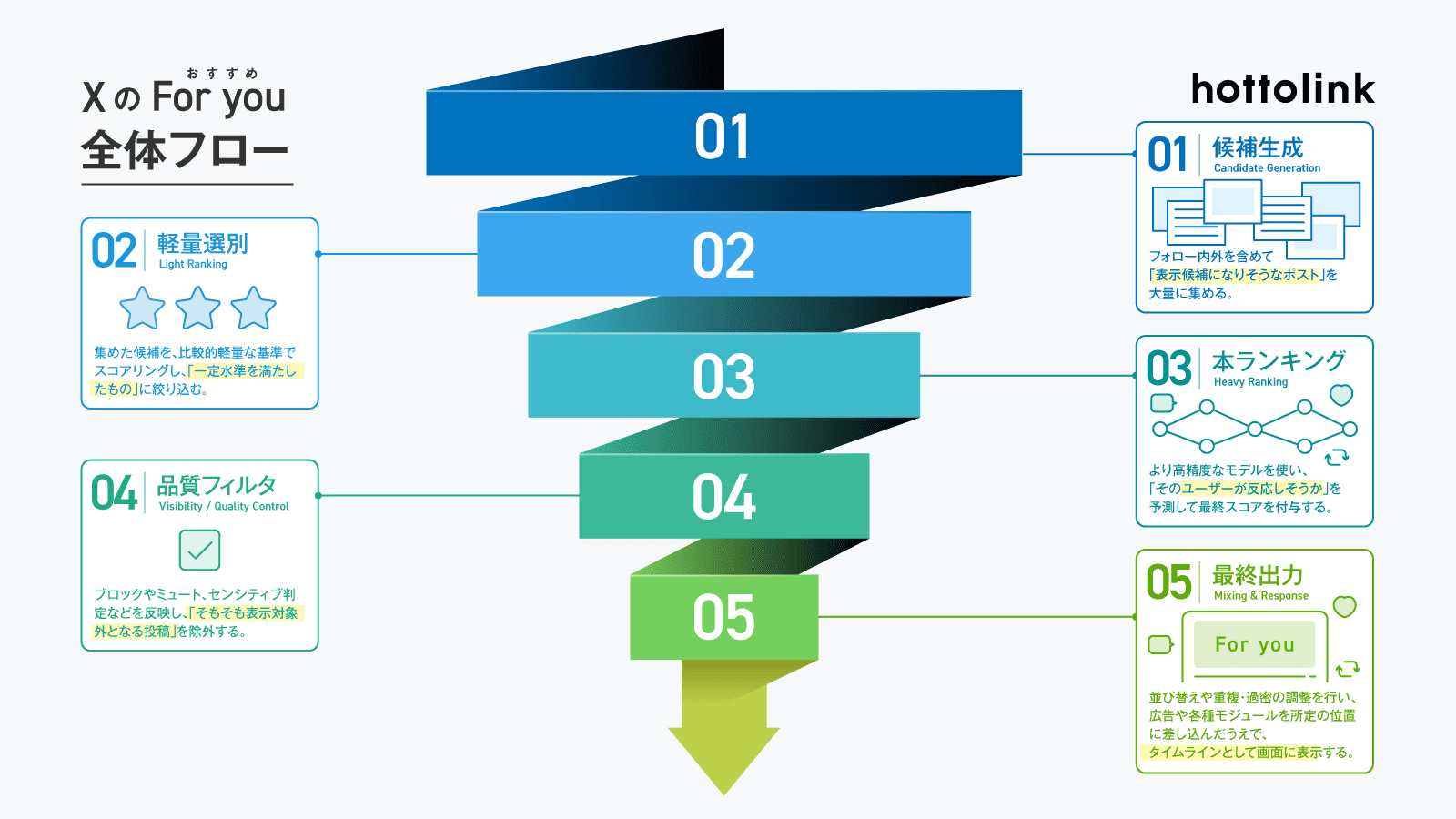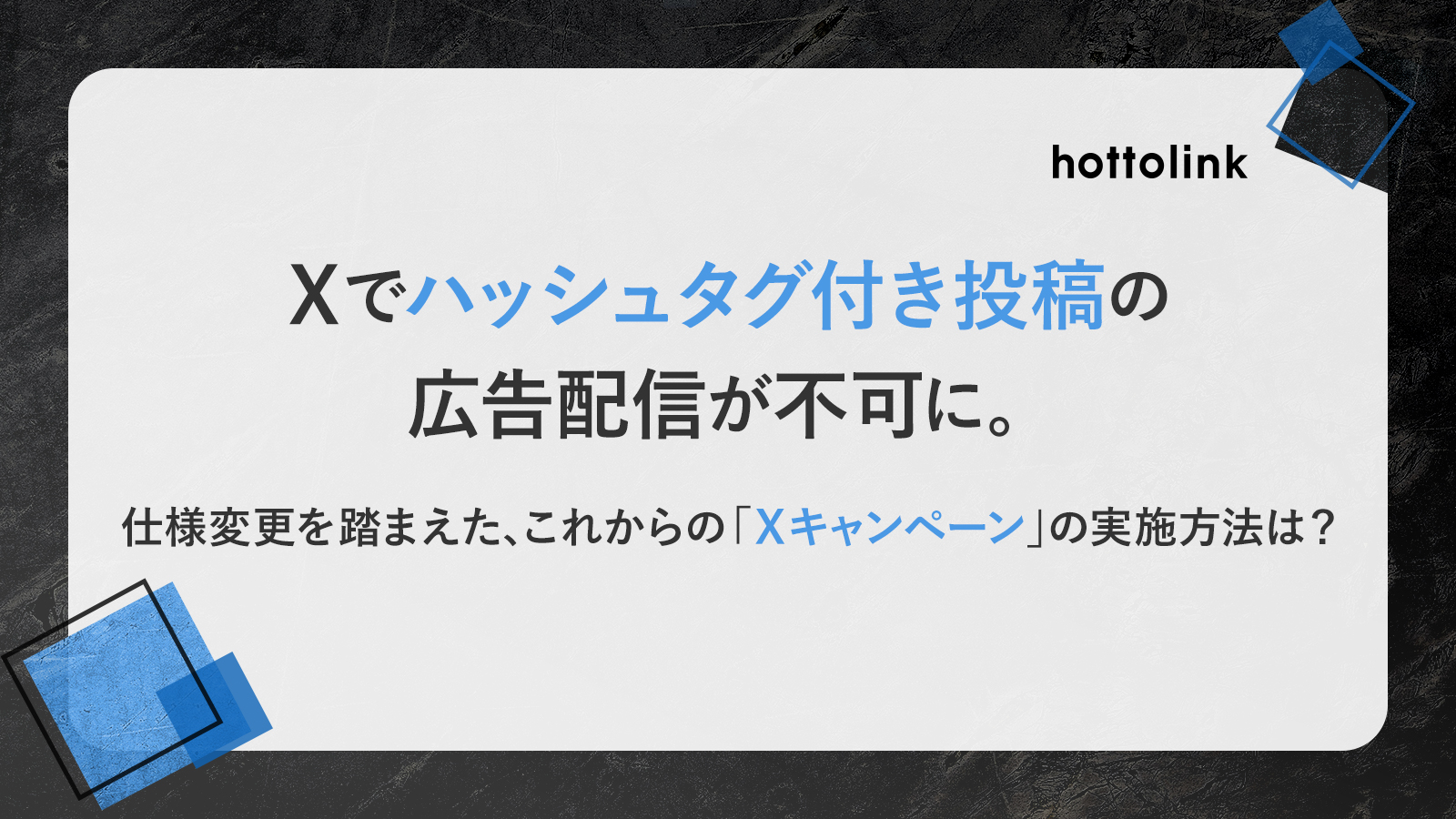※こちらの記事は2019年11月に社員の個人noteで公開された記事をベースに加筆修正を施しています。
ホットリンクの石渡広一郎と申します。
当社が新たに取り組んでいる、PGCマーケティング。先日、弊社のコンサルタント増岡が公開した『ソーシャルメディアマーケティングにおける「PGC」の必要性』という記事は、関係各所で話題になっているようです。大変うれしく思っています。
私は以前、芸能事務所で働いていたこともあり、その経験を買われてPGCマーケティングに取り組むことになりました。SNSのプロモーション手法としてよく挙がるインフルエンサーマーケティングとは全く異なるものとして、PGCマーケティングには可能性を感じています。
ペイドメディア思想に基づく一部のインフルエンサーマーケティングには、インフルエンサーが蓄積したブランドを「消費」していると感じることもありました。このPGCマーケティングが、広く普及していくと良いなと思っています。
今回は、まだあまり知られていないこのPGCマーケティングを、コンテンツマーケティングの観点からお話ししていきたいと思います。
コンテンツマーケティングで、情報を変化させる
「コンテンツマーケティング=コンテンツSEO」と考えていたり、「SNSなんて、オウンドメディアの記事タイトルをちょっと変えて配信すればいいんでしょ」ぐらいに考えている人もいるかもしれません。
少し、具体例を挙げてお話しします。例えば、ここに一本の水が入ったペットボトルがあるとします。
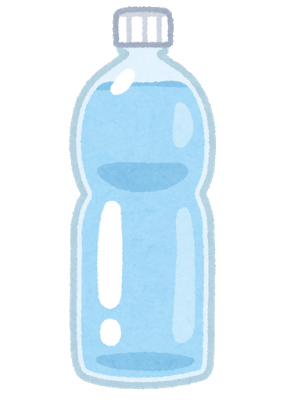
何の変哲もないペットボトルに見えますが、実は素材、製法、評判、製造会社など、消費者に訴求しうる点が複数あると仮定します。
この商品についてWebページを作るときは、これらの情報をまとめて盛り込むことになります。では、消費者はいかにして、この情報に到達するのか。
近時、商品やサービスをローンチする際にはWebページを作ることがほとんどだと思います。(大企業は別として)多くの会社にとって、このWebページの内容を定期的に作り変えることは容易ではありません。Webページを通じた商品やサービスの「見せ方」は、長期にわたって固定化する傾向にあります。
またソーシャルで情報を広めるにも、せいぜいソーシャルプラグインをページに設置して、Webサイト訪問者に拡散を促す程度です。
このような「静的な」Webページに対しては「動的な」コンテンツを用いることで、消費者に訴求したい情報を変化させて発信することが必要となります(UGCの発生を促すには、「人に語られる」コンテンツを提供することも必要となります)。
このペットボトルの例ですと、
コンテンツA⇒「この水は、〇〇の土地から採った天然水だ」
コンテンツB⇒「この水は、特殊な製法を用いて作られている」
コンテンツC⇒「この水は、ミシュランの3つ星シェフが愛用している」
コンテンツD⇒「この水を作った会社の経営者は、元アスリートだ」
といった訴求軸のコンテンツが作れます。
コンテンツマーケティングの利点はWebページだけではたどり着けない潜在的な消費者にリーチし得ること、さらにコンテンツを通じて商品やサービスを知ってもらい消費者の態度変容を引き起こし得ることになります。
上記では4つのコンテンツを活用して商品の訴求点を発信しましたが、一つの商品やサービスを複数のコンテンツで「動的」に語らせ、指名検索を増やし、商品等のWebページに誘導することがコンテンツマーケティングになります。
「バズ」を起こすことにこだわる必要はありません。「n:n」の情報伝播に寄与するコンテンツ、人々の会話の中に登場することを後押しするコンテンツ制作が大事になります。
PGCのコンテンツフォーマットを選定する
コンテンツフォーマットを選ぶにあたっては、それぞれの特性や、表現方法の幅について留意する必要があります。商材がイキイキと描写できるフォーマット選定はもちろん、疑似体験性の高さや、コスト感に合わせて決めると良いでしょう。
A. 画像
まず、画像です。タレントやモデルを起用することで、消費者の目を引くことができます。疑似体験性はそこまで高くありませんが、コストをおさえつつ視覚に訴えることができます。
下記は、「TommyHilfiger」のモデルとして出演している永野芽郁さんの画像です。この画像からは「かわいさ」「かっこよさ」「アーバン」といったイメージを視覚的に捉えることができます。
B. 動画
次に動画です。疑似体験性が極めて高く(コストも高くなりますが)、SNSではリーチを伸ばしやすいフォーマットであり、画像よりも表現の幅が広いものとなります。
下記は、コカ・コーラさんが配信する動画ですが、元号発表を思わせる冒頭のシーンと綾瀬はるかさんが登場するという期待感によって、消費者の興味を喚起しています。
C.記事コンテンツ
さらに、「note」のような記事コンテンツも活用できます。疑似体験性は高くありませんが、コストをおさえることができますし、Twitterのように文字数を140字以内に収める必要がないため、様々な表現手法を用いて情報発信を行なうことができます。
下記は、ロート製薬さんの「note」企業アカウントの記事です。広報担当の方が書いた記事で、ロート製薬さんの製薬事業以外のお取り組みを窺い知ることができます。
D.マンガ
マンガも、代表的なフォーマットです。動画同様に疑似体験性が高い一方で、コストパターンにもバリエーションがあり、また、撮影が難しいような描写もマンガであれば可能となります。
下記は、先日話題になった「ハーシーズゴールド」のPRマンガです。1ページ目から2ページ目への展開が急であり、さらにオチまでのストーリーに「Twitterライク」な強引さもあって、非常に印象に残るコンテンツでした。
最後に
以上、「PGCマーケティング」の代表的なフォーマットをご紹介しました。
フォーマット例としてご紹介してきたコンテンツは、コンテンツ単体としても企画力があるものとなりますが、「PGCマーケティング」はコンテンツそのものの企画力に依存するものではないことを改めて申し添えておきます。
最後に、この記事を読まれた方の中には、自社の商品やサービスには何も消費者に訴求しうるところがない、と考えている方もおられるかもしれません。しかし商品やサービスが、正当な事業活動の中で生まれたものであるならば必ず消費者に訴求しうる点があると、私は思っています。
それは、その商品やサービスが誕生する過程の中で関係者の方々が直面した問題や、解決するまでの試行錯誤それ自体が消費者に訴求しうるものだと考えているからです。
ぜひ、そのような商品やサービスの魅力発信を、これからもご支援していきたいと考えています。
最後までお読みいただきありがとうございました。
Twitter:石渡広一郎