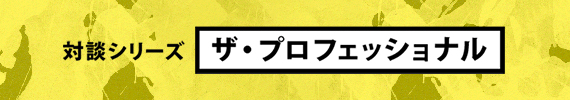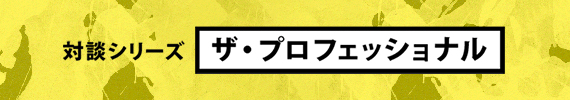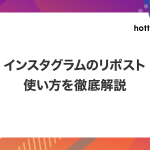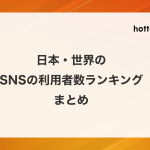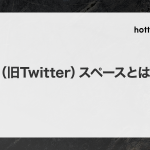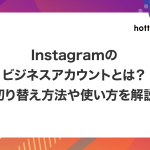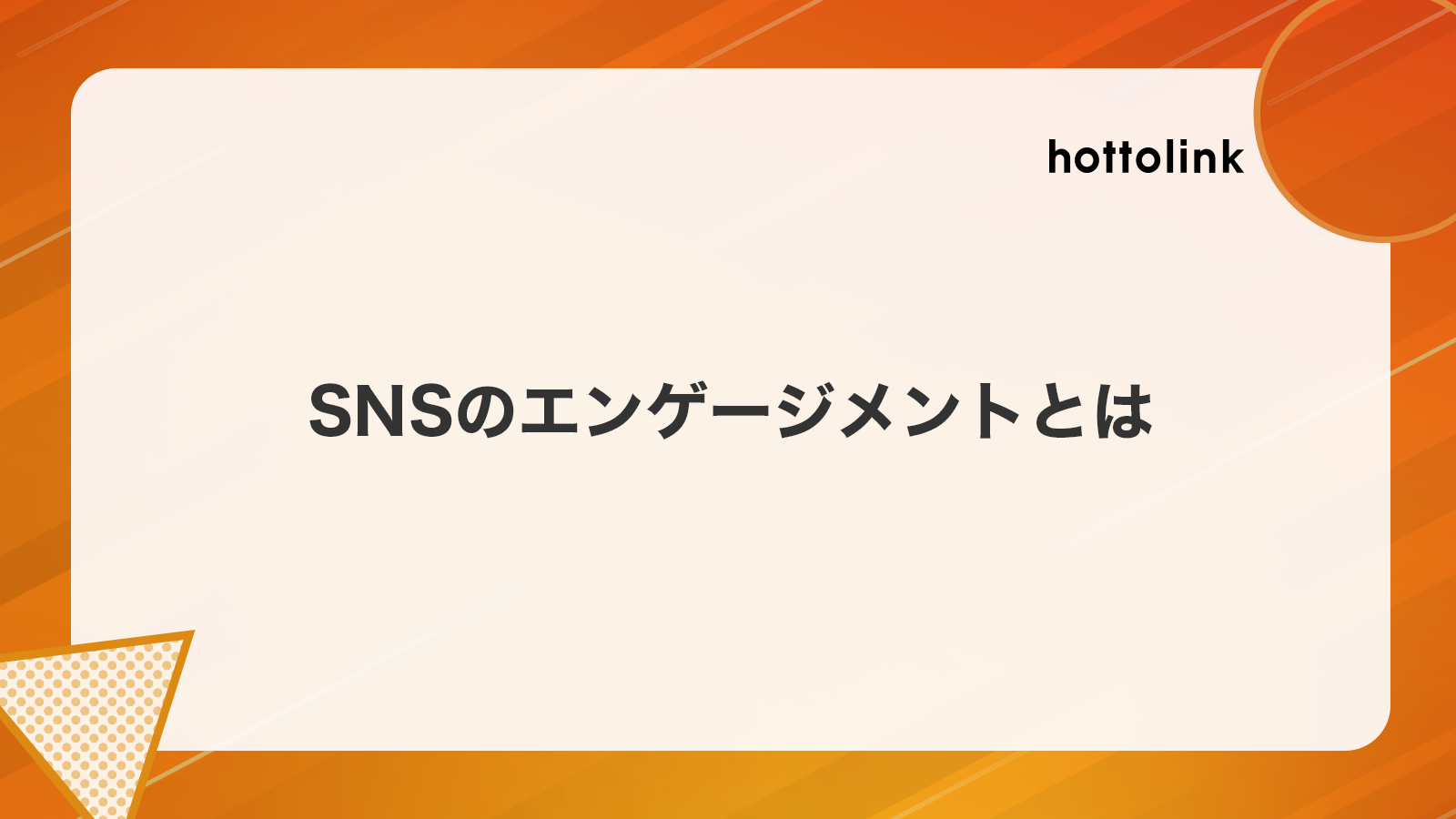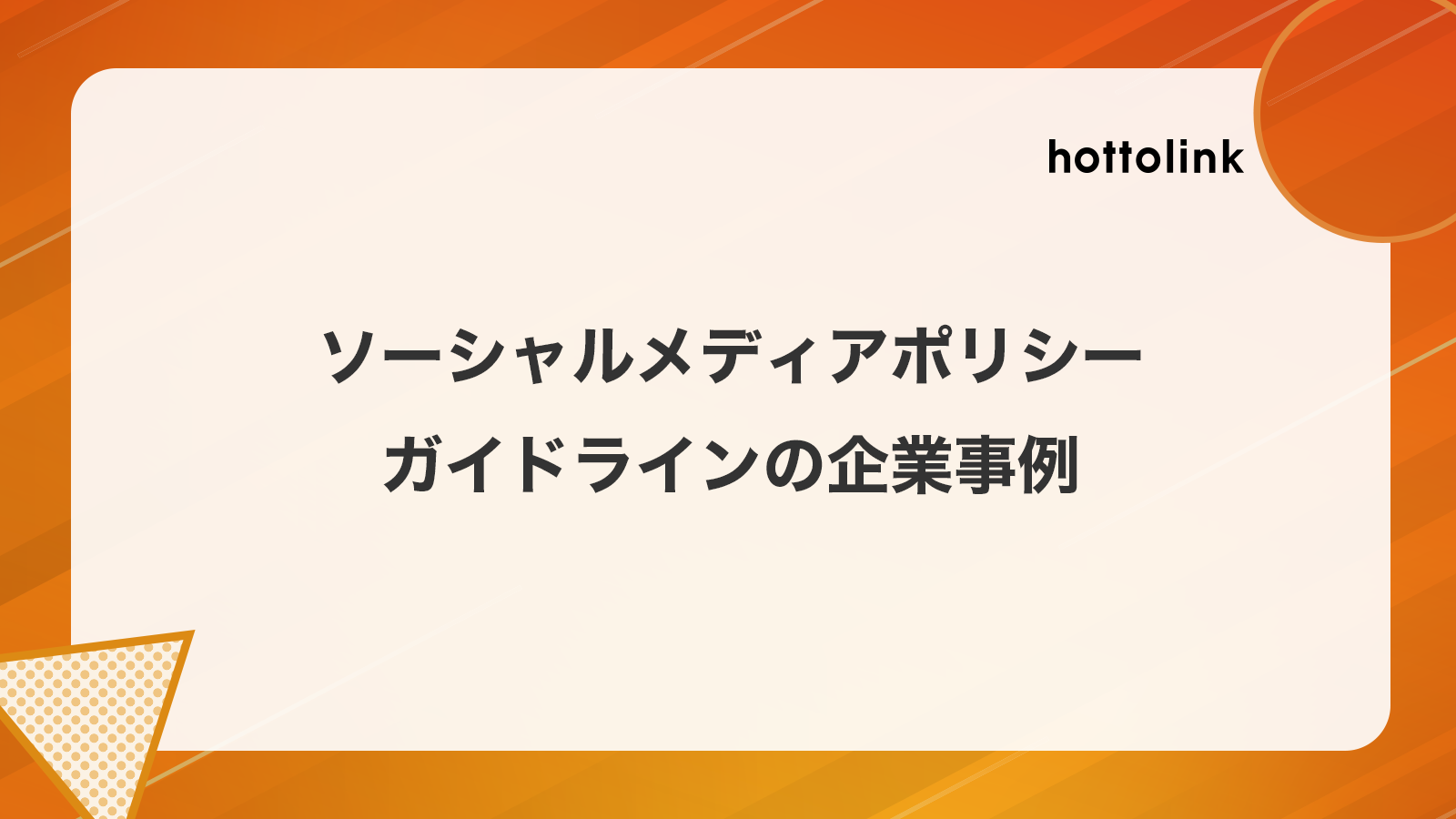最終更新日:2024年1月9日
各業界で活躍するさまざまなプロフェッショナルとホットリンクCMO・いいたかが、SNSやマーケティング、ビジネスのあり方について考える対談シリーズ「ザ・プロフェッショナル」。
今回のゲストは、ソフトバンク株式会社、メディア統括部長の井上大輔さんです。
ニュージーランド航空やユニリーバ、アウディジャパンなど、幅広い業種でマーケティングを経験してきた井上さん。今回は「ソーシャルメディア×コンテンツ」というふたつの軸を中心に、SNSにおける目立つコンテンツやアカウントの特徴、いいコンテンツの持つ性質などの観点から、7,000字以上にわたってお話を伺いました。
(執筆:サトートモロー 撮影:小林一真 編集:澤山モッツァレラ)
井上大輔:マーケター、ソフトバンク株式会社コミュニケーション本部メディア統括部長。ニュージーランド航空、ユニリーバ、アウディなどでマネージャーを歴任。ヤフー株式会社マーケティングソリューションズ統括本部マーケティング本部長を経て現職。NewsPicksアカデミアプロフェッサー。著書に「マーケターのように生きろ(東洋経済新報社)」「デジタルマーケティングの実務ガイド(宣伝会議)」など。
※本対談はリモートにて収録されました※
ソーシャルメディアに見られる3種類の「立ち居振る舞い」
澤山:
本日は、よろしくお願いします。今回の対談は、井上さんが9/1のプライベートな勉強会にいいたかをお招きいただいたことがきっかけで実現しました。しかも井上さんの新刊(『マーケターのように生きろ』)の宣伝はいらない、というお気遣いまで(笑)。
いいたか:
本書、すごく勉強になりました。例えば「口コミの裏には、『必死の働きかけ』がある」という記述がありましたよね。
|
口コミの裏には「必死の働きかけ」がある
「本当にいい商品」をつくったら、むしろ「本当にいい商品」であればあるほど、それを多くの人にしっかりと伝えていかなくてはならないのです。
(中略)
SNSでの情報発信を何年もコツコツと続け、徐々にファンを増やし続けることで市民権を得たブランドもあります。(中略)「口コミで広がった」という結果だけについ目が行きがちですが、商品をつくり、あとは座して待っていたというヒット商品は、実際にはほとんど存在しません。
『マーケターのように生きろ―「あなたが必要だ」と言われ続ける人の思考と行動』(井上 大輔著/東洋経済新報社刊)
|
これは、とても本質的な記述だと思っていて。
井上:
そうですね。自分をコンテンツとしたときの、ソーシャルメディアでの立ち居振る舞いには、3種類あると思っています。
●一つ目:私見をうまく言語化して伝える言語系プラットフォームとしての立ち居振る舞い。
●二つ目:焚き火のような立ち居振る舞い。いじられビリティを発揮して、自分をみんなが囲うなにか(話題の中心)にするもの。
●三つ目:より能動的に動く、パーティホストのような立ち居振る舞い。
ソーシャルメディアの興味深いところは、共時性が強いところだと考えています。「みんなが見ている」こと自体に、面白さが宿るというか。
ノルウェーの公共放送「NRK」が、薪が燃えるシーンだけを流し続ける放送をしたんです。通称「スローテレビ」と呼ばれる番組なんですが、焚き火の回は視聴率が約20%もありました。
いいたか:
聞いたことがあります。そんなに視聴率が高かったんですね。
井上:
あの番組こそ、「みんなが見ている」ことの面白さを体現していると思うんです。
教会のミサは英語ではマス(Mass)といいます。マスメディアの「マス(Mass)」と綴りも読みも一緒です。ミサという場所に人々が集い、同じ時間を共有することで、人は精神的な充足を得られます。マスメディアにも似たようなところがあると思っています。
「その場に集まる」という意味では、焚き火をみんなで眺める構図も似ていると思いませんか?
いいたか:
そうですね。
井上:
ソーシャルメディアにおいても、ある種のミサ性(マス性)が重視されるのかなと。そうすると、自分が焚き火のような輪の中心になってフォロワーに「共時性」を与えられる人は、ソーシャルメディアでも高い存在感を発揮すると思うんです。5歳さんはこのタイプに近い気がします。
三つ目の「パーティホスト」でいうと、田端信太郎さんがこのタイプだと思います。自らお題を投げ込んで、議論している様子をリツイートして盛り上げるわけです。
言語化タイプ、焚き火タイプ、パーティーホストタイプ。どれかひとつに秀でていれば、たくさんの口コミを生み出せるんじゃないかなと。
いいたか:
このカテゴライズは面白いですね。それで言うと、焚き火タイプはTikTokやInstagramに多く見られる立ち居振る舞いだと思います。
一方Twitterは、言語化タイプやパーティホストタイプが強いかな。リツイートという機能があることで、赤の他人まで会話や話題を届けられる。こうしたプラットフォームの特性が、立ち居振る舞いにも影響すると思いました。
共時性をいかに生み出すか
井上:
「共時性」は、ソーシャルメディアにおけるキーワードのひとつだと感じています。
フォロワー数って、幾何級数的に伸びるじゃないですか。初期段階より、アカウントが成長してからの方が伸びが大きい。これは、共時性が利くからと思うんですよね。
フォローが多い人の発言には、共時性がある。例えば有名なテレビタレントが「タコライスおいしい」とつぶやくと、それだけで価値が生まれる。発言内容だけでなく、多くの人が見ていることも価値なんですよね。
いいたか:
炎上事例でも、共時性の高いアカウントの言及がトリガーになることもありますよね。
バイト中にふざけて冷蔵庫に入るケースなんて、最初は学生が身内だけで「お前バカやってんな」みたいな会話してるだけなんです。それが、例えば隣の高校の生徒が見て、面白がって拡散され、伝播していく。
そして共時性の高いアカウントに見つかって「けしからん」となり、その瞬間に悪ふざけから「悪いこと」に変質し、大炎上に発展する。このケースは、井上さんのお話に当てはまると思いました。
井上:
一定数の閾値を超えないと、共時性は発生しないんですよね。しかも、努力と結果が必ずしも直結しない領域です。この分野は、ちょっと研究してみたいですね。
いいたか:
それこそ、本のオビも共時性を生むモノですよね。「あの人が勧めるなら、多くの人が手に取るはず」という期待で書いてもらうわけですから。昔から存在する概念が、SNSの中で形を変えただけとも捉えられそうです。
井上:
共時性について、こういう経験もありました。ある知り合いがFacebookでライブ配信をしたので、何気なく覗いたんですね。そうしたら、閲覧者が僕1人だったんです。
知り合いの話を、たった1人で聞く。この状況に、強烈なストレスを感じたんです。「同じ場所に人がいる」ということは、すごく大事なんだなと感じました。
コンテンツだけにフォーカスすると、向き不向きがありますよね。特定の事象をうまく言語化する、面白い動画を撮る、マジックをやる、かっこよくダンスを踊る……でも、それだけじゃないんですよね。
「共時性」は、こうした手法論に一石を投じる概念かなと思います。
身内と世間の乖離に気づけるか
いいたか:
SNSって、自分の観測範囲と世間とで、流行っているものが大きく異なるケースがありますよね。これを認識できてない人、意外に多いと思うんです。
井上:
その話は、「マーケターの職業病」というテーマにつながりますね。
まず、相手を理解する。自分を客観視し、周辺がすべてではないと当たり前に理解する。これを職業としてやるのがマーケターだと思います。
例えば食器洗い乾燥機とFAXでは、どちらが国内で普及しているか。実は、FAXなんですよ。世帯普及率でいうと、ゲーム機なんかより普及している。
澤山:
そうなんですね。
井上:
ほかにも、こういう話があります。日本において、エアコン2台持ちとクルマ2台持ちの世帯はどちらが多いか。これ、正解は「クルマ2台持ち世帯」です。
都会に住んでいたら、直感的にはわからないと思うんです。都内は、クルマを所有する世帯が珍しいレベルですから。でも全国で見ると、2台持っている家は多いんですよね。
こうして思い込みを疑いデータを見る習慣を持っておくこと、お客様と自分の周りの差異を感じ取ること。これらは、マーケターとして基本の所作だと思います。なので、SNSでも職業病的にそれをやってしまうところがあります。
いいたか:
本質ですね。ソーシャルメディア領域にいると、SNSってすごく普及していると思っちゃいます。
でも、例えば沖縄ではTwitterがあまり普及していないんです。その代わりInstagramが人気で、さらにテキスト媒体よりもラジオ広告が有効だったりします。こうしたファクトはフラットに見れば理解できるけれど、そうでないと痛い目を見ますね。
シャローコンテンツとディープコンテンツ
いいたか:
井上さんにとっての「いいコンテンツ」の定義を、改めて伺いたいです。
井上:
前提として「コンテンツのよさ」は、そのものの魅力だけで定義されないと思うんですよね。
例えば「焚き火を延々と流す」映像。焚き火それ自体に、コンテンツの価値はそれほどない。「みんなが見ている」ことが付加価値になるわけです。こうした掛け合わせを認識しないと、ソーシャルメディアで起こる事象は理解しにくいと思います。
いいたか:
以前お話した時に、「シャロー(浅い)コンテンツ」「ディープ(深い)コンテンツ」という分類をされていましたよね。この2つは、どう定義できるんでしょうか。
井上:
シャローコンテンツは、より直感的に理解できるコンテンツです。時間も集中力も使わず消費できる。逆に、ディープコンテンツは時間・集中力・知力などが要求されます。特にディープコンテンツは、イマーシブ(没入できる)ですね。
それぞれ、よさがあります。どちらか一方だけ好き、という人はいないと考えます。僕も、状況に応じてそれぞれを消費します。
また、このシャロー性とディープ性は、一つのコンテンツに同居すると思います。例えば『呪術廻戦』は、すごく設定が複雑です。『アベンジャーズ』などのマーベル作品も蓄積された歴史があり、簡単には入り込めません。一方で、それぞれの登場人物は直感的に面白いので、小さな子どもでも直感的にも楽しめたりします。
最近は、コンテンツ消費の2極化が起こっているのではないでしょうか。ソーシャルメディアは基本的にシャロー、気軽に繋がる一方でストレスを感じることもある。別のものに没頭したいとき、ディープなコンテンツが求められる。そう仮説を立てています。
いいたか:
僕も基本的にはディープコンテンツが好きですが、日常で触れているのはTikTokなどシャローコンテンツなんですよね。何も考えずに観て、気づいたら時間を費やしていたパターン。
シャローが悪いとかではなく、TikTokのプラットフォームの強さですよね。シャローとディープで、それぞれアプローチ手法が違う。
井上:
そうなんです。僕もシャローという言葉を、悪い意味では使っていません。
ニコラス・G・カーの『The Shallows(邦題『ネット・バカ インターネットがわたしたちの脳にしていること』)』という、興味深い書籍があります。著者の主張を要約すると「インターネット上のコンテンツは、仕組み上必然的にシャローになっていく」ということなんです。
これはなぜか。インターネットでは、広告が邪魔だと毛嫌いされる一方で、ある種の邪魔は歓迎されるんですよね。チャットやメールなど、さまざまな形で通知が来る。書斎で読書をしているとき、人が入ってきて手紙とか渡してくると邪魔だと感じませんか? せっかく集中していたのにって。
いいたか:
たしかに。
井上:
でも、SNSで「ゆうたさんから、いいねが届きました」という通知がきたら見ちゃいます。自分にとっていい情報だからではありますが、「邪魔される」ことに変わりはない。
そうしたいい知らせを待つことで、集中力は落ちた状態で固定化されます。自然、集中しなくても消費できるコンテンツが求められる。ホームページ、ブログ、Twitter、今ではInstagram、TikTokと、徐々に写真・動画が主流になりました。集中力がなくても後追いできるコンテンツへ変化しているんですね。
人気漫画に包含される、シャローとディープそれぞれの魅力
井上:
一方、没入感がほしくてディープコンテンツを求める人も増えています。例えば『呪術廻戦』は、かなりディープだと思うんですよね。『進撃の巨人』も世界観が確立され、多くの考察を生んでいます。
いいたか:
『ONE PIECE』も回を重ねるごとに複雑になっていて、ディープ寄りだと思います。
井上:
最近の作品は、ハイコンテクストになっている気がしますね。一方で、これらの作品はマス受けもしています。
いいたか:
アニメで考えてみると、多くの人が「ディープコンテンツに時間を費やしている」とも感じますね。
井上:
先ほども話しましたが、魅力的な作品はディープとシャロー、両方の性質を合わせ持っているんだと思います。
『鬼滅の刃』は設定が入念に作りこまれた作品ですが、読んだこともない幼稚園児でも「鬼滅ごっこ」をします。炭治郎や禰豆子といったキャラを知っているだけでも、ごっこ遊びが成立する。つまり、シャローな魅力も持っているんですよね。
キャラクターの魅力というシャローな要素と、世界観というディープな要素。このふたつが共存しているのが、最近のスマッシュヒットの特徴かなと。
いいたか:
キャラクターがわかりづらかったら、話が見えなくなってしまいますもんね。こういう目線を持ってSNS上の流行を捉えると、客観視の精度は上がりそうですよね。
サウナはシャローコンテンツ?
井上:
サウナ好きの経営者、多いですよね。これは、サウナがシャローだからではと思ってるんです。
僕もサウナ好きですが、「考えなくていい時間を過ごせるから」なんですよね。思考力をいい感じに鈍らせてくれる。日ごろ頭をフル回転させる経営者にとって、魅力なのではと思います。
いいたか:
間違いなくありそうですね。サウナ以外にも、トライアスロンやランニングが好きな経営者は多いですよね。「身体に一定の負荷がかかり、一時的に思考が鈍る」感覚はサウナと共通する気がします。
井上:
「頭を鈍らせる」ものは、コンテンツとして優れているのかも。僕自身、「なぜ」を深堀りして考えていくタイプで、気がついたら疲弊している部分があると思うので。これをソーシャルメディアの文脈で説明すると、ちょっとむずかしいですが。
澤山:
ソーシャルメディアを使っていると、常に認知負荷がかかっている状態にありますよね。気づかないうちに蓄積されたストレスから、シャローなコンテンツを求める部分はあるのではと思います。
脳がフレッシュな時間帯はディープを、やや疲れた時間はシャローを、と行き来する部分はあるのかなと思いました。
井上:
ああ、それは間違いなくありそうですね。
SNSの有毒性と向き合う
井上:
以前、Facebookが報告書において「InstagramはToxic(有害)である」とした報道がありました。ああいう話題が出てくると、SNSの有害性について考えてしまいますね。
いいたか:
そうですね……。
井上:
この間、人間ドックに行ったらビックリしたことがあって。待合室にいたら、10人ぐらいいる人がみんな「何もやってなかった」んです。
要はスマホを見ていない。僕は終始スマホをいじっていましたが、ゆうたさんできますか? 5分もスマホを見ないでじっとするって。
いいたか:
絶対無理です(笑)。健康診断に行くときも、必ず本やKindleを持っていきます。近場に出るときも、Kindleを持参しますね。
井上:
それって異常なんですよね(笑)。僕たち、SNSを使いすぎているがゆえに、ちょっとした異常者なんですよ。僕はもともとじっとしていられないタイプで、左手でコーヒーを注いでいる時間すら待てず、右手で水を飲もうとしてこぼしてしまったりしますが(笑)。ソーシャルメディアは確実に、この「スキマ時間を埋めたくなる」性質を悪化させているように思います。
いいたか:
スマートフォン自体にも、スキマ時間を埋めさせる性質がありますよね。
井上:
僕は周囲から「Twitterすごく頑張ってますね」と言われるんです。でも、僕は何も努力していなくて。少しでも時間が空いたら、何かしないと気がすまないだけなんです。
いいたか:
Twitterを見ていると、僕らのように多動な人たちがいる一方、すごくヒマでTwitterそのものが大好きって人もいると思います。
僕の場合、Twitterのコンテンツは消費していません。スキマ時間でバーっとつぶやいてるだけなんですよね。「多忙なときもつぶやく頻度が変わらないですね」って言われるんですが、タイムラインを見ていないんですよね。
井上:
僕やゆうたさんのような多動な人には、そういう使い方が合っているのかもしれませんね。小さなスキマ時間をうまく埋めてくれる存在として。
澤山:
ソーシャルメディアの中毒性は深刻な課題ですし、SNSマーケティングに関わるわれわれは、真剣に取り組まなきゃいけない問題だなと思いますね。
いいたか:
本当にそうですね。
モラルライセンシングとしてのディープコンテンツ
井上:
実際問題、SNSは先ほどの報道のように悪影響が指摘されています。先ほどの「ディープコンテンツへの揺り戻し」は、ここにも関わっていると思います。
ディープコンテンツは、モラルライセンシング(心理学者ダニエル・カーネマンが提唱した、「よい行ないをしたら悪い行ないをしてもいい」と感じる心理のこと)として働いているというか。
僕も、そういう気持ちが働いていることがあるんです。『失われた時を求めて』のような難解な長編小説を読んて、徳を積んでからソーシャルメディアを使うというか(笑)。
いいたか:
それは、わかりますね。
井上:
ゆうたさんが外出時に本を持ち歩くのも、そういう気持ちがあるのかもしれないですね。
いいたか:
そうですね。スマホでも本は読めるんですが、SNSの誘惑が100%勝ってしまうんですよ。それがわかっているんで、必ず本も持ち歩くようにしています。
井上:
今後、ディープとシャローの併用という概念が広がっていきそうですよね。
いいたか:
ありえますね。SNSばかりやると、「これだけじゃダメだ」という思考が働きますから。「ここまで読んだらSNSを開いていい」という、学生時代の勉強のような思考が働いているのかもしれません。
井上:
哲学が流行っている理由も、同じ背景がありそうですね。シャローコンテンツを消費し続ける罪悪感から、自分を救いたいというか。ディープコンテンツに触れることで、シャローコンテンツを思い切り楽しめるようにしてあげるみたいな部分があるのかもしれませんね。
…なんのまとまりもない話でしたが、大丈夫ですか?(笑)
いいたか:
僕は、面白い投げかけになる記事だと思いますよ(笑)。
今回の「ザ・プロフェッショナル」もお楽しみいただけましたか? 本シリーズでは、今後も各業界で活躍するさまざまなプロフェッショナルをお招きして対談を行ないます。過去の記事はこちらからご覧ください。